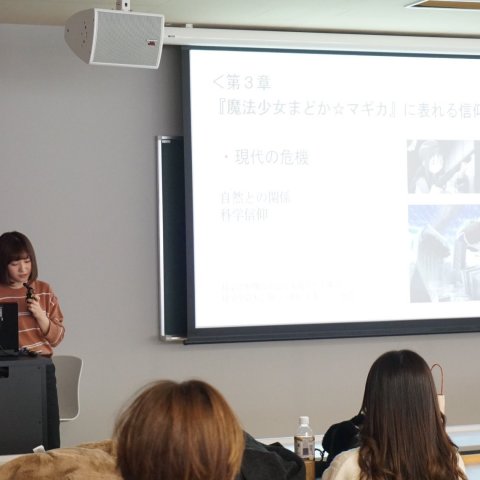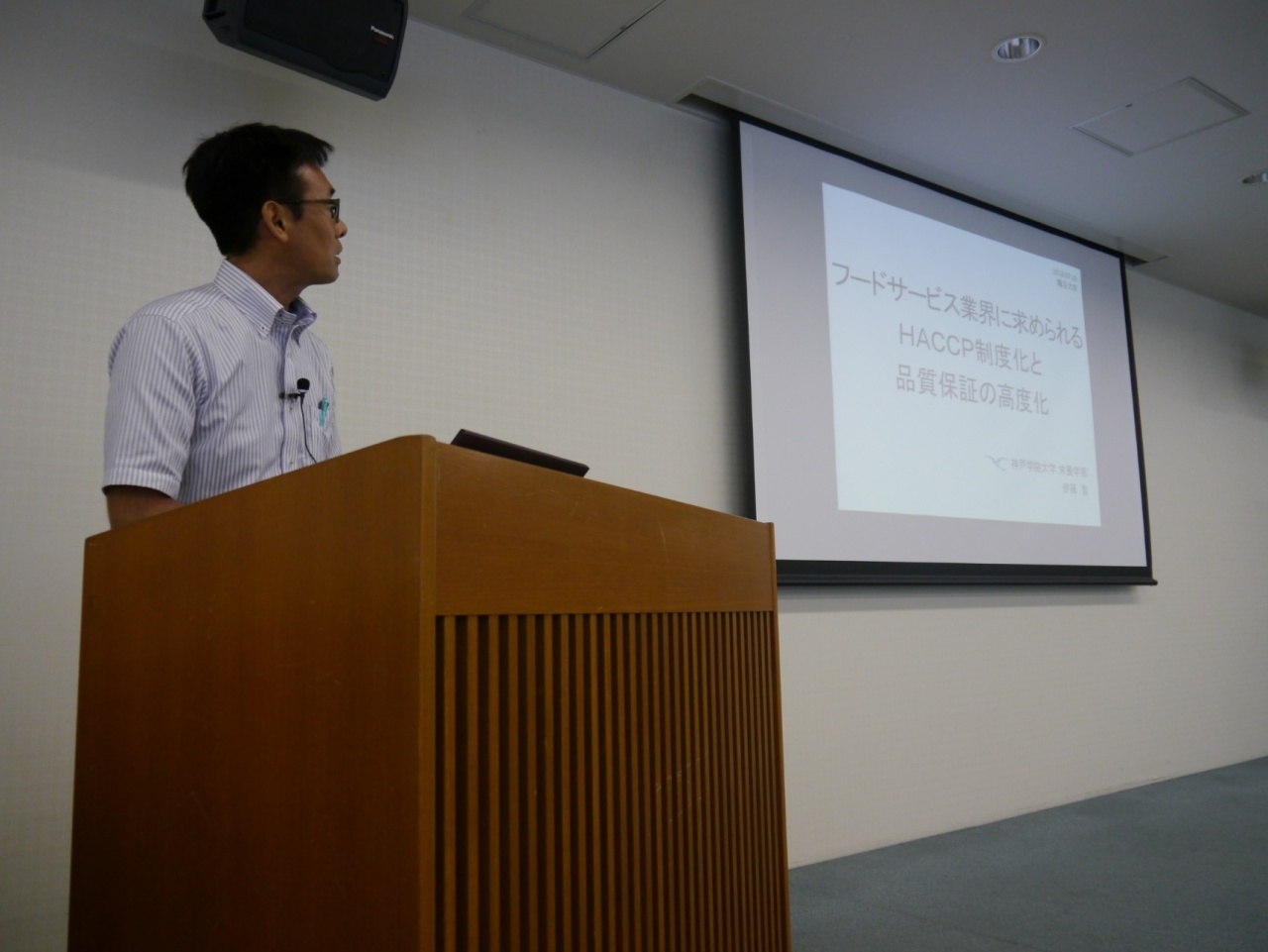龍谷ミュージアム 秋季特別展 「日本の素朴絵-ゆるい、かわいい、たのしい美術-」会期:9/21(土)~11/17(日) 8/1(木)~前売り券販売開始
【本件のポイント】
・9月21日(土)から秋季特別展「日本の素朴絵-ゆるい、かわいい、たのしい美術-」を開催(現在、三井記念美術館<東京>で開催中)
・開幕に先立ち、8月1日(木)から前売り券の発売を開始
・本展は、これまで本格的に取りあげられなかった、ゆるやかなタッチでおおらかに描かれた様々な時代・形式の「素朴絵」を紹介する展覧会
・仏画、大津絵、白隠、仙厓、尾形光琳の作品、加えて埴輪や仏像などの立体物まで展示件数は98件
・重要文化財「仏鬼軍絵巻」は本展(京都会場)のみ展示
【本件の概要】
龍谷ミュージアムでは、9月21日(土)より秋季特別展「日本の素朴絵-ゆるい、かわいい、たのしい美術-」を開催いたします。
日本では昔から、様々な形式の作品が緩やかなタッチでおおらかに描かれ、大切にされてきました。それらは「うまい・へた」の物差しでははかることのできない、なんとも不思議な味わいを持っており、見る人を虜にします。
本展では、ゆるく、とぼけた、あじわいのある表現で描かれた絵画を「素朴絵」と表現し、これまで本格的に取りあげられることがなかった様々な時代・形式の絵巻、刷り物、掛け軸、屏風、仏画などに表された素朴絵を紹介することで、新しい美術の楽しみ方をご提供します。
なお、本展のプレス内覧会は、開幕前日の9月20(金)を予定しています。詳細が決まりましたら、案内いたしますので、よろしくお願いします。
【秋季特別展「日本の素朴絵-ゆるい、かわいい、たのしい美術-」 概要】
1 名称 秋季特別展 「日本の素朴絵-ゆるい、かわいい、たのしい美術-」
2 会期 2019年9月21日(土)~ 11月17日(日) 会期50日間
※開館時間 10:00~17:00 ( 入館は16:30まで )
※10月5日(土)、12日(土)、19日(土)、
26日(土)は20:00まで開館時間を延長します。
( 入館は19:30まで )
※休館日 月曜日 ( 祝日の場合は翌日 )
3 会場 龍谷ミュージアム
〒600-8399 京都市下京区堀川通正面下る(西本願寺前)
4 主催 龍谷大学 龍谷ミュージアム、毎日新聞社、京都新聞、NHK京都放送局、
NHKプラネット近畿
5 入館料 前売り・団体(20名以上):
一 般1,000円 高大生 600円 小中学生300円
当日料金: 一 般1,200円 高大生 800円 小中学生 400円
※小学生未満、障がい者手帳などの交付を受けている方と
その介護者1名は無料
6 前売り券 2019年8月1日(木)~ 9月20日(金)
取扱い: ローソンチケット(Lコード:54271)、
チケットぴあ(Pコード:769-875)、セブンチケット、
近鉄電車主要駅、龍谷ミュージアム受付などで販売
問い合わせ先…龍谷ミュージアム
Tel 075-351-2500 Fax 075-351-2577
E-mail muse@ad.ryukoku.ac.jp
HP https://museum.ryukoku.ac.jp