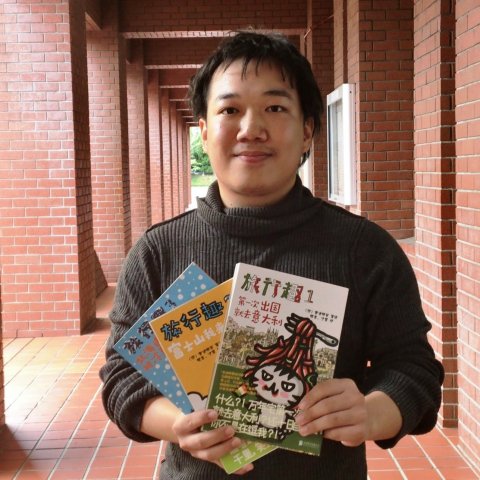「フードビジネスマーケティング論」で講演会を実施
2019年6月28日(金)4限時「フードビジネスマーケティング論」において、株式会社早和果樹園代表取締役社長秋竹 俊伸 様を講師としてお招きし、「有田みかんを活用した地域活性化の取り組み」と題しご講演いただきました。中でも株式会社早和果樹園の6次産業化(生産・加工・販売)の取り組みについて次の3点を中心にお話いただきました。
・甘くて美味しいみかんを栽培する技術に加え、ICT農業システムを取り入れるなど、最先端技術を用いた生産活動
・みかんの皮やフクロなど余すところなく活用するという多様な商品開発の取り組みや、加工品の年間生産体制の構築
・従業員一丸となって日本全国や海外へ商品を売り込む販路開拓の取り組み
講義の終盤においては、企業内部の組織づくりと人材育成の重要性と持続可能なみかん産地のあり方について今後の展望をお話いただきました。
学生のコメント
・「加工することで地域が潤う」というのは初めて聞きいた。その作物の強みに特化した商品等を作ることで価格競争が起こることを防ぎ、適正価格で販売することができ、地域貢献につながることを知って感銘を受けた。
・「農家が集まった会社だから、高く買って高く売らないといけない」という言葉がすごく印象的だった。地域社会でビジネスとして拡大していく姿勢が、すごく共感を持てた。
・失敗してもいいから多くの商品を発売することで、損失が出たとしても、知ってもらうことが重要だと感じた。