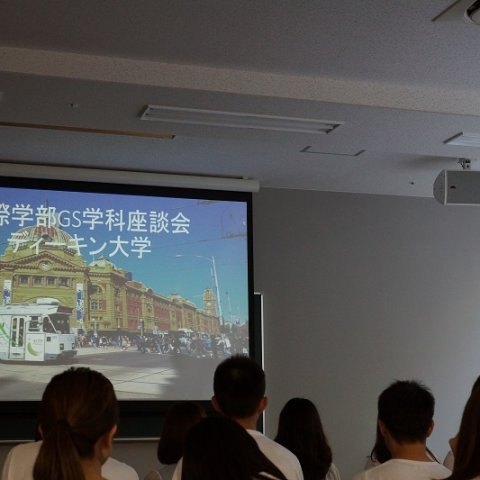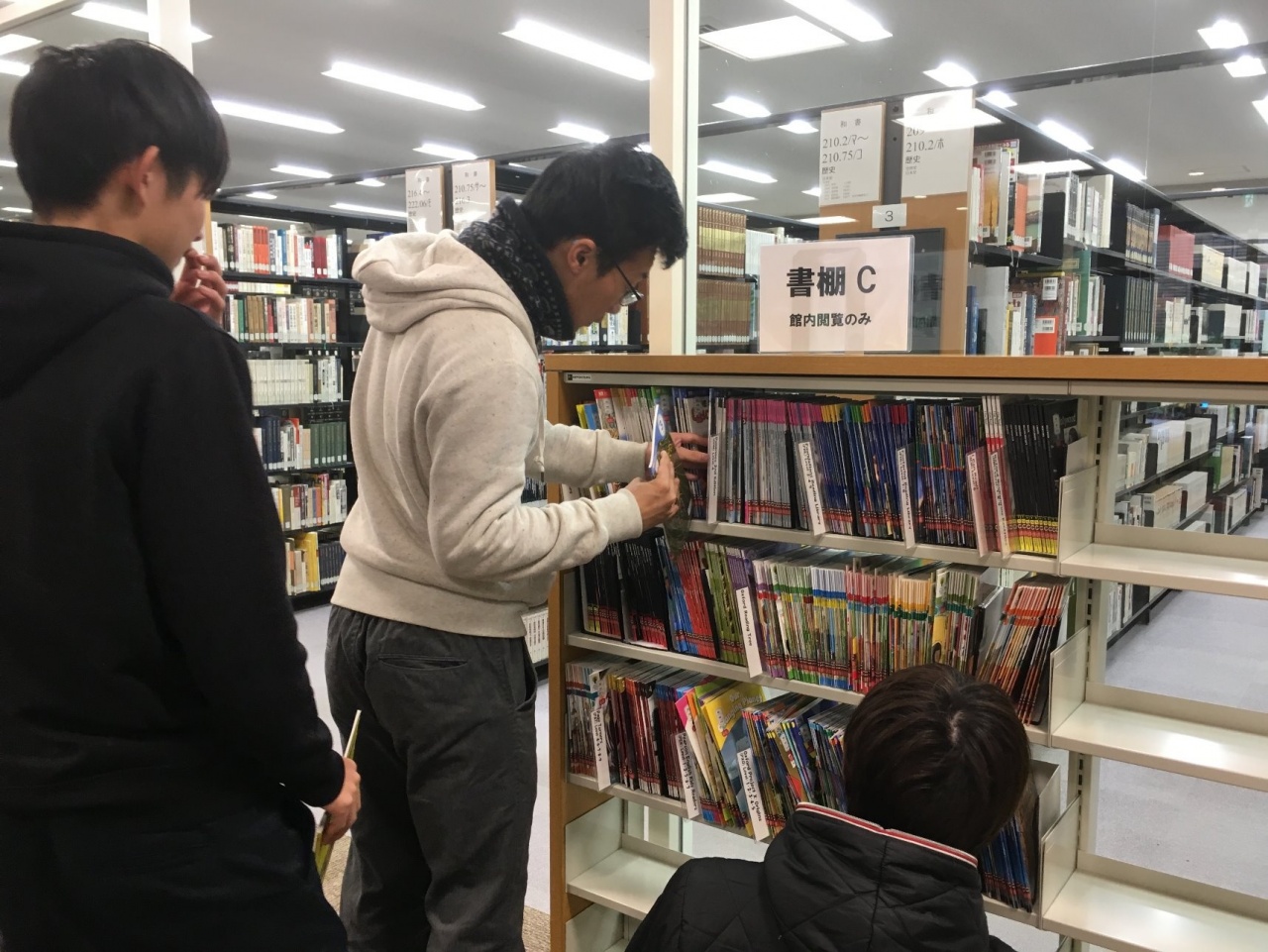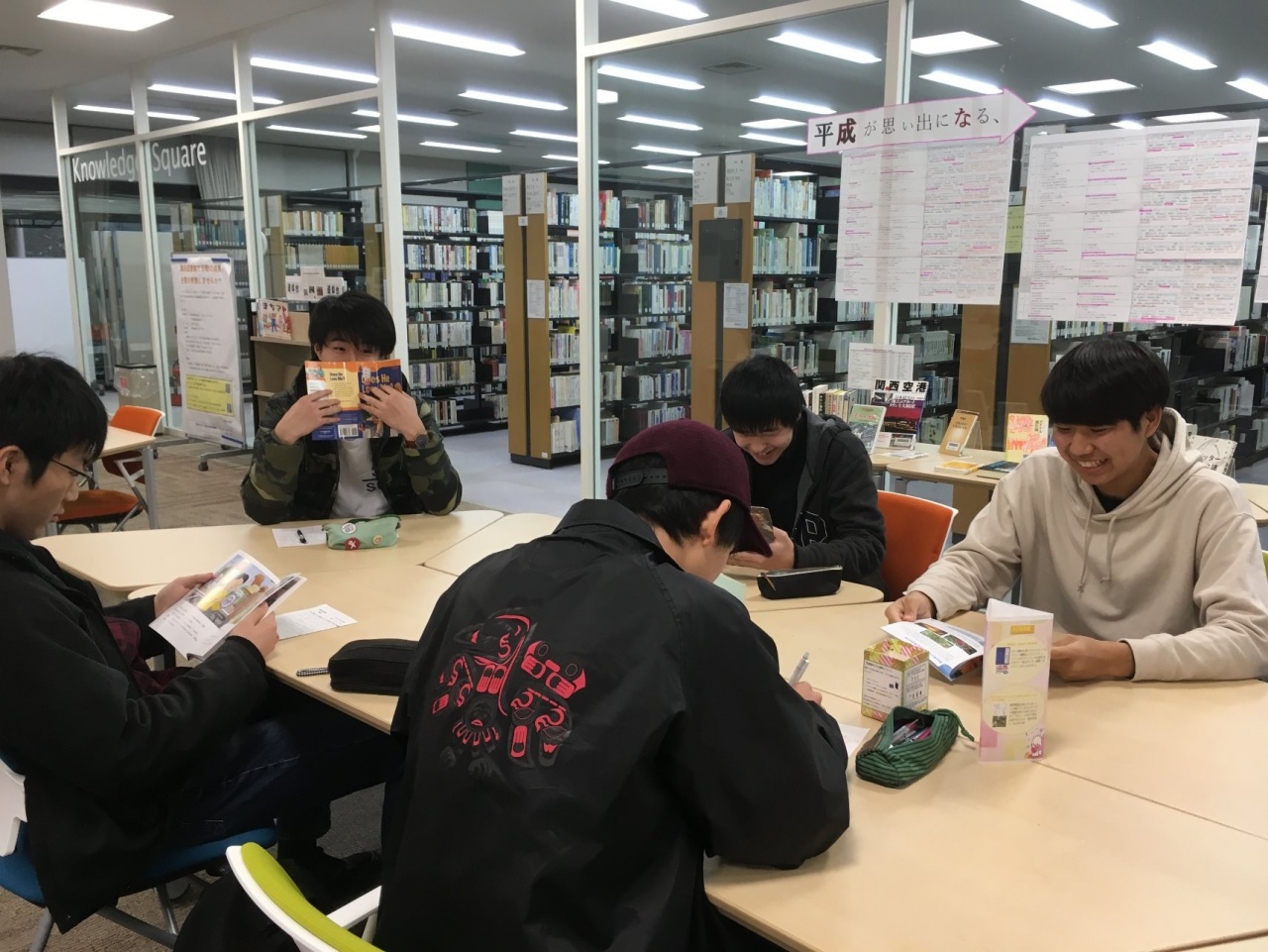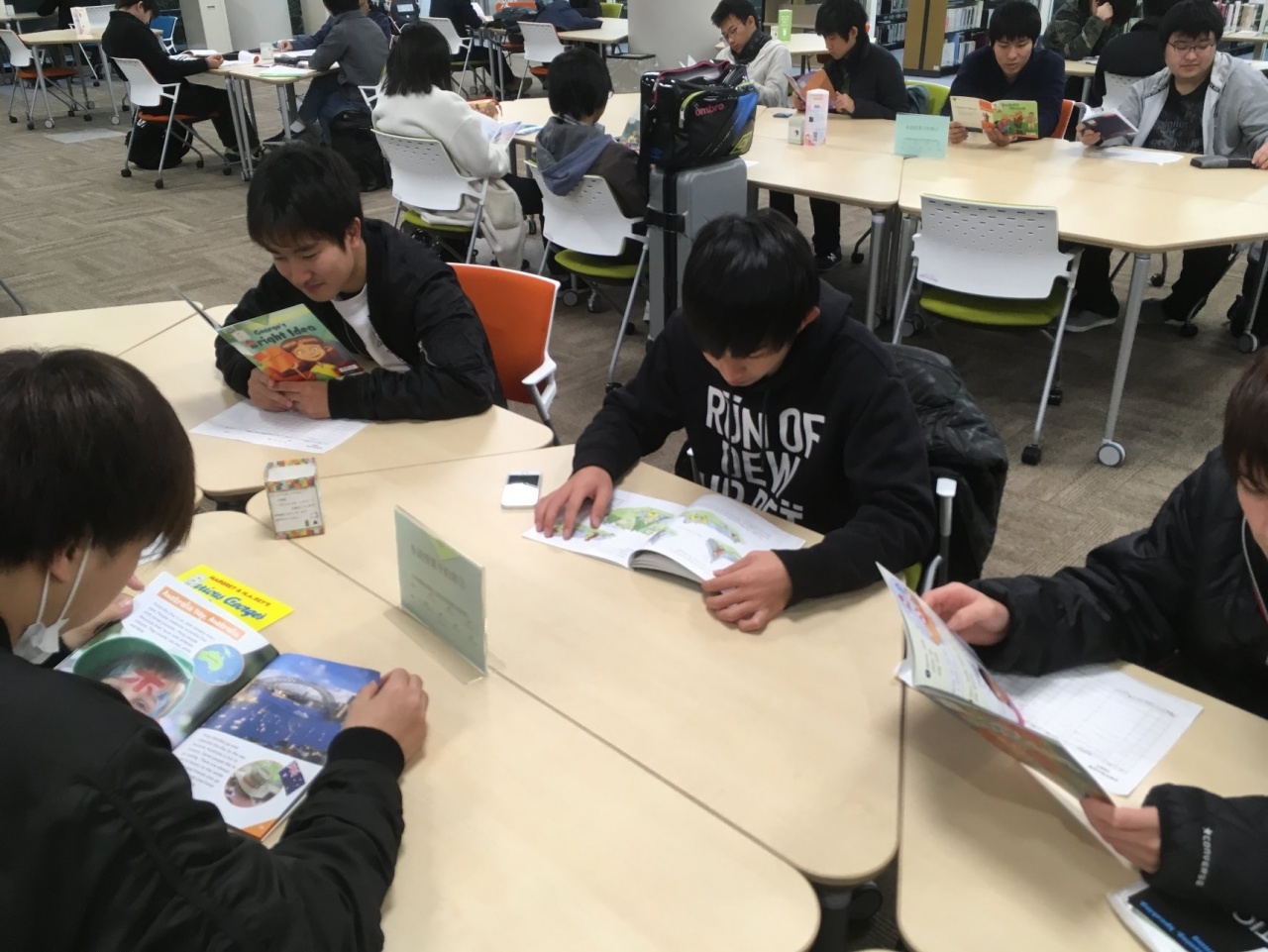「対テロ戦争における『いのち』」をテーマに、ジャーナリスト 安田純平氏の講演会を開催【犯罪学研究センター】
2019年3月3日(日)、龍谷大学 犯罪学研究センターは深草キャンパス紫光館4階法廷教室にて、ジャーナリストの安田 純平氏をお招きし「対テロ戦争における『いのち』~シリア拘束40か月の安田純平さんが、いま、京都で語る~」と題した講演会を開催しました。
犯罪学の研究対象は、殺人や詐欺など個人の法益を侵害する犯罪だけではなく、内乱のような国家の存立を危うくする犯罪、大量虐殺のような人道に対する罪も含みます。今、世界では紛争によって多くの命が奪われています。これらを「犯罪の被害」という視点からとらえ、多くの方と「いのちの大切さ」について考える機会とするため、この講演会を企画しました。
【イベント概要>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-3097.html
安田氏がシリアにおいて2015年から3年4ヵ月にわたり拘束されていたことは、記憶に新しい出来事です。何度も危険な目に遭遇されながらも戦場の最前線で取材し、昨年の帰国後も「自己責任論」などの批判を受けながら、それでもなお真実を伝え続ける理由とは?ジャーナリストとしてのスピリットについて講演していただきました。
当日は定員の100名が聴講。シリアでの拘禁当時の状況や心境など、取材時の写真をスクリーンに映しながらの迫真の内容に、じっくりと聴き入る講演会となりました。
本講演会は、前半の部で安田氏の講演を、後半の部で犯罪学研究センター長の石塚 伸一教授との対談が行われました。
冒頭、司会者による紹介の後に「スーツは落ち着かないんです」と断りを入れながら、Tシャツにダウンジャケット、デニムパンツに足元はスニーカーという出で立ちで登場した安田氏。
講演の序盤では、取材目的に「対テロ戦争」を掲げるにあたり、あえて「テロリスト」という表現は使用していない、と話しました。そこには「テロとは何なのか?」という問いが常にあるとのこと。印象的だったこととして、2004年にイラクで拘束された際、テロリストと呼ばれる人達が普通の村人だったことを述べました。彼らが紛争に加わった経緯とは、米軍が突如、地域を占拠し、拘束・虐待されたり家族を殺されたりしたことから、反米感情が高まったというものです。安田氏は「そもそもイラク戦争がなければ、その地で平穏に暮らし続ける人々だったであろうことは容易に想像できた」と語ります。ここで「テロ」とは何なのか? 話題は核心へ向かいます。
日本の犯罪であれば、被疑者として裁判を受け、有罪判決が下ってはじめて犯罪者と呼ばれますが、テロリストにはそういったプロセスがありません。殺人罪や内乱罪など、既存の法律で表現できる点を無視し、あえて「テロ」という表現で恐ろしいイメージを与え、人々に想像の余地を与えず思考停止に陥れる。安田氏はその点を厳しく指摘しました。
「テロとは主観的な表現であり、定義も曖昧です。それなのに今『テロリスト』という言葉は、他国へ介入しようとする国家権力者だけでなく、メディアにも一般人にも、都合の良い表現になっている。相手をまるでモンスターのような存在に仕立て上げ、テロリストであれば無条件に殺してよい、潜伏している地域は空爆してもよいとする……そんな風潮に危機感を覚えます」。内情も明らかでないまま「外」の社会からテロリストと定義することで、相手の人権すら奪っているのだと警鐘を鳴らしました。
つづいて、取材先に潜入する際の苦労や、2015年に拘束された際の話題に。まず紛争地域で反政府組織の実態を取材するには、その国の政府が定めた法律に従っているだけではたどり着けないこと。いたしかたなく正攻法以外で潜入した結果、不法入国扱いとなってしまい、国外追放の憂き目に遭ったエピソードなどが披露されました。さらに2015年の拘束当時の話では、当初スパイ容疑で捕まったものの、疑いはすぐ晴れたこと。しかし、先の2004年の拘束の件で、相手から何ら要求の出ていない単なるスパイ容疑による拘束だったにも関わらず、「人質」と報道され、まるで日本が身代金を支払ったかのような憶測情報がインターネット上に出回っていたため、金銭との引き替えを要求する人質として扱われてしまったことにも触れました。日本側への生存証明のため、幾度か伝言を書くよう指示されたそうですが、仲介役になって商売しようとしたブローカーがやったもので、日本政府は全く関与していなかったそうです。家族から聞き取った、本人しか答えられない質問を相手に送り、正しい答えが戻ってくれば本人が生きているという証明になるのですが、本人が答えてから妻が内容を確認したのが2年7カ月後で、日本のテレビ局が取材で入手したものでした。人質を本当に捕まえていること、今も生きていることが確かでなければ身代金の支払いはできません。これらのことから、身代金の支払いどころか交渉があったかどうかも疑わしい、と述べました。そのなかに家族への暗号を盛り込む工夫をしたことも、実際のメモの写真とともに紹介されました。自身としては覚悟のうえの取材だったため、日本政府に身代金を払ってもらうつもりは全くなかったそうです。ですが、その考えをどうにか伝えておかないと、もしもの時には残された家族が世間から糾弾されるかもしれない、と考えたそうです。
講演の終盤、石塚教授がマイクを握り「なぜ危険を冒してまで取材をするのですか」と問いかけました。安田氏がジャーナリストとして信念を持ったのは、新聞記者時代だったと言います。戦争に限らず、身の周りで起きることについて、一人の人間という立場から“自分ごと”として探究できる存在でありたいと考えたそうです。また、石塚教授の「報道組織に所属するより、フリーランスの方が動きやすいのですか?」という質問に対しては、「組織に所属していると、つてやバックアップなど有利な面もあります。しかし、私が望む取材の大半はフリーランスにしかできないような題材です」ときっぱり。さらに「紛争地域の報道は成果を発表する場が少なく、利益を出すのが難しいのですが……」とも明かしました。
いったん休憩を挟み、後半の部では安田氏と石塚教授のトークセッションを実施。最後には安田氏の奥さまも登壇され、ジャーナリストとしての信念を貫く安田氏への思いを語りました。
まず、石塚教授が「先ほど生存確認のお話がありましたが、拘束されたとき、身代金を払ってほしい気持ちはありましたか」と切り込むと、安田氏は改めて「ノー」と答えました。「どのような状況下でも日本政府が身代金を払うことはないと思いますが……」と前置きしたうえで、「だからこそ、自分の判断で潜入先を選べる自由があります。その自由には、死ぬことも含まれることは理解しています」と明言。
ここから話題は、世間の一部で上がっていた「自己責任論」に言及することになりました。石塚教授は「安田氏を非難する人が使用する『自己責任』という言葉は、危険な考え方だと思います」と指摘。「作為や過失による行動には責任を取るべきですが、不可抗力な災いに巻き込まれることは『被害』です。安田氏も、誘拐・拘禁という犯罪に巻き込まれた被害者だったんですよね」と語り、“危険な地域へ自ら赴く=拘束された結果は自己責任の範疇”とする論調に異を唱えました。
その言葉に安田氏は「政府の退避勧告に従わなかった点も指摘されるのですが、退避勧告地域は政府が自由に設定できます。言い換えれば、政府にとって不都合な地域を指定することも可能だということ。政府の発表が果たして真実で、正しいのか? 民主主義国家に生きる私たちは、その点も自分たちで判断しなくてはいけないと思っています」と添えました。
また、戦争・紛争に対する報道機関のあり方として、イラク戦争時の米国エンベッド取材(軍の活動に同行するかたちでの取材)を例に挙げ、「エンベッド取材は軍に守られて最前線まで取材できる一方、政府が選別したものしか取材できない。それは記者の仕事とは言えないと思う」と語り、危険を伴ってでも真実を伝えたいという安田氏の想いが会場に強く響きました。
対談の後には、聴講者からの質疑応答の時間が設けられました。「40ヵ月間もの拘束中、心を保っていられた支えはなんでしたか」という質問には「自分の身に起きたことを、なんとしても発信したいという想いでした」と安田氏。そして一番気がかりだったのが、日本にいる家族のことだったと語りました。
ここで石塚教授の誘導で、講演会に同行されていた安田氏の奥さまがステージ上へ。ジャーナリストとしての信念を貫く安田氏へのエールと、安田氏が拘束されていた間は精神的に苦しかったこと、それでも帰国を信じ続けたことなどを話され、安田氏を支持する人々の祈りがあったからこそ、解放という奇跡的な結果に繋がったと感謝の言葉を述べられました。
安田氏いわく、人質を拘束した組織が何らかの交渉を目論んでいた場合、そのやりとりは必ず秘密裏に進められるそうです。「日本のマスコミはすぐに大々的に報道する傾向があるが、公にすることで人質が危険にさらされる恐れがある。国内で人質事件があった場合には、人命に配慮して報道を控えた、ということをするのに、海外での人質事件では争うようにして不確かなものまで報道してしまう。報道されることによって解放に近づくということは一切ない。家族へのバッシングが起きるだけで、報道によるメリットは何もない」とのこと。帰国してから事実とまったく異なる報道が多数あったことに驚き、またその報道から起こった世論によって家族に大きな負担をかけた、と口惜しさを滲ませていました。この話を受けて、石塚教授は「まさに、犯罪被害者の家族も同じことが言えます」と話題を繋ぎ、大きな事件ともなれば、心が傷つき疲弊しているところに報道陣が押しかけ、憤りや悲しみのコメントを要求する報道のあり方に疑問を呈しました。
最後に石塚教授があいさつに立ち「安田氏が2018年10月に解放されて、まだ4ヵ月ほどです。回復途中のところ貴重なお話をうかがえたこと、参加者の皆さんとこの場を共有できたことに心から感謝申し上げます」と締めくくりました。
犯罪学研究センターでは、今後も「生命(いのち)」の大切さについて、さまざまな視点からみなさんと一緒に考える機会を設けていきたいと考えています。