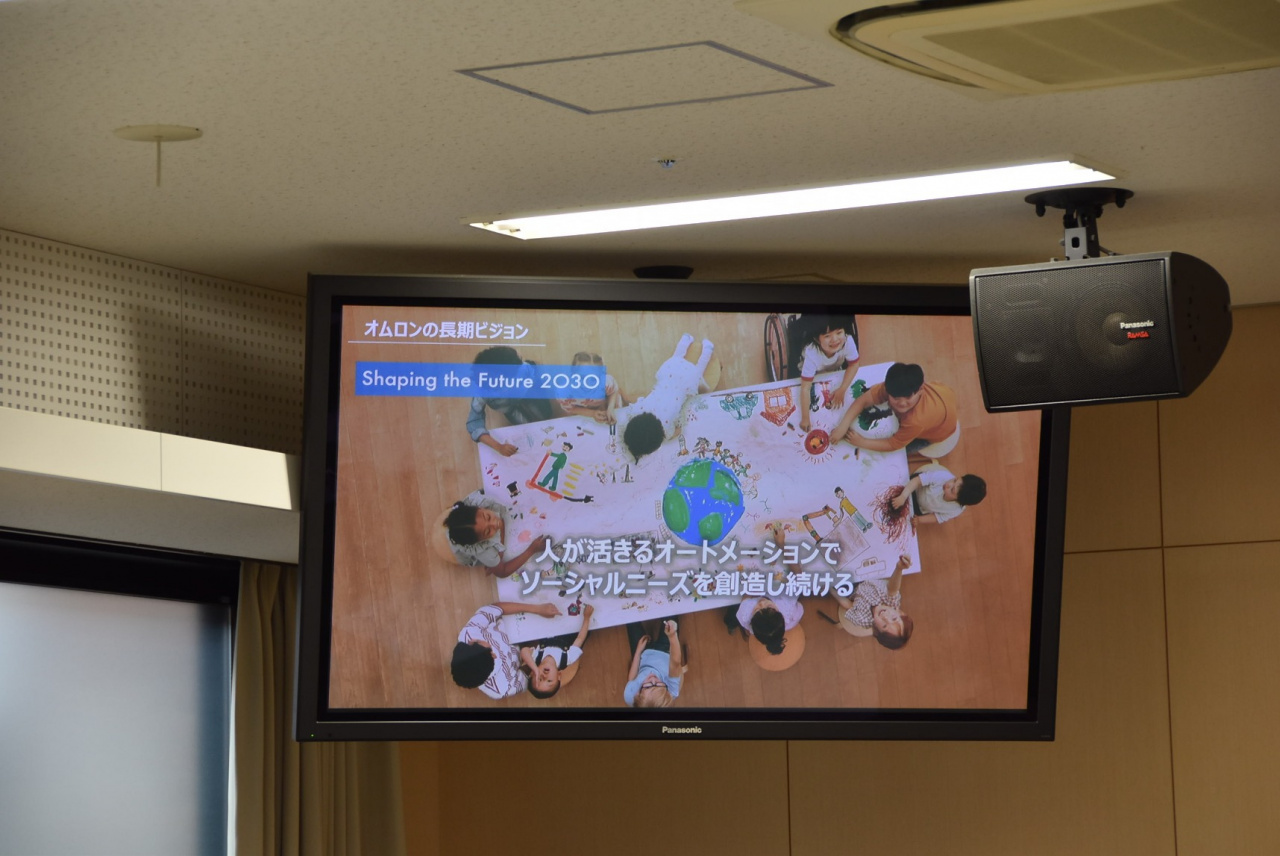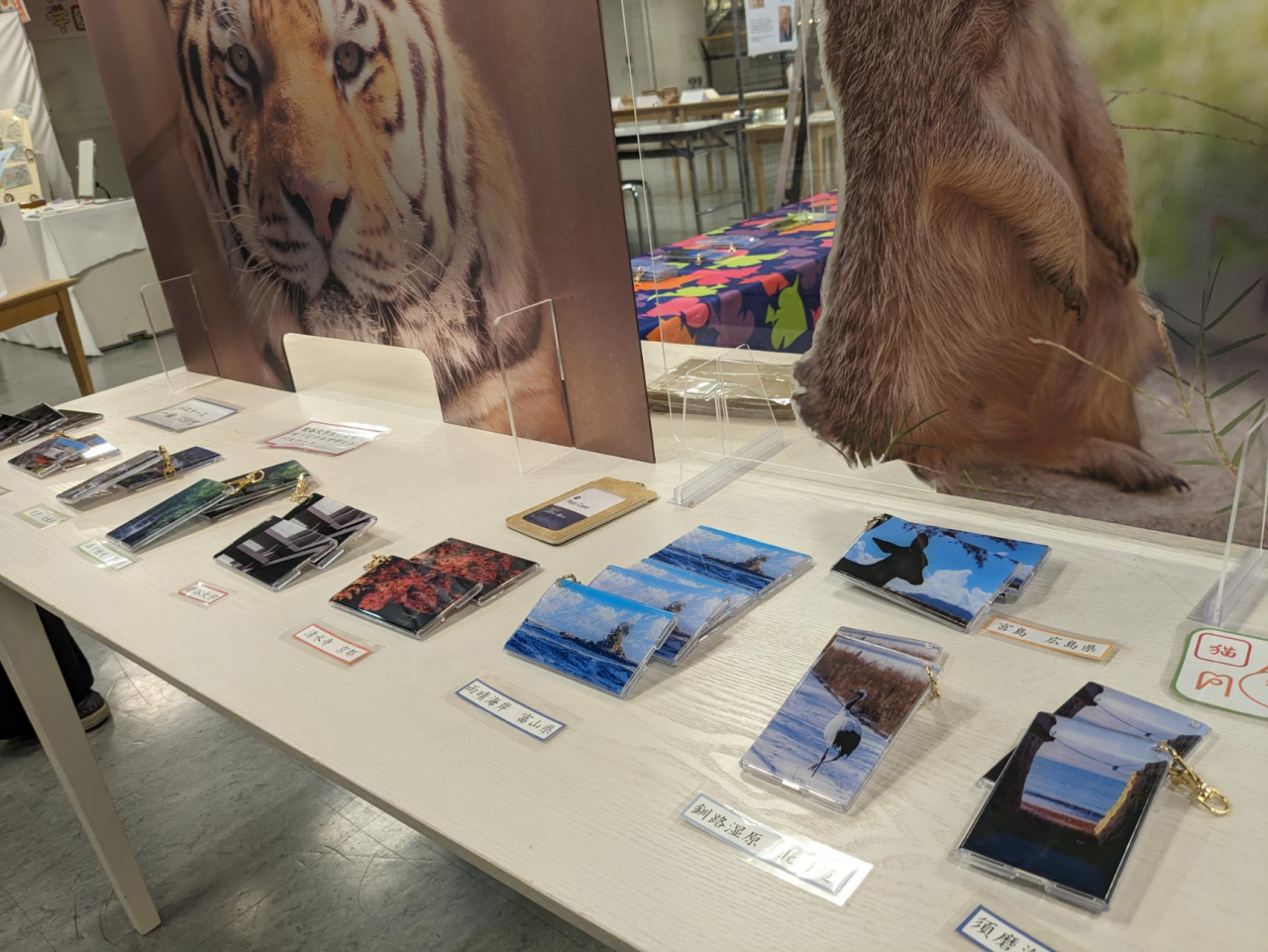オムロン京都太陽 代表取締役社長 三輪建夫氏、CSR課荒井裕晃氏が経営学部特別講義「我が社の経営と京都」に登壇【経営学部】
京都企業の経営者をお招きし、ご講演いただく経営学部の特別講義「我が社の経営と京都」では、経営者の経営哲学が経営戦略としてどのように具体化されているのか、あわせて京都という資源がどのように経営に生かされているのかを学生に把握してもらうことを到達目標にしています。
第4回(11月7日)は、オムロン京都太陽株式会社代表取締役社長 三輪建夫氏、CSR課荒井裕晃氏のお二人をお招きしてご講演いただきました。三輪氏は、同社の企業理念経営や設立された背景、そして従業員の約60%が障がい者である同社の社会的責任と収益確保の経営システムを詳しく説明してくださいました。続いて、荒井氏は実際の工場の様子をご紹介くださり、障がい者ができることとできないことを把握して、できないことをできないで終わらせずに、工程改善や機械の導入等、さまざまな方法でできるようにする、健常者が1人でできる仕事を障がい者が作業できるよう細分化し、2人で分担作業しても効率性を落とさないということをデータなどで示してくださいました。
講義後の質疑応答では複数の学生から使われているツールのことや法定雇用率との関係などの質問が挙げられましたが、それらに対して詳しくお答えいただきました。授業後に提出する学生のコメントでは、車椅子に乗ったスーツの社会人の方が説明されているのを見て驚いた自分と同時に、誰もが働ける社会はまだ実現されていないことに気づかされたいう感想もありました。
2023年度の特別講義「我が社の経営と京都」では、10月17日から6回にわたって6人の経営者の方に登壇していただく予定です。
ご講演いただきましたオムロン京都太陽株式会社につきましては以下のホームページのリンクから確認できます。
https://www.kyoto-taiyo.omron.co.jp/