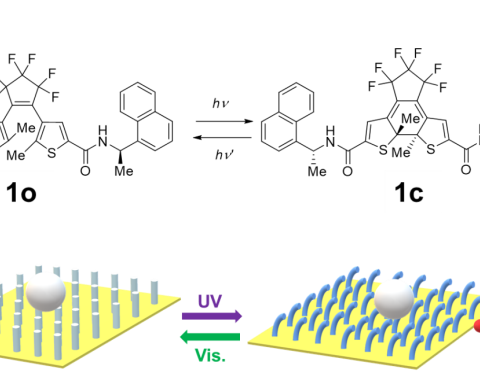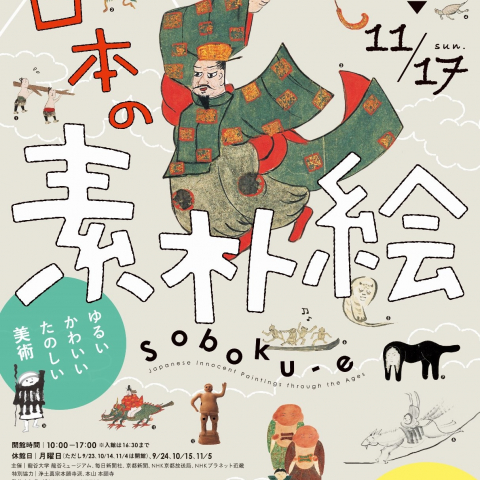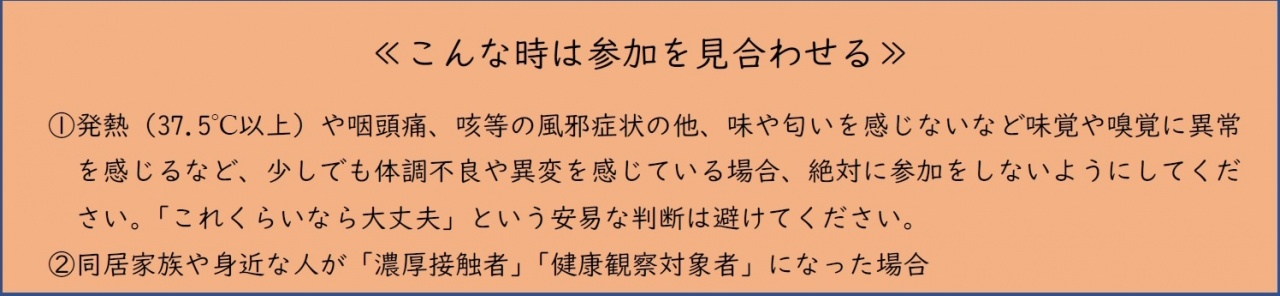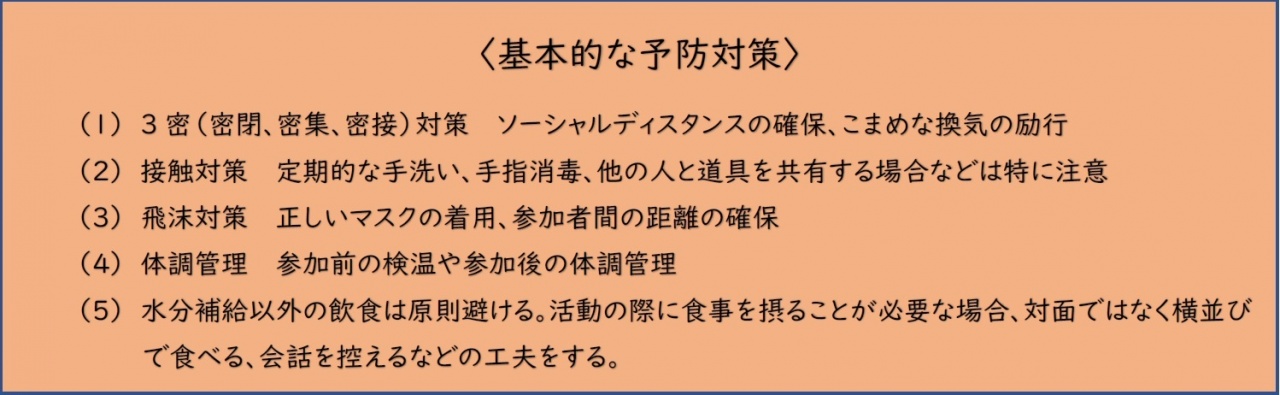【グローバルサポーター企画】オンライン「留学報告会」及び「留学経験者座談会」開催のお知らせ
グローバルサポーター企画の「留学報告会」及び「留学経験者座談会」をオンラインで開催します。
留学希望学生、すでに留学が決まっている学生、留学に興味関心がある学生等々、ぜひご参加ください!
[留学報告会]
留学経験者が、留学関連の生々しい情報(留学前の準備や資金調達、現地で必要な言語レベル、就職活動への影響、留年の可能性等)を学生目線で提供します。
<開催日時>
東アジア留学編(韓国/台湾)
10月5日(月)12:30〜13:30
北米&豪州編(アメリカ/カナダ/オーストラリア)
10月7日(水)12:30〜13:30
ヨーロッパ編(ドイツ/フランス/スロヴァキア)
10月23日(金)12:30〜13:30
[留学経験者座談会]
留学経験者、外国人留学生が、写真等を活用しながら、留学経験(現地や日本での思い出や日本(出身国)では絶対に経験できないエピソード、それらを通して現地(日本)で学んだこと)を語ります。
<開催日時>
東アジア留学編(韓国/台湾)
10月12日(月)12:30〜13:30
北米&豪州編(アメリカ/カナダ/オーストラリア)
10月14日(水)12:30〜13:30
ヨーロッパ編(ドイツ/フランス/スロヴァキア)
10月30日(金)12:30〜13:30
参加希望の方は、Instagramよりダイレクトメッセージ(DM)でお申込みください。
[問い合わせ先]
グローバルサポーター代表メールアドレス
E-mail: glosup777@gmail.com