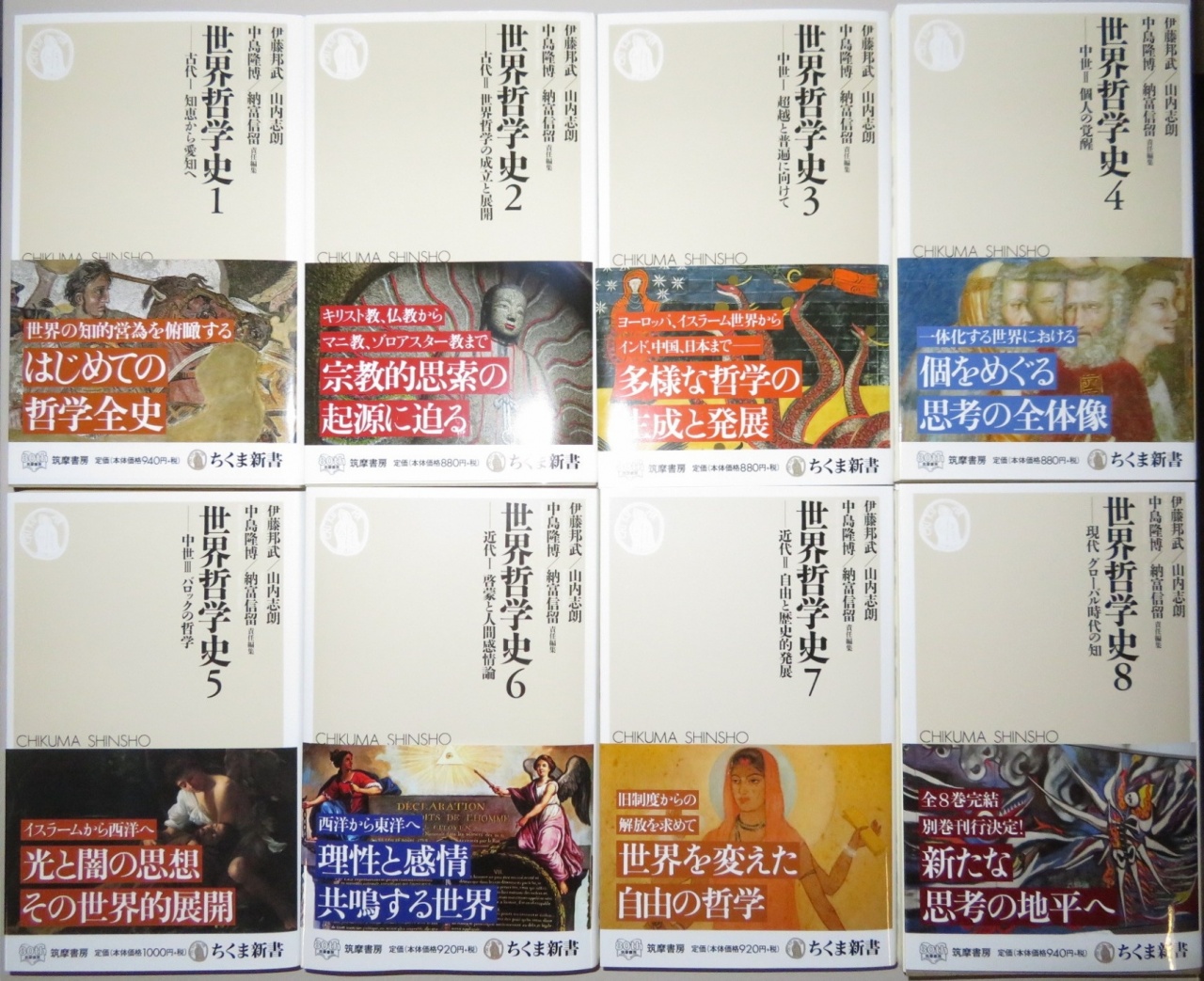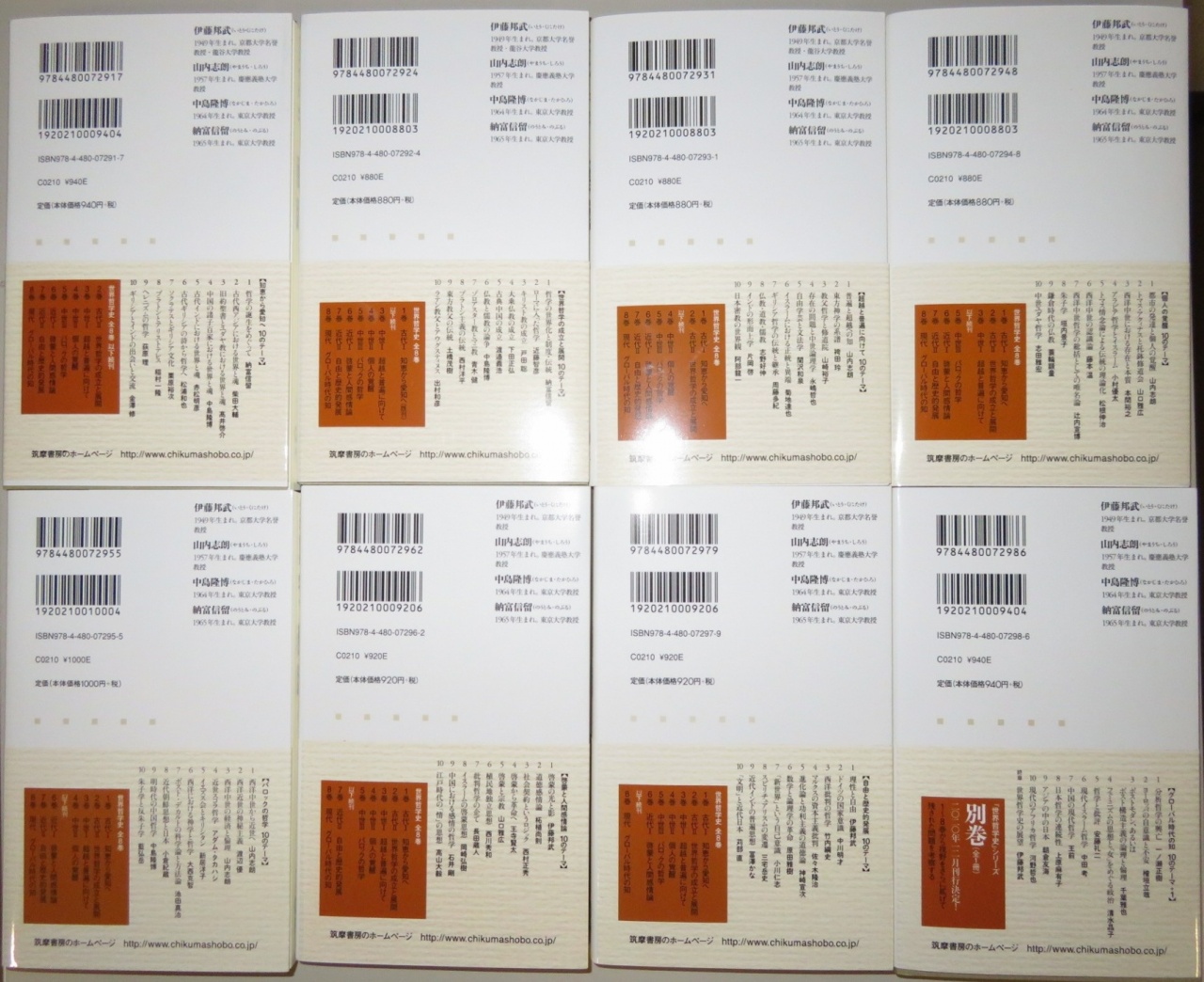1.被确诊感染新型冠状病毒时
新型冠状病毒传染病(COVID-19),是学校保健安全法指定的「第一种传染病」。被确诊感染新型冠状病毒(COVID-19)时,为防止传染扩大,请按以下指示行动。
我校将从保护人权的立场出发保护受感染者的个人隐私。防御措施是为了保护学生和相关人员的生命和健康,希望大家都能同心协力阻止感染扩散。
致各位同学
(1)在得到主治医生的痊愈诊断之前,不要到校,请在医疗机构等地方进行治疗。
(2)使用电话或电子邮件,向所属学部教务科报告以下事项。
※8月8日(周六)~18日(周二)为教务科放假期间,请使用电子邮件联系。
① 学籍号码・姓名
② 确诊病名
③ 症状出现日期
④ 目前病情
⑤ PCR检查日期以及检查结果日期
⑥ 保健所的指示内容(在家待命、在酒店待命、住院、期间等)
⑦ 感染途径
⑧ 家人的感染状况
⑨ 出现症状前2天内的行动轨迹(是否出入过大学)
⑩ 最后一次到校的日期
⑪ 是否接触过大学相关人员(有接触过的,请告知学部、姓名)
⑫ 是否有出入境经历(2020.1月之后)(地区、期间)
⑬ 是否有基础疾病
⑭ 联系方式・电话号码
致各位教职员工
(1)在得到主治医生的痊愈诊断之前,不要到校上班,请在医疗机构等地方进行治疗。
(2)使用电话或电子邮件向所属上司报告以下事项。
① 所属部门・姓名
② 确诊病名
③ 症状出现日期
④ 目前病情
⑤ PCR检查日期以及检查结果日期
⑥ 保健所的指示内容(在家待命、在酒店待命、住院、期间等)
⑦ 感染途径
⑧ 家人的感染状况
⑨ 出现症状前2天内的行动轨迹(是否出入过大学)
⑩ 最后一次到校的日期
⑪ 是否接触过大学相关人员(有接触过的,请告知学部、姓名)
⑫ 是否有出入境经历(2020.1月之后)(地区、期间)
⑬ 是否有基础疾病
⑭ 联系方式・电话号码
2. 被确认为密切接触者以及与感染者・密切接触者有接触时
收到保健所通知,被确认为密切接触者或者家人出现感染者・密切接触者时,请遵从以下指示。
致各位学生
(1)在收到保健所解除待命指示前不要到学校。
(2)使用电话或电子邮件向所属学部教务科报告以下事项。
※8月8日(周六)~18日(周二)教务科放假期间,请使用电子邮件联系
① 学籍号码・姓名
② 与感染者・密切接触者的关系
③ 在家待命期间(保健所的指示内容)
④ 目前的身体状况
⑤ 接触的日期
⑥ 接触以后的行动轨迹
⑦ 联系方式・电话号码
(3)收到保健所通知后,请尽快联系所属学部教务科。
(4)待命期间结束后,向教务科汇报其经过。
致各位教职员工
(1)在收到保健所解除待命指示前不要到校上班。
(2)使用电话或电子邮件向所属上司报告以下事项。
① 所属部门・姓名
② 与感染者・密切接触者的关系
③ 在家待命期间(保健所的指示内容)
④ 目前的身体状况
⑤ 接触的日期
⑥ 接触以后的行动
⑦ 联系方式・电话号码
(3)收到保健所通知后,请尽快联系所属上司。
(4)待命期间结束后,向所属上司汇报其经过。