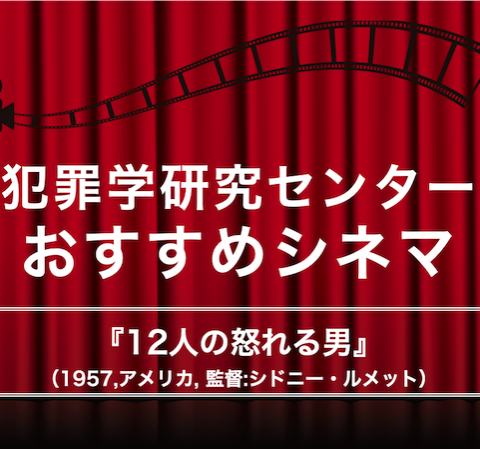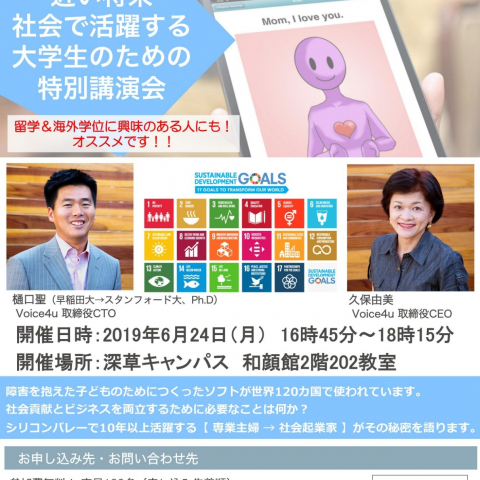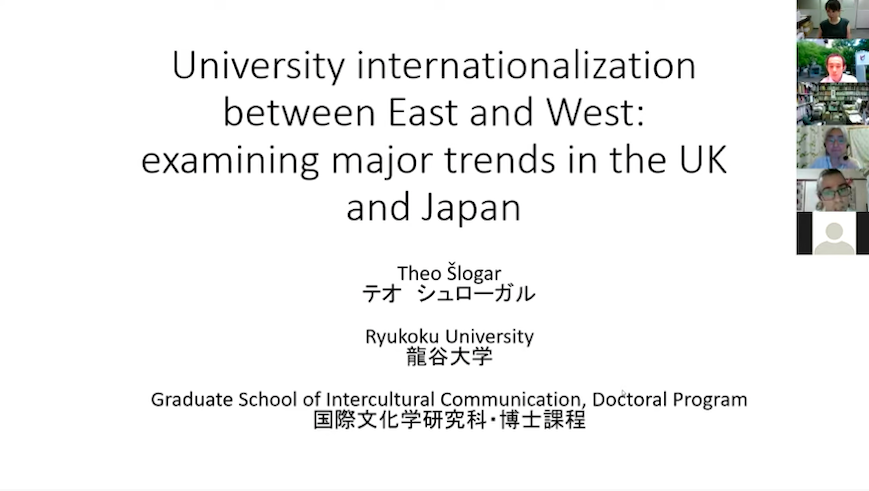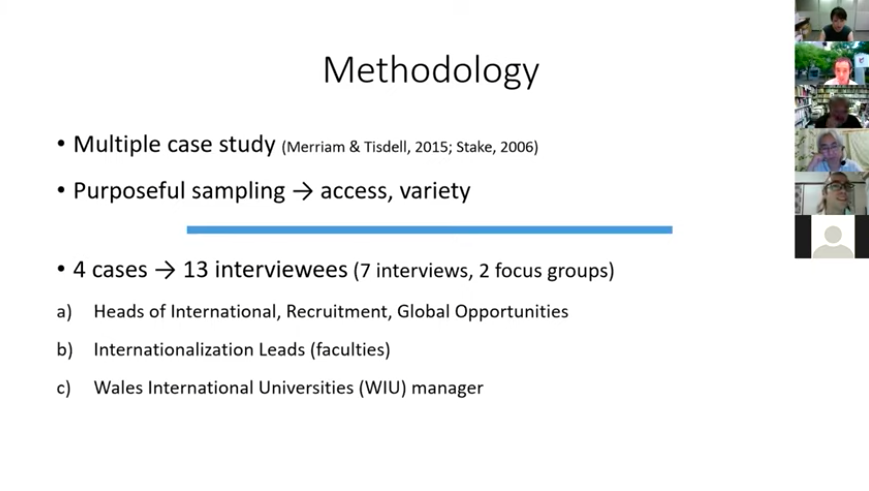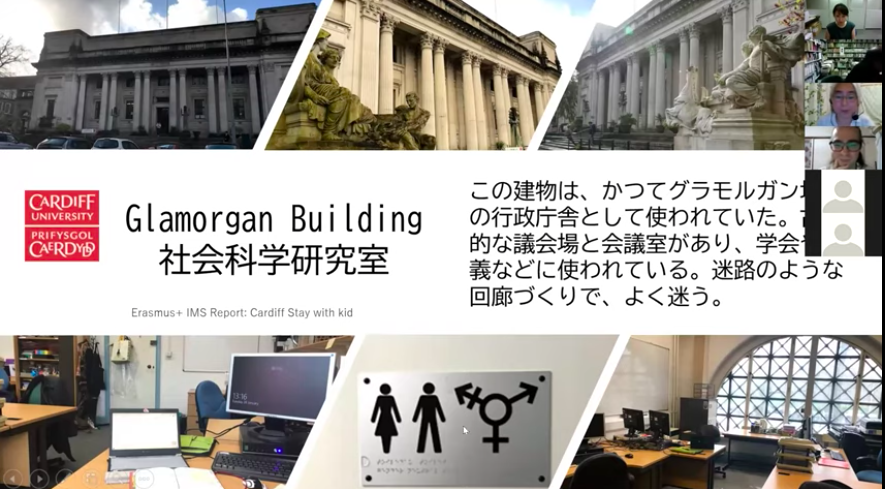キャンベル共同計画ライブラリー(C2ライブラリー)を更新【犯罪学研究センター】
龍谷大学 犯罪学研究センター(Criminology Research Center)では、犯罪をめぐる多様な〈知〉の融合と体系化を目的とし、現在14のユニットでの研究活動が行われています。
その一つである「政策評価」ユニット*1では、浜井 浩一 ユニット長(本学法学部教授)のもと、犯罪学(犯罪防止)における科学的エビデンスの構築と共有を目的として、2000年に国際研究プロジェクトとして始まったキャンベル共同計画(Campbell Collaboration: C2)*2に協力しつつ、政策評価研究が行われています。
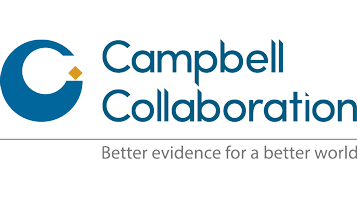
https://campbellcollaboration.org
今回、キャンベル計画 日本語版WEBサイトにて「抄録(Plain language summary)」を中心として、計22ファイル(刑事司法3・社会福祉2・国際開発17)をライブラリへ追加、更新しました。
■キャンベル計画 日本語版 TOP
https://crimrc.ryukoku.ac.jp/campbell/index.html
■キャンベル共同計画ライブラリ TOP
https://crimrc.ryukoku.ac.jp/campbell/library/index.html
今回、新たに加わった「抄録」は、キャンベル共同計画の数々の成果報告を広く一般に周知するために簡潔にまとめられた英語版のパンフレット(Plain language summary)を日本語に訳したものです。この「抄録」を通して、各調査研究が何を目的とし、どのような結果が得られたのかを端的に理解することができます。
さらに、この「抄録」を端緒として「レビュー」や「プロトコル」などの調査報告書を読み進めていくことで、エビデンスについて考える機会や成果を活用する機会が増える一助となることを期待しています。
▼「刑事司法」分野
https://crimrc.ryukoku.ac.jp/campbell/library/crimejustice.html
・【>>PDF Link】バイスタンダープログラムは居合わせた人の介入を増加させるが、性的暴行の加害には効果がない
・【>>PDF Link】低・中所得国におけるギャングのメンバーシップを予測する要因がどのようなものかを示すエビデンスがあるが、さらなる調査が必要である
・【>>PDF Link】低リスクの若者に対する警察主導のダイバージョンは、若者が司法制度と将来的に関わることを減らす
▼「社会福祉」分野
https://crimrc.ryukoku.ac.jp/campbell/library/social.html
・【>>PDF Link】ホームレス状態を減らし、居住安定性を改善する介入は効果的である
・【>>PDF Link】失業手当の最長期間を短縮することは、失業者の就職率向上に有益である
▼「国際開発」分野
https://crimrc.ryukoku.ac.jp/campbell/library/international.html
・【>>PDF Link】分散型森林管理プログラムは森林伐採率を減少させうる。しかし、研究成果が未だ乏しいため、評価のためのエビデンスとして扱うには限界がある
・【>>PDF Link】環境サービスへの支払いは、森林破壊にわずかな影響しか与えない
・【>>PDF Link】低中所得国における障がい者とその介護者に対する地域に根ざしたリハビリテーションによる正の効果
・【>>PDF Link】トレーニングと革新及びテクノロジーの介入はアフリカの小規模農家の暮らしを向上させることができるが、厳密な研究はほとんどない
・【>>PDF Link】無料の蚊帳の所有者は増加し、教育はその利用者を増加させられる
・【>>PDF Link】ESHG(経済的自助グループ)は女性に力を与える
・【>>PDF Link】中小企業に対するビジネス支援サービスは企業業績を改善するように思われる
・【>>PDF Link】路上生活の子供たちが社会復帰するための介入の有効性に関するエビデンスの欠如
・【>>PDF Link】集団駆虫プログラムは、大部分の福祉的成果に対してほとんどまたはまったく効果がない
・【>>PDF Link】コミュニティ監視介入は汚職を減少させることができ、サービスを向上させる可能性がある
・【>>PDF Link】学校が決定権を持つことは、教育効果が高い。しかし低所得国では効果が低くなる
・【>>PDF Link】認証制度は農家の世帯収入や労働者の賃金を改善しないように思われる
・【>>PDF Link】地域密着型アプローチは、衛生習慣の変化を促すのに最も効果的だが、しかし、持続可能性が課題である
・【>>PDF Link】契約農業は、富裕層の農家の収入を向上させる
・【>>PDF Link】現金による人道支援アプローチは、食糧安全保障の安全性を高めることができ、食糧の現物支給よりも費用対効果が高い
・【>>PDF Link】職業訓練および実務教育は、労働市場において女性に利益をもたらすが、ほとんどのプログラムの効果は少ししかない
・【>>PDF Link】農業の投入補助金は、投入財使用や収穫高および農場収入を増加させる
【補注】:
*1犯罪学研究センター「政策評価」ユニット:
https://crimrc.ryukoku.ac.jp/org/science.html
*2 「キャンベル共同計画(Campbell Collabolation: C2)/英語サイト
社会、行動、教育の分野における介入の効果に関して、人々が正しい情報に基づいた判断を行うための援助することを目的する国際的な非営利団体です。
https://campbellcollaboration.org/