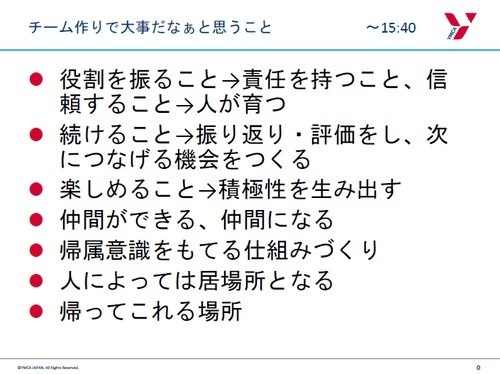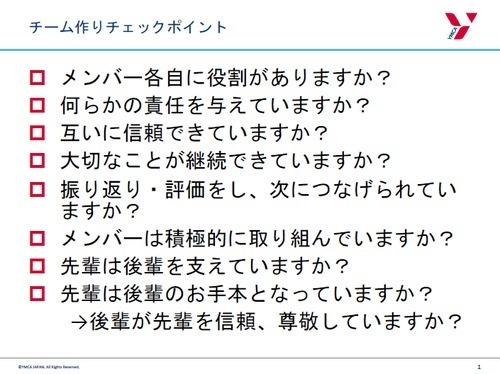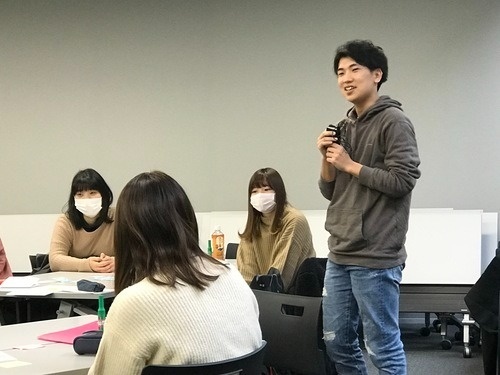~失われた食材 「姉川クラゲ」をよみがえらせたい~「姉川クラゲ」を練り込んだコシの強い蕎麦を開発 2/18瀬田キャンパスで試食会を実施
【本件のポイント】
・農学部4学科の有志がそれぞれの視点でおこなった「姉川クラゲ」に関する研究報告をあわせて実施
・姉川流域で食べられていた「姉川クラゲ」を練り込んだ蕎麦の試食会
・そば粉に姉川クラゲを加えるとそばのコシが強くなり、美味しいそばができることが判明
龍谷大学農学部(滋賀県大津市)は、2018年から4学科を横断して「『姉川クラゲ』配合食品の商品化に向けての取り組み」という研究プロジェクトを始動させました。
「姉川クラゲ(イシクラゲ)」とは、ネンジュモ科に属する陸棲ラン藻類の一種で、湿った地面に自生するワカメのような生物です。姉川流域(滋賀県)で過去に食用にされた記録が残るため「姉川クラゲ」と呼ばれていたこともあります。しかし、現在は地元の方の多くは食べておらず、消えつつある食文化と言えます。
一方、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」は、植物界のクマムシと言われるように過酷な環境状況で生き延びることができ、また、多くの生理活性物質を有しています。そのため地域資源として再活用できないかと考えたことが、配合食品の開発を目指した本プロジェクト立ち上げのきっかけです。さらに、農学部では4学科の1、2年生が学科の垣根を越えて実習を行う「食の循環実習」が開講されおり、それを研究レベルでも拡張し、学部教育につなげたいという意図もあります。
この度、食品栄養学科朝見准教授による研究によって、「姉川クラゲ」の特性を活かし、コシの強い蕎麦の開発に成功しました。試食会当日は、「姉川くらげそば」の解説や試食、これまでのイシクラゲに関する調査・研究について、遺伝子解析、栽培実験、食味検査、蕎麦の特性、栄養分析、食文化・歴史など文理を融合した多角的な視点から報告します。
※一般の方の参加も歓迎します。
1.日時:2020年2月18日(火)11:00~(1時間程度)
2.場所:龍谷大学瀬田キャンパス 9号館1階オープンキッチン
3.内容:「姉川くらげそば」の試食会およびその研究報告
4.説明者:
農学部植物生命科学科 教授 古本 強
農学部資源生物科学科 講師 玉井 鉄宗
農学部食品栄養学科 准教授 朝見 祐也
農学部食料農業システム学科 講師 坂梨 健太
農学部学生有志
問い合わせ先 : 学長室(広報) 橋本 Tel 075-645-7882