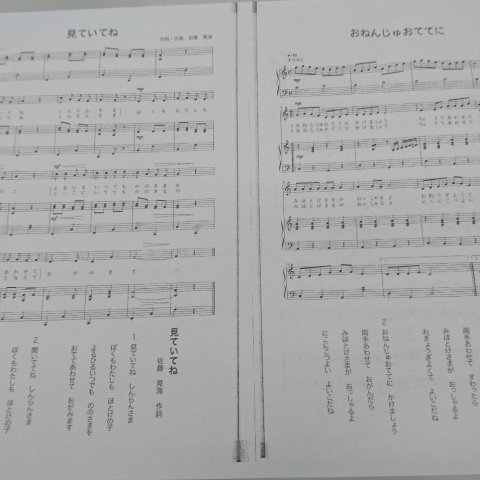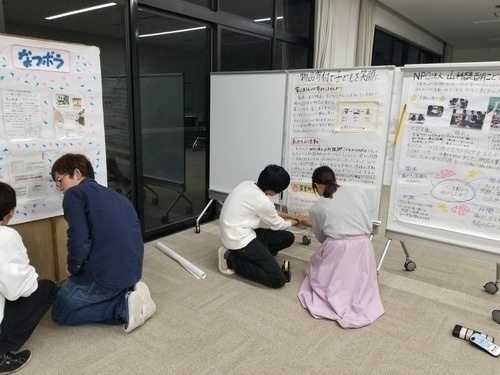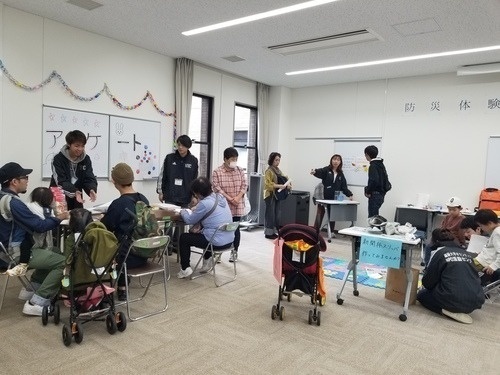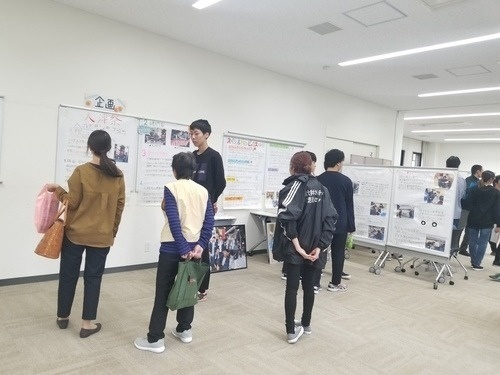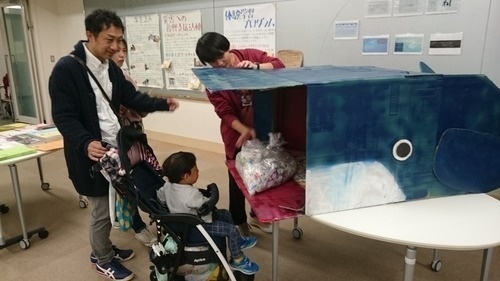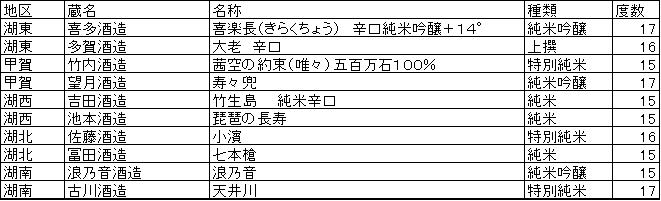経済学部長に 小峯 敦 教授を選出<任期>2020年4月より2年間
佐々木 淳 経済学部長の任期満了(2020年3月31日)に伴う選挙会を11月6日に実施した結果、次期経済学部長に小峯 敦(こみね あつし)教授を選出しましたのでお知らせいたします。
【龍谷大学経済学部長】
任 期 : 2020年4月1日~2022年3月31日まで
氏 名 : 小峯 敦 (こみね あつし)教授
生 年 月 日 : 1965年2月11日 (54歳)
【専門分野】
経済学史、経済思想史、福祉国家論
【最終学歴】
1994年3月 一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程 単位取得満期退学
【学位】
博士(経済学)(一橋大学) (2011年2月)
【職歴】
1994年 4月 一橋大学経済学部助手
1995年 4月 新潟産業大学経済学部専任講師
1999年 4月 新潟産業大学経済学部助教授
2005年 4月 龍谷大学経済学部助教授
2007年 4月 龍谷大学経済学部准教授
2008年 4月 龍谷大学経済学部教授(現在に至る)
【研究業績・著書】
・『ベヴァリッジの経済思想─ケインズたちとの交流』(昭和堂 2007年)
・Keynes and his Contemporaries: Tradition and Enterprise in the Cambridge School of Economics(Routledge, 2014)
・“William Henry Beveridge (1879-1963)”, in R. A. Cord (ed.) The Palgrave Companion to LSE Economics(Palgrave Macmillan, 2018)
・『戦争と平和の経済思想』(編著、晃洋書房 2020年刊行予定)
【所属学会】
経済学史学会(2017/18 第34代・代表幹事)、社会思想史学会、日本イギリス哲学会など
問い合わせ先 : 経済学部教務課 内田・丸山 Tel 075-645-2496