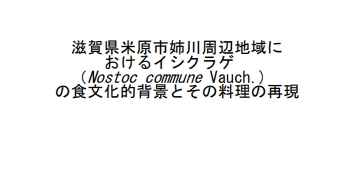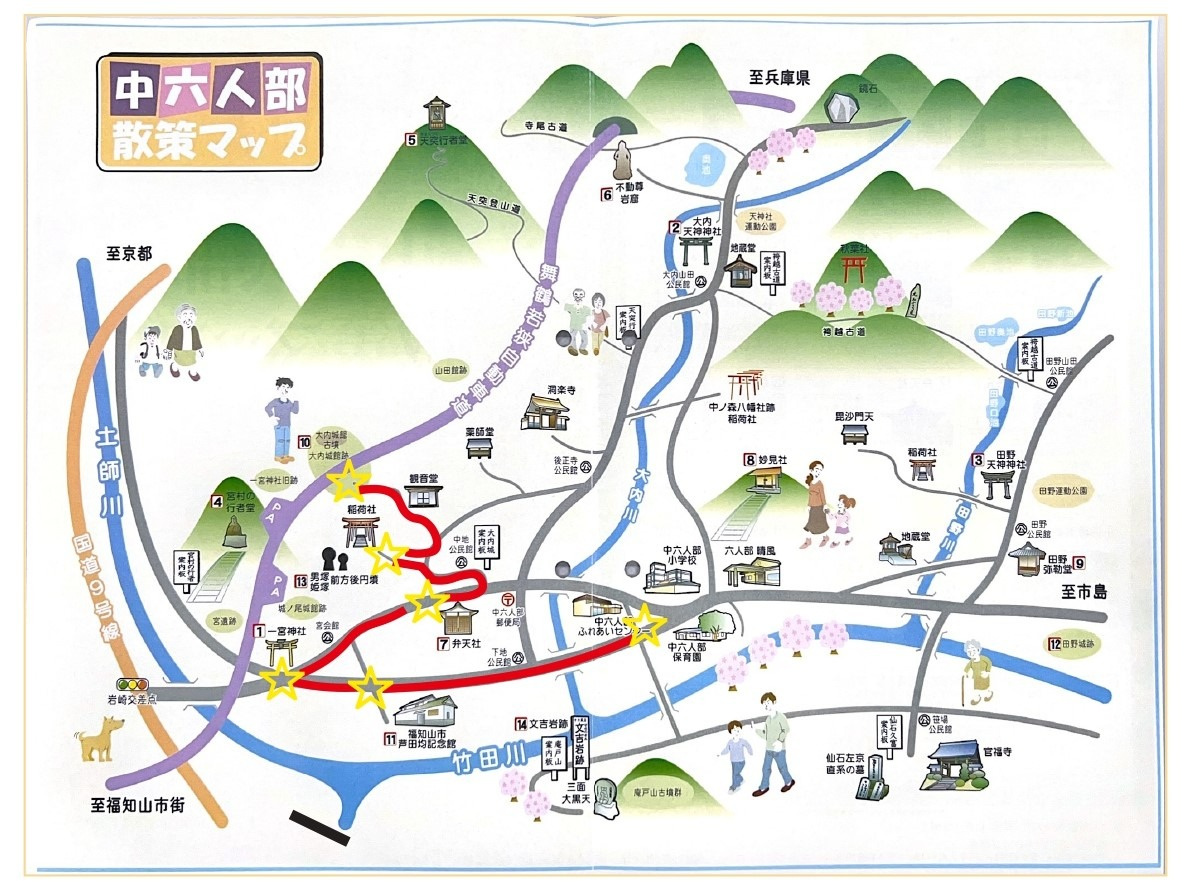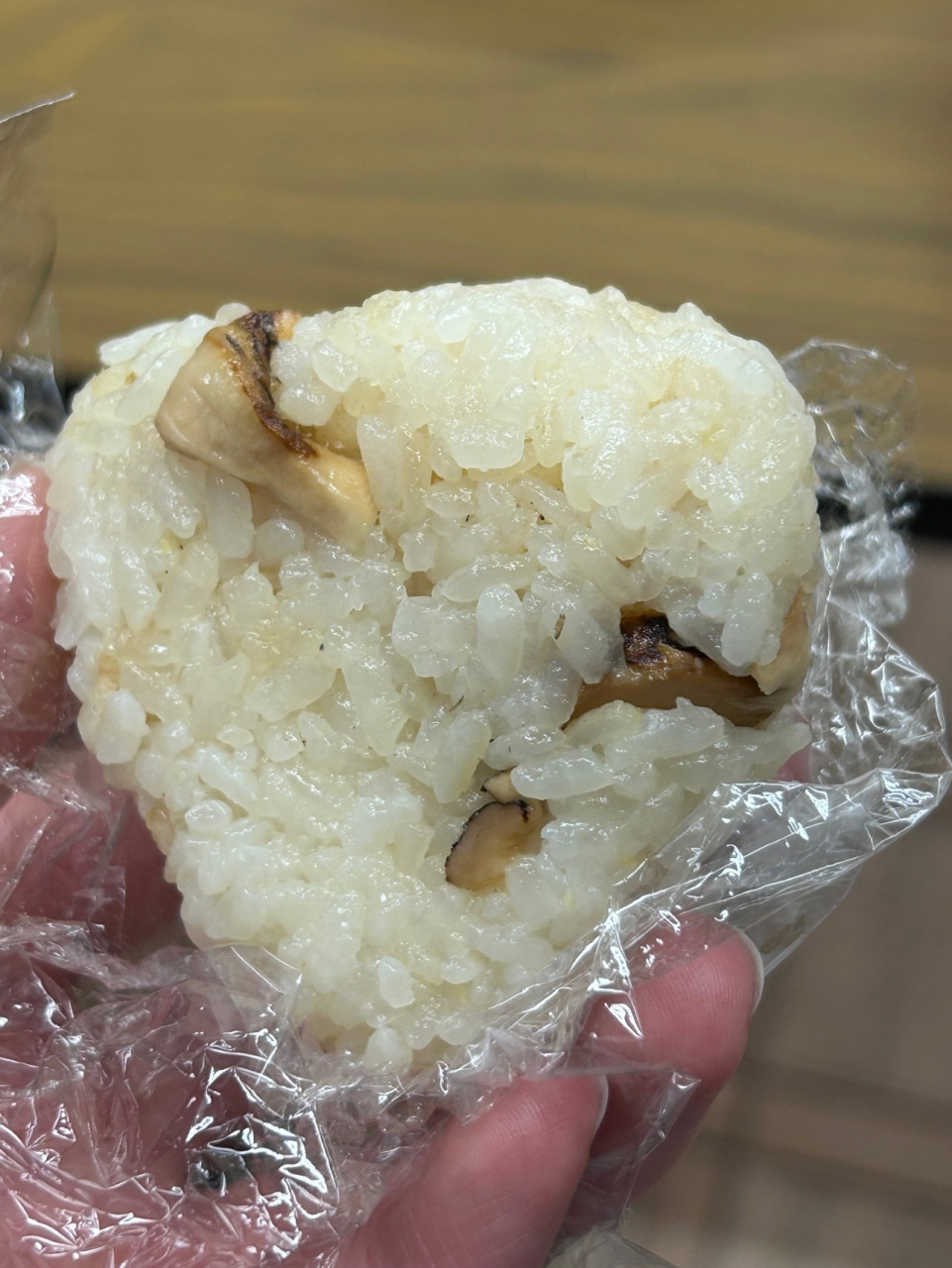研究発表・卒業論文発表に向けた練習場所について
研究発表や卒業論文発表の練習に活用できる場所をご案内します。ぜひご利用ください。
1. スチューデントコモンズ
【利用可能エリア】
深草キャンパス:クリエイティブエリア、瀬田キャンパス:コラボレーションエリア
【利用方法】
深草のラーニングサポートデスクや瀬田の情報メディアセンターでプロジェクターを
借りて、ホワイトボードに投影しながら簡単なプレゼン練習ができます。
※予約不要のフリースペースですので、気軽にご利用いただけます。
※注意:混雑状況により、使用いただけない場合があります。予めご了承ください。
2. ナレッジコモンズ
【利用可能エリア】
深草・瀬田・大宮キャンパス:図書館内のグループワークルーム
【利用方法】
グループワークルームは、事前予約制の個室で、壁面ホワイトボードを完備して
います。「MyLibrary」にログインし、「グループワークルーム予約」から申請
してください。予約状況の確認や修正も同じシステムから行えます。
※注意:2名以上で使用いただく必要があります。予約状況により、使用いただけない
場合があります。予めご了承ください。
その他利用上の注意事項など詳細は以下のページをご確認ください。
施設・機器予約 - 龍谷大学図書館
ラーニングコモンズHP → ラーニングコモンズ|龍谷大学 You, Unlimited
(参考)プレゼン資料やレジュメ作成の相談
プレゼン資料やレジュメ等の作成のうち書くことにまつわるものは、ライティング
サポートセンターで相談を受け付けています。大学院生のライティングチューター
がみなさんの考えに沿ってサポートします。ご活用ください。
詳細はHPをご覧ください。
ライティングサポートセンター|龍谷大学 You, Unlimited