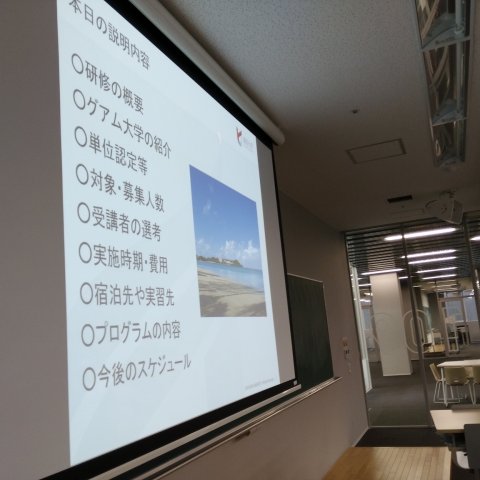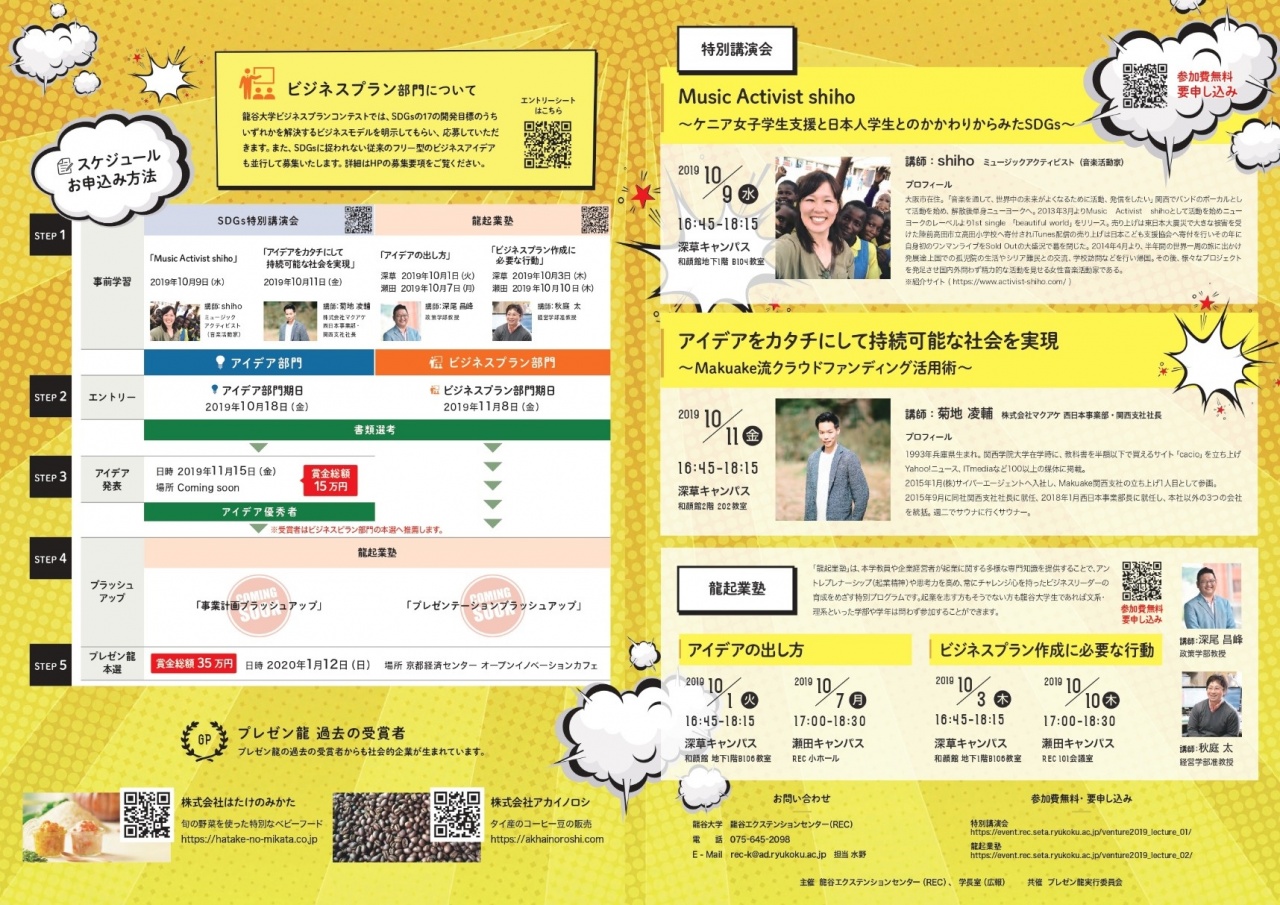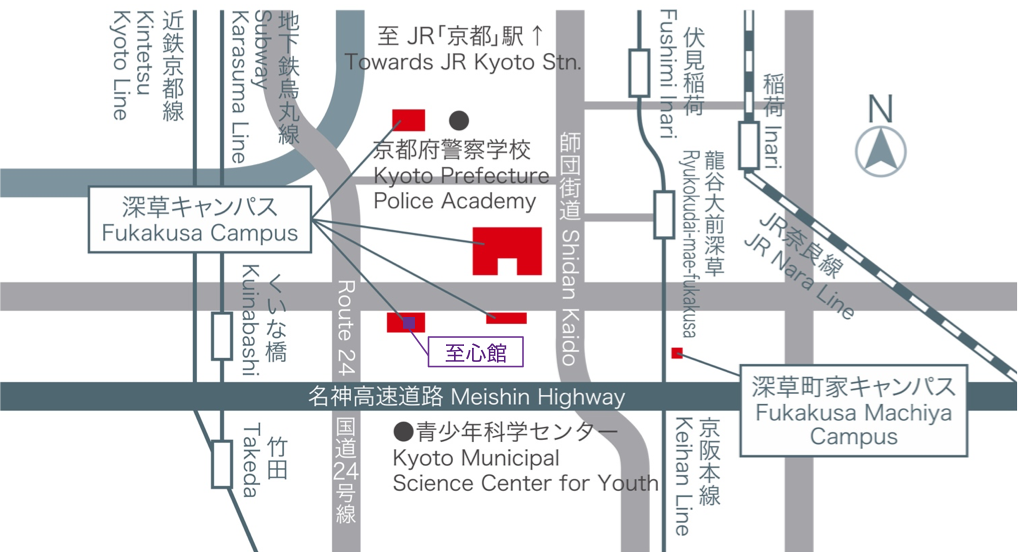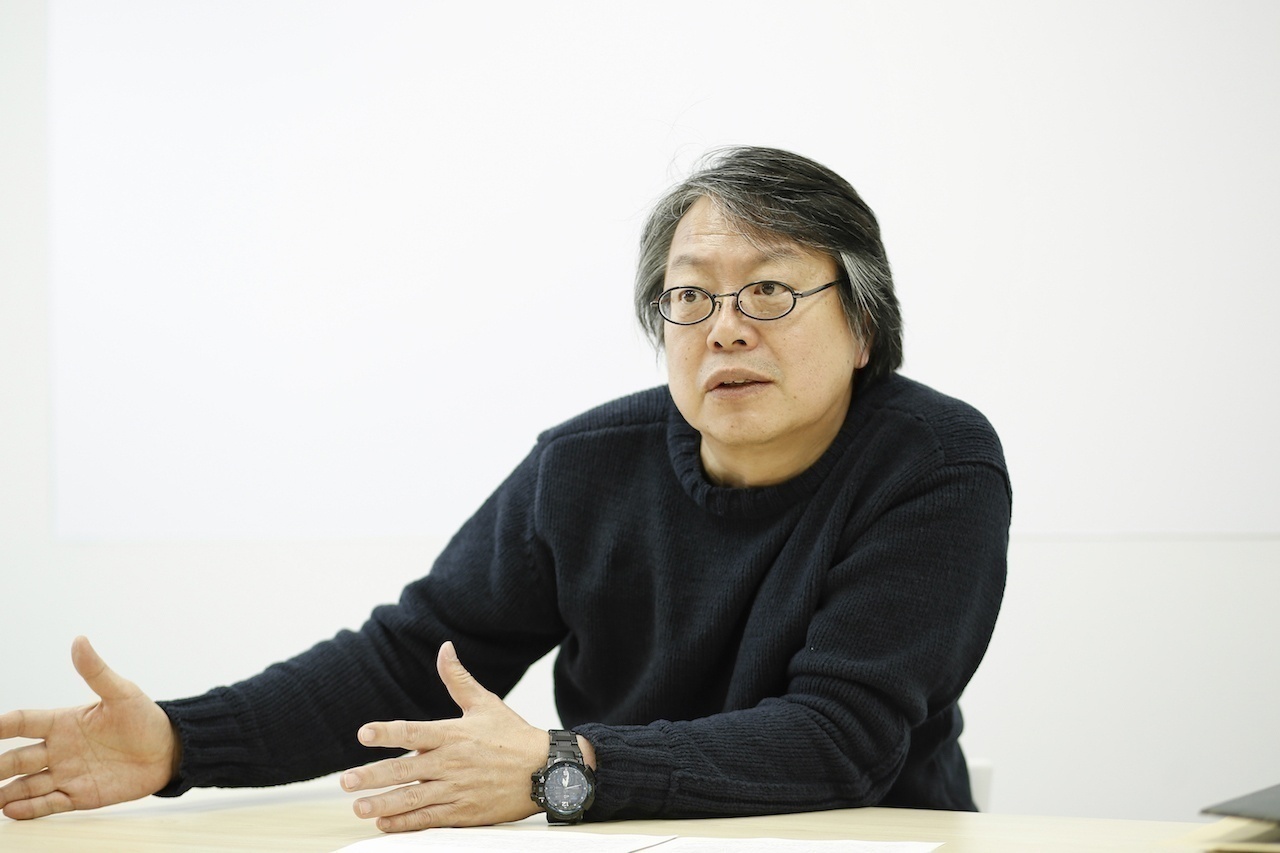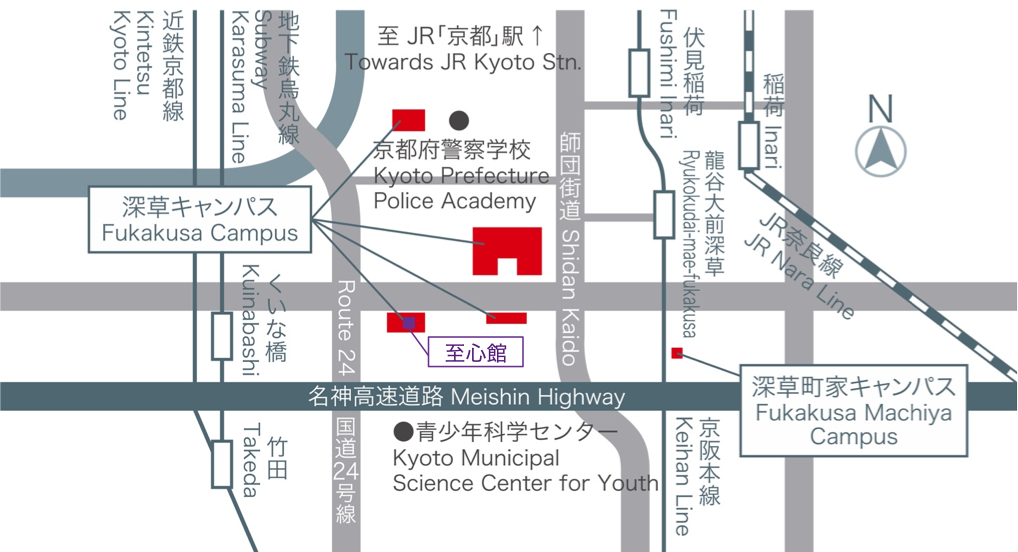小学生を対象とした「龍谷大学ジュニアキャンパス・吹奏楽体験スクール」を開催しました【REC】
龍谷エクステンションセンター、通称REC(レック)。RECでは、小学生を対象とした「龍谷大学ジュニアキャンパス」を開講しています。
2019年9月15日(日)、小学生を対象とした「龍谷大学ジュニアキャンパス・吹奏楽体験スクール」を開催しました。
本事業は、龍谷大学吹奏楽部が講師となり、楽器体験や指揮者体験、マーチング体験を通して吹奏楽の楽しさを小学生に伝えること目的としています。
スケジュールは以下のとおり。
12:15 受付開始
13:10 オリエンテーション
13:15 第Ⅰ部 コンサート&指揮者体験
14:00 楽器体験(前半)
15:10 第Ⅱ部 マーチングショー&マーチング体験
16:00 楽器体験(後半)
17:00 終了
当日は小学生が約80名、保護者や家族など総勢200名以上の参加があり、迫力の演奏を間近で感じていただいたり、10種類以上ある吹奏楽の楽器に直接触れていただいたりと、普段の演奏会では経験出来ない体験をしていただきました。