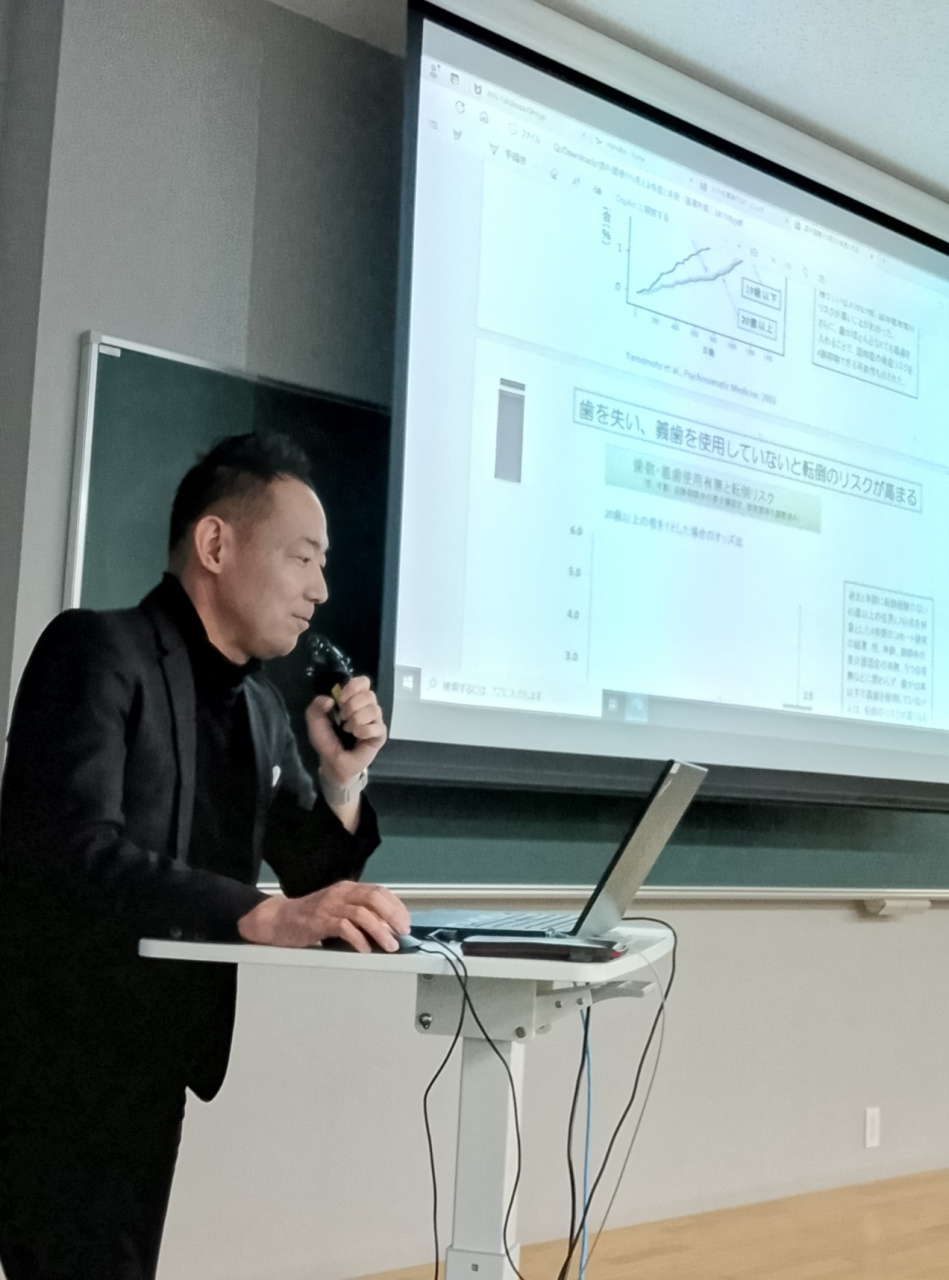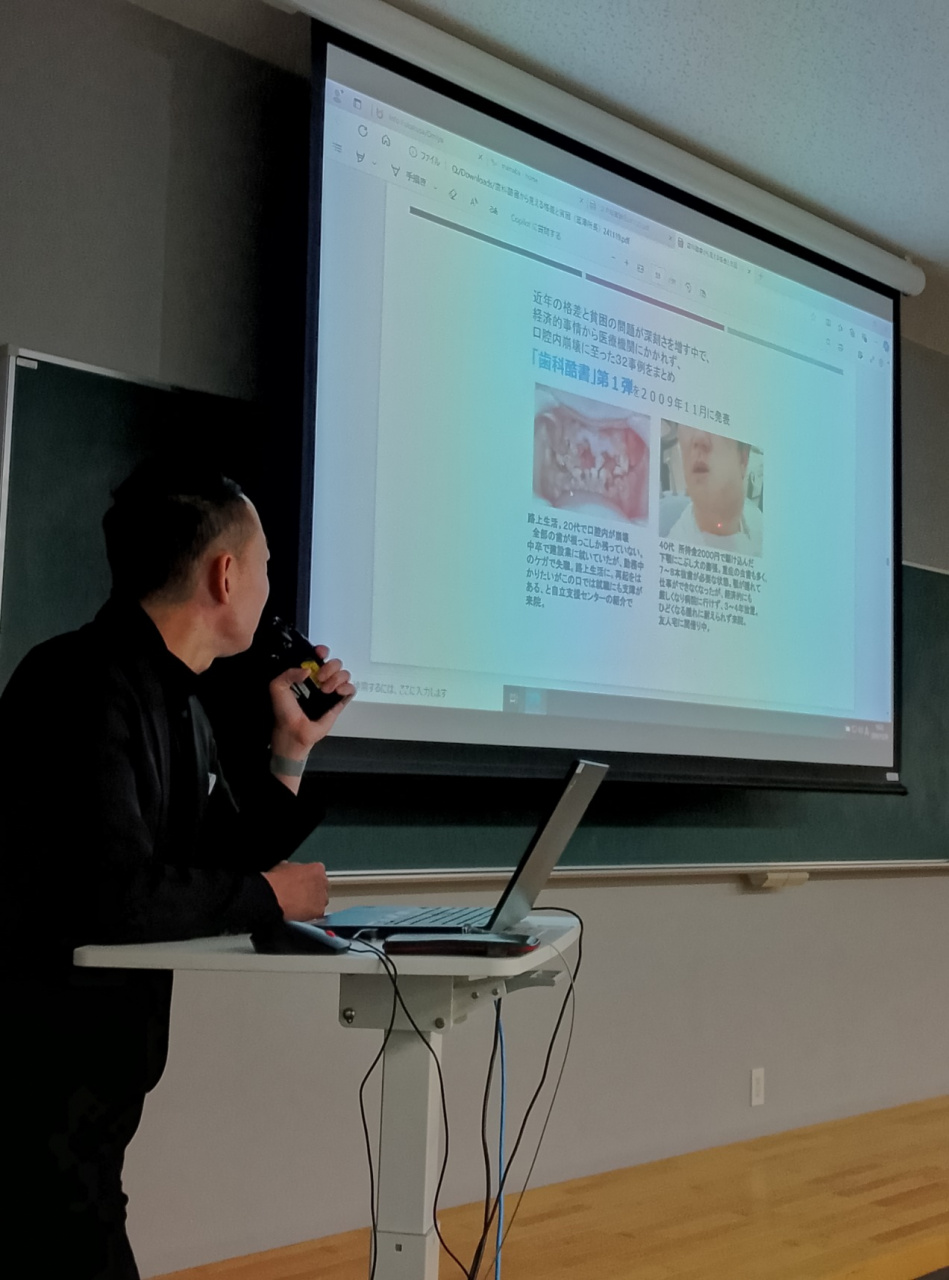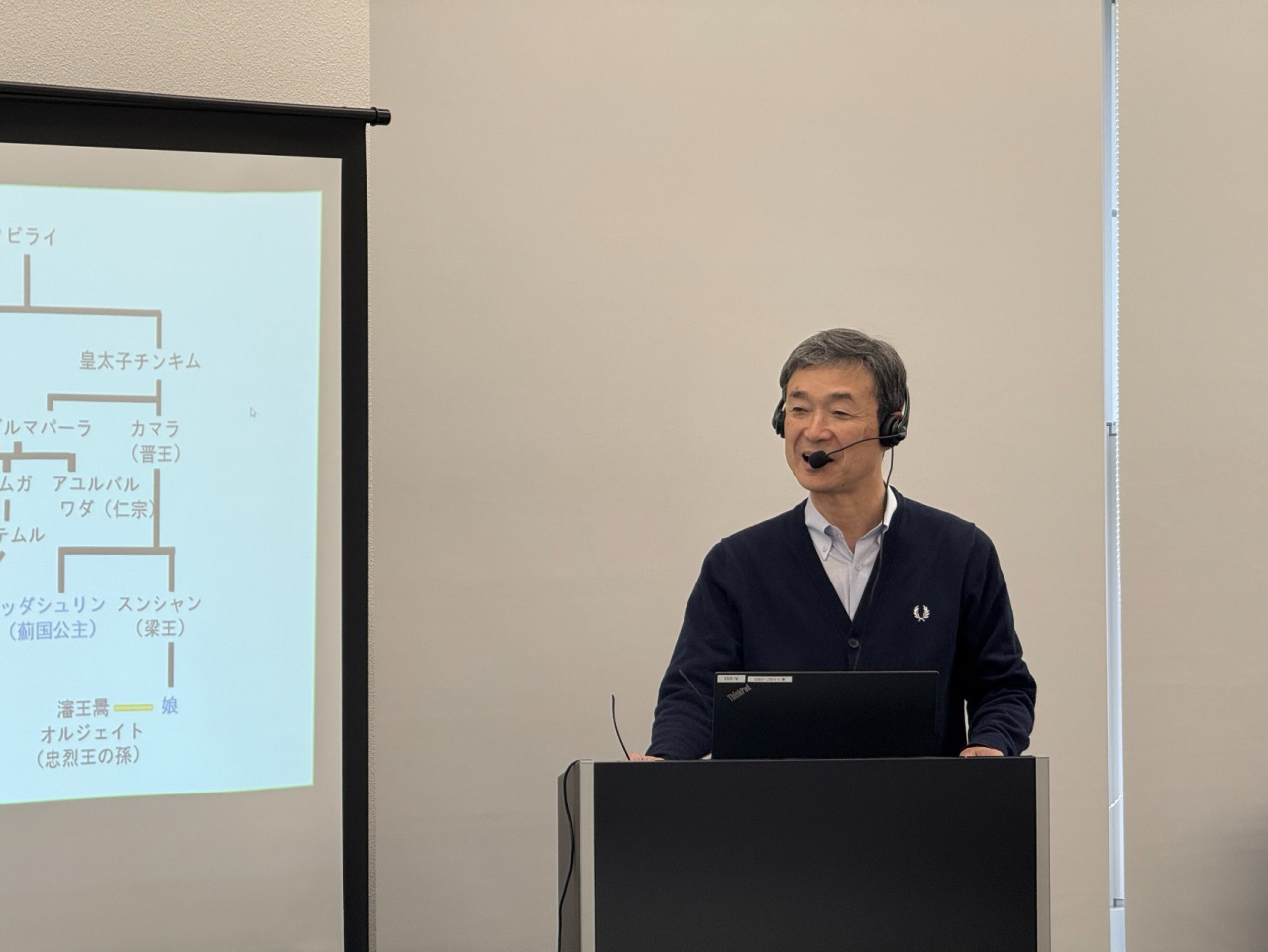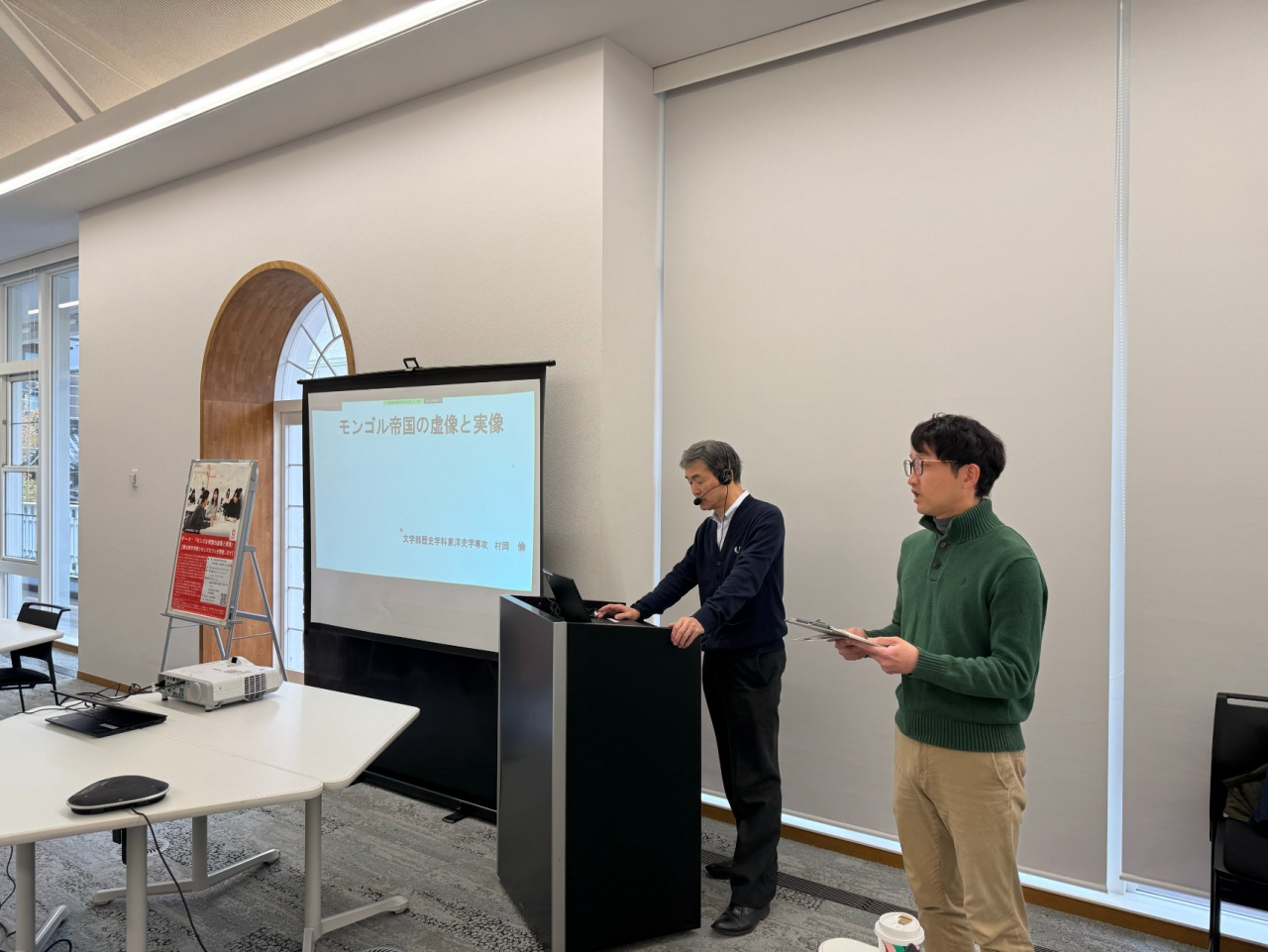龍谷大学生と地域で暮らす知的障がい者が共に学ぶ1年間の集大成 第22回ふれあい大学発表会を開催<深草キャンパス成就館12/11(水)13:30~>
【本件のポイント】
- 短期大学部社会福祉学科が2002年から毎年実施する知的障がいのある方々と学生が共に学ぶ講座
- 知的障がいのある方々は年間通じて大学の授業に通い、その集大成としてふれあい大学発表会を開催
【本件の概要】
『オープンカレッジふれあい大学課程』とは、龍谷大学短期大学部社会福祉学科で開講している地域に暮らす知的障がいのある方々と学生が共に学ぶオープンカレッジ講座です。あらゆる人々が「共生」するインクルーシブな社会を目指すための取り組みです。本課程は、2002年の開設以来、様々な講座・音楽・演劇を、障がいの有無に関わらず、共に学び、地域共生社会の実現に向けて取り組んでいます。
知的障がいのある人たち22名が、年間15回程度通学し、学生とペアを組んで、2コマの授業を選択します。学生は、準備と振り返りを含めて計30回の授業とし、単位認定を行っています。知的障がい者対象のオープンカレッジに取り組んでいる大学は全国で数多くあります。しかし、通年の正課授業(「障がい児者学習支援特講」、「音楽療法特講」、「演劇療法特講」)で取り組んでいるのは、全国的に珍しい取組です。障がいのある方々は4年間で卒業とし、修了証を学長名で出しています。
1年間の集大成として、12月11日(水)に発表会を開催します。生き生きと取り組む障がいのある方々と本学の学生の様子を、ぜひご取材ください。
●発表会の実施概要
『第22回 ふれあい大学発表会
テーマ:RESTART リスタート』
日時:12月11日(水)13:30~(開場13:00)
場所:深草キャンパス
成就館4階メインシアター
https://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/fukakusa.html
対象:学生・教職員・一般
(どなたでもご参加いただけます)

昨年度のふれあい大学発表会
問い合わせ先:龍谷大学 短期大学部
Tel 075-645-7897 tandai@ad.ryukoku.ac.jp https://www.ryukoku.ac.jp/