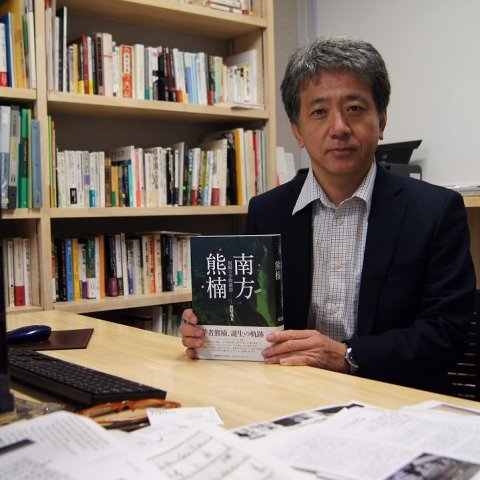龍谷大学深草キャンパス 学生活動支援施設(仮称)の起工式を挙行 5/30(木)9:30~ 深草キャンパス顕真館にて
【本件のポイント】
・ 龍谷大学が2020年6月竣工、8月供用開始の、学生活動支援施設(仮称)の建築を着工
・ 施設は、創立380周年記念事業の一貫で整備し、研修室や留学生寮、滞在施設としても利用可能な施設となる予定
・ 学生の主体的な活動を支援し、キャンパス全体を活性化することがねらい
龍谷大学は、深草キャンパス学生活動支援施設(仮称)の工事着工にあたり、起工式を開催いたします。
学生活動支援施設(仮称)は、創立380周年記念事業の一貫で整備する施設で、ゼミ活動、課外活動をはじめとした研修室や、本学のグローバル化の推進に資する留学生寮といった学生の諸活動を支援する機能に加え、卒業生、保護者等も利用できる短期研修機能、海外からの短期研究員の滞在施設として使用する教員宿舎機能を有しています。
また、深草キャンパスに隣接している立地を生かし、既存施設、特に現在建設中の学友会館跡地施設(仮称)と連携することで、学生の主体的な活動を支援し、キャンパス全体を活性化することを企図しています。
1.日 時 2019(令和元)年5月30日(木) 9:30~10:15(予定)
2.場 所 龍谷大学深草キャンパス顕真館(京都市伏見区深草塚本町67)
3.建築内容
○工事明細
学生活動支援施設(仮称)
規模: 地上5 階
構造: 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造
建築面積: 430.61 ㎡
延床面積: 1,778.29 ㎡
○建設場所 深草キャンパス
○工事期間 2019年6月~2020年6月(予定)
○供用開始 2020 年8 月1 日(予定)
○設計監理 株式会社飯田善彦建築工房
○施工 株式会社笹川組

学生活動支援施設(仮称)完成予想図
問い合わせ先 : 総務課 河角 Tel 075-645-7890