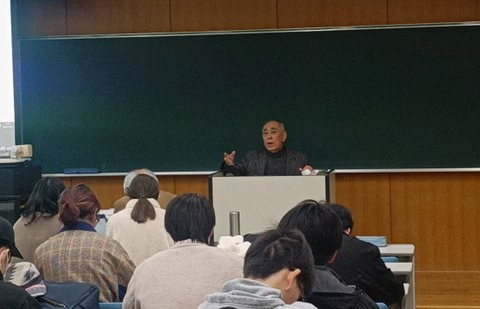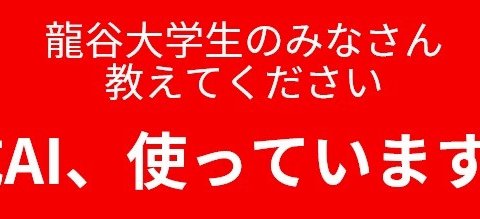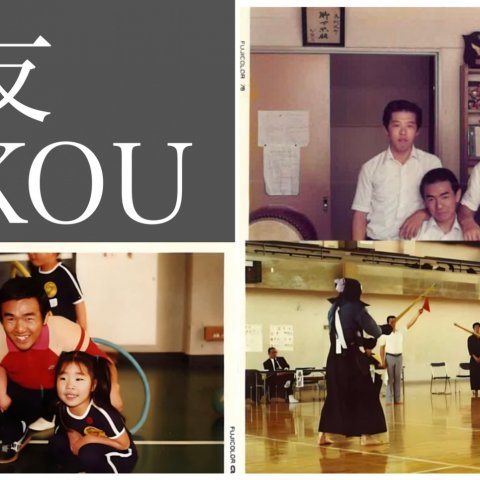滋賀ダイハツアリーナで開催されるオープン戦 『ロボカップジャパンオープン2024』に 龍谷大学 先端理工学部 植村研究室のチームが参加<開催期間:4月26日(金)~ 29日(月)>
【本件のポイント】
-
龍谷大学 先端理工学部電子情報通信課程 植村准教授が実行委員長を務める『ロボカップジャパンオープン2024(※)』のオープン戦が滋賀ダイハツアリーナにて開催。日本のみならず海外も含めて61チーム424人が参加。
-
ジャパンオープン2024では、サッカー(小型・中型・ヒト型)、レスキュー(実機・シミュレーション)、@ホーム(実機、シミュレーション)、ロジスティクスの4リーグを開催。龍谷大学(植村研究室)は「ロジスティクスリーグ」参加。龍谷大学のほか、高校2チーム(四日市工業高校、奈良商工高校)とタイの大学チームが初参加し、計4チームでの対戦を予定。
-
植村研究室のチーム「BabyTigers–R」は、RoboCup世界大会「ロジスティクスリーグ」に2011年から毎年出場しており、2015年は3位に入賞。
※ “ロボカップジャパンオープン2024”
RoboCup(ロボカップ)とは1997年から毎年行われている。世界大会だけでなく、各地域・国が開催するオープン戦があり、日本委員会が中心となって開催する大会が「ジャパンオープン」である。今回の開催は25回目。自ら考えて動く自律移動型 ロボットによる国際競技大会。サッカーの競技だけでなく、災害救助を想定したレスキューリーグ、家庭用のパートナーロボットを題材とした@ホームリーグ(アットホームリーグ)、そして植村研が参加している第四次産業革命(インダストリー4.0)の工場のオートメーション化を想定したロジスティクスリーグを開催。
【本件の概要】
4月26日(金)~4月29日(月)、龍谷大学 先端理工学部電子情報通信課程 植村准教授が実行委員長を務める『ロボカップジャパンオープン2024』のオープン戦が、滋賀ダイハツアリーナにて開催されます。
ロボカップジャパンオープンは、RoboCup世界大会をめざすチームを支援し、競技者を育成する場として重要な役割を果たす日本を会場とした競技大会です。ロボット技術の発展と交流の場として大会形式は、RoboCup世界大会に準じ、競技会、研究会を開催しており、学生たちのロボット開発のベストプラクティスや新技術を共有する機会でもあります。過去は世界大会とドイツ大会でのみ実施されてきた「ロジスティクスリーグ」を日本でも開催しようと世界大会運営委員の植村渉准教授が日本大会を提案し、2020年に日本で初めて「ロボカップジャパンオープン2020 ロジスティックリーグ」の開催を龍谷大学で実現しました。
龍谷大学 植村研究室のチーム「BabyTigers–R」が出場する「ロジスティクスリーグ」は、工場の生産ラインが大量生産から変種変量生産に変化する中、工場で活躍する自律移動型ロボットの研究とその研究発展のため、工場のオートメーション化をテーマに2011年から毎年開催されています。これに本チームは2011年から毎年出場し、顕著な成績を残してきました。また、同リーグに参加する唯一の日本チームとしてリーグの運営にも貢献し、積極的に大会をサポートしています。
植村研究室では、工場内の無人搬送車の制御技術を始めとし、アーム型ロボットを併用することで移動しながら作業するロボットの開発を進めています。本競技大会を通してソフトウエア、ハードウエアの両方を扱える人材育成に力を注ぎ、次世代の産業界へと貢献していきます。
1. 実施概要
(1)名 称 : 『ロボカップジャパンオープン2024』
(2)開催日時 : 2024年4月26日(金)~ 29日(月)9:00~17:00
(26日チーム準備日/27-28日競技/29日午前中競技、その後閉会式)
(3)開催場所 : 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀県大津市上田上中野町779番地)
(4)参加チーム: サッカー:小型10チーム、中型2チーム、ヒト型2チーム
レスキュー:実機9チーム、シミュレーション4チーム
@ホーム:実機26チーム、シミュレーション4チーム
ロジスティクス:4チーム
計:61チーム424人(うち海外9チーム、66人)
(5)主 催 : ロボカップジャパンオープン2024開催委員会
(特定非営利活動法人ロボカップ日本委員会)
実行委員長:植村 渉(ロボカップ日本委員会専務理事/
龍谷大学 先端理工学部 電子情報通信課程 准教授)
(6)協 力 : 龍谷大学 先端理工学部
2. 当日会場での取材について
ご取材いただける場合は、事前に問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
当日の参加も可能です。当日の場合は、受付で取材希望とお伝えください。
3. その他
競技に合わせて下記URL(大会ページ)にて各リーグの動画公開予定。
https://www.robocup.or.jp/japanopen2024
問い合わせ先:龍谷大学 先端理工学部 電子情報通信課程 准教授 植村 渉
Tel 077-543-7410 E-mail wataru@rins.ryukoku.ac.jp