グアム大学(国際交流一般協定)の学生と短期国際交流プログラムを実施します!【R-Globe】
本学は3月18日(月)~22日(金)の間、国際交流一般協定校であるグアム大学(グアム)の短期留学プログラムを本学で実施します。
本プログラムはグアム大学の人気科目「Travel Studies in Asia」の一部です。
本学の清水耕介教授(国際学部長・グローバルスタディーズ学科)による京都学派(哲学)をテーマとした講義のほか、京都の文化・歴史・環境・哲学を学びます。
また、プログラム初日には龍谷大学の学生バディが深草キャンパスを紹介し、学生食堂での昼食を一緒に楽しむ予定です。
一週間を通して、龍谷大学の学生バディはグアム大学の学生達と共に、京都市内の様々な観光スポット(清水寺、哲学の道、伏見稲荷大社、嵐山、サムライ忍者体験ミュージアムなど)に同行し、国際交流をおこないます。
グローバル化する経済・社会の中でますます重要となる人的ネットワークを形成するとともに、相互理解の増進や友好関係の深化を図る機会となることを願っています。




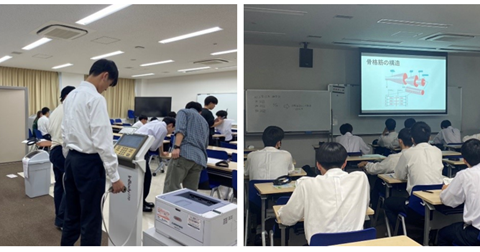


![出典:『合類日用料理抄』[巻四]魚類/塩漬の類(東京学芸大学附属図書館所蔵)※ページ左にふなずしについての記載](https://www.ryukoku.ac.jp/nc/archives/001/202402/197041f132b7ed0ad302b366b299ebfa3ba566c96f96140f47c4d3b3c507f0b1.jpg)


