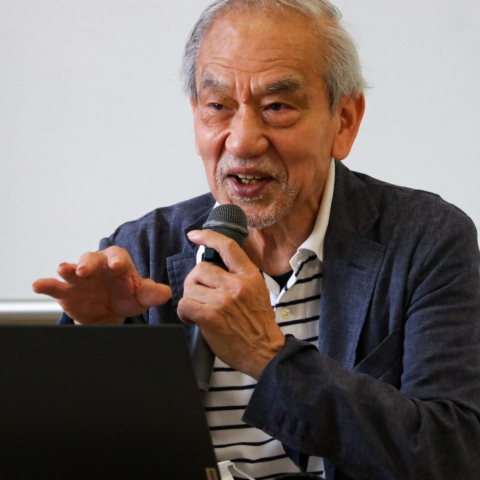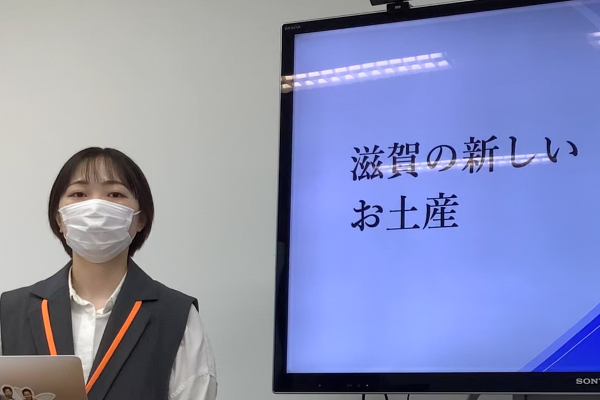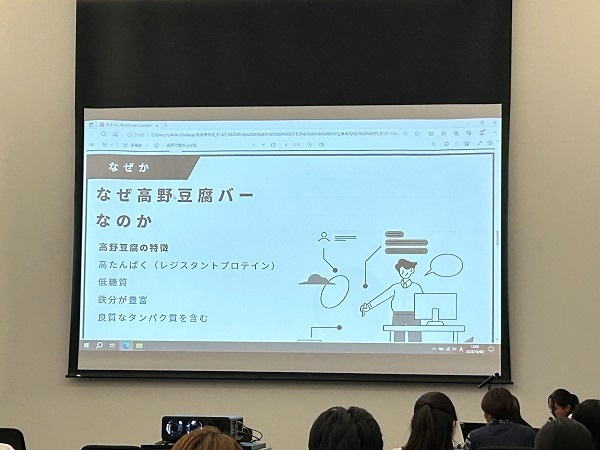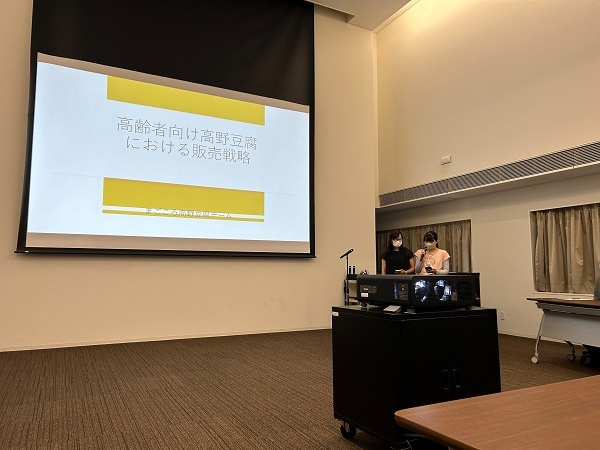日本学生支援機構奨学金 高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)の『在籍報告(10月)』の手続きについて
日本学生支援機構の高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)に採用された者は、大学に在籍していることを定期的(4月・10月)に日本学生支援機構へ報告するための『在籍報告』の手続きが必要です。手続きを怠った場合、給付型奨学金の支給が止まります。
1. 対象
日本学生支援機構の高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)に、令和5年9月までに採用された者(全員)
※休学・留学・停止中であっても手続きが必要です。
2. 手続き方法
在籍報告は、奨学生自身がインターネット(スカラネット・パーソナル)から行います。詳細は「在籍報告(兼通学形態変更届)」の提出手続きリーフレット(入力準備用紙)で確認の上、手続きを進めるようにしてください。
定められた期限までに報告がなく、大学等に在籍していることが確認できない場合は、給付奨学金の支給が止まります。また、停止となった期間分は支給総月から減じられます。
必ず期限内に手続きを完了させてください。
日本学生支援機構の奨学生が自身の奨学金に関する情報をインターネット上で閲覧できる情報システムです。
2023年4月以降に採用され、スカラネット・パーソナルを今回初めて利用する者は、まず新規登録を行った後に『在籍報告』を提出(入力)してください。
3.報告期限
| 報告期限 | 2023年10月4日(水)~10月23日(月)<期限厳守> |
|---|---|
| 入力時間 | 8:00~25:00 |
4. 「自宅外通学の証明書類」の提出について【該当者のみ】
今回、通学形態を「自宅」から「自宅外」に変更希望する者のみ、「自宅外通学を証明する書類」を大学へ提出してください。
すでに「自宅外を証明する書類」を提出し、自宅外月額を受給中の者は、新たに提出する必要はありません。
【提出書類】
① 通学形態変更届(自宅外通学)(指定様式)
② 自宅外を証明する書類(賃貸借契約書、入寮許可証等)
5. 「在留資格の証明書類」の提出について【該当者のみ】
国籍を「日本国以外」に変更した者、在留資格を変更した者、在留期間(満了日)を更新した者は、在留資格を証明する書類の提出が必要です。
【提出書類】
① 給付奨学金『在留資格証明書類』提出書(指定様式)
② 在留資格に関する証明書類(「在留カード」のコピー、「特別永住者証明書の両面コピー、「住民票」のコピー等)
【書類提出先】
龍谷大学 学生部 奨学金担当
(深草・大宮学舎対象)
〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67 4号館1階
受付時間 9:00~17:00(毎週火曜日は10:45~)
(瀬田学舎対象)
〒520-2194 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5 4号館地下1階
受付時間 9:00~11:30,12:30~17:00(毎週火曜日は10:45~)
※やむを得ず郵送で書類を提出する場合は、レターパックや特定記録等、自身で配送履歴を追跡できる方法で送付してください。