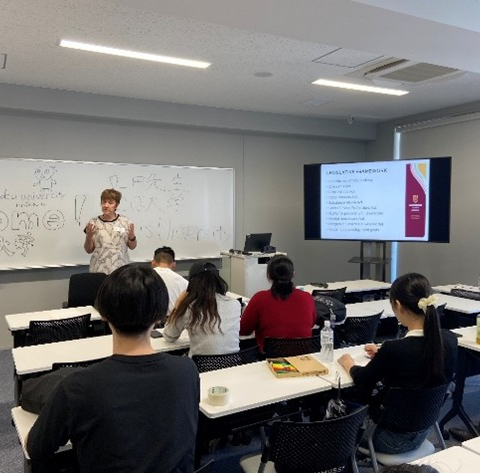国際学部長に 清水 耕介 教授を再任 <任期>2026年4月から2年間
清水 耕介 国際学部長の任期満了(2026年3月31日)にともなう選挙会を10月29日(水)におこなった結果、次期国際学部長に清水 耕介 教授を再任しましたので、お知らせいたします。
なお、清水 耕介 教授の略歴は下記のとおりです。
【龍谷大学国際学部長】
任 期 : 2026年4月1日から2028年3月31日まで
氏 名 : 清水 耕介(しみず こうすけ)教授
【専門分野】
国際関係論、政治学
【学 歴】
西南学院大学大学院経済学研究科修士課程修了
ニュージーランド国立ヴィクトリア大学政治学国際関係学大学院博士課程修了
【学 位】
Ph.D. in International Relations
【職 歴】
2005年4月 龍谷大学国際文化学部助教授
2011年4月 龍谷大学国際文化学部教授
2015年4月 龍谷大学国際学部グローバルスタディーズ学科教授(現在に至る)
2022年4月 龍谷大学国際学部長(現在に至る)
【研究業績】
An East Asian approach to temporality, subjectivity and ethics: bringing
Mahāyāna Buddhist ontological ethics of Nikon into international relations
(Cambridge Review of International Affairs 2023年)
Buddhism, Quantum Theory, and International Relations: On the strength of the subject,
the discontinuous relationality, and the world of contingency
(International Political Theory 2023年)
A Non-Western Attempt at Hegemony: Lessons from the second-generation Kyoto
School for international pluralism an its discontents (Global Studies Quarterly 2022) など
【所属学会】
日本政治学会、日本国際政治学会、International Studies Association(US)等
問い合わせ先 : 龍谷大学国際学部教務課 鹿谷・友次 Tel 075-645-5645