食料農業システム実習「香港フードエキスポ2023」研修での学び(前半)

ここにメッセージを入れることができます。



吹奏楽部 第46回全日本アンサンブルコンテストで金賞を受賞 日本一に輝く【学生部】
2023年3月19日(日)、アクトシティ浜松にて、第46回全日本アンサンブル...
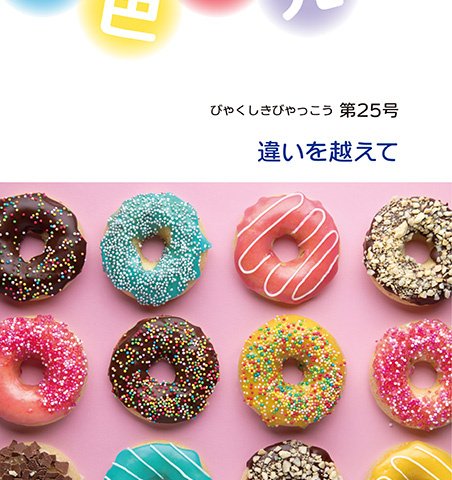

龍谷大学経営学部の秋庭ゼミでは3月20日(月)に第11回 日本酒勉強会を...

近隣の小学生が、キャンパス内で大学生と遊ぶイベント「龍谷キッズふれあいパーク」を開催<3月27日(月)9:00~15:00/深草キャンパスにて開催>
【本件のポイント】 「ふかくさ輝っず(きっず)児童館」でボランティア...

2023年8月14日~8月27日の間、龍谷大学の協定校である国立中央大学の「NCU Summer Program 2023」に本学より2名が参加しました。
以下、学生レポートを紹介します。
〈宿泊施設など〉
台湾の桃園市に位置する国立中央大学で開催された、短期留学プログラム「NCU Summer Program」には本学からは2名が参加し、他大学からは20名ほど参加者がいました。このプログラムは2週間の滞在で、航空券を自分で取ると、大学までピックアップしてくれます。
寮は国立中央大学中大曾館の1人一部屋でした。部屋にはベッド、冷蔵庫、トイレ、シャワールーム、ドライヤーがあります。トイレについてですが、日本と違って紙を流すことができません。拭いた紙は、備え付けのゴミ箱に捨てることになります。また、シャンプーや歯ブラシなどの消耗品は無いので、事前に買っておく必要があります。共同部屋には洗濯機、乾燥機、ウォーターサーバーがあります。ハンガーや洗剤はありません。
台湾では朝ごはんが有名で、台湾の人々は朝ごはんを食べるために朝早く起きるそうです。食事はほぼ外食で、日本より安く、ボリュームがあります。
台湾ならではの料理が沢山あり、どれも美味しいので、毎食何を食べるか悩みました。学内にも沢山の飲食店があり、コンビニや生活用品を販売している店もあります。また、台湾には夜市が多くあるので、土日や授業が終わってから行くこともありました。
学費や宿泊費は本校が負担してくれるので、台湾に興味がある方は参加してみてはいかがでしょうか?台湾での生活は慣れないことも多いですが、毎日が新鮮でとても楽しいです!


〈Field Trip-國立故宮博物館・龍山寺など〉
通常は中国語の授業が午前と午後に3時間ずつありますが、この日は1日中校外学習として、早朝に集まりバスで移動しました。午前は、世界四大博物館の1つである國立故宮博物館に行き、午後は、龍山寺に行きました。龍山寺では、ツアーガイドの方が龍山寺の歴史について詳しく教えて下さりました。また、それだけでなく、ガイドの方が端的にまとめられた資料を私たち学生が読むという参加型のツアーでもありました。その後は、周辺の市場や西門町を散策し、夕方頃に国立中央大学に戻りました。
私は、この1日を通して、日本では博物館では撮影不可能な場所が多いですが、國立故宮博物館では、撮影可能であることに驚きました。この博物館のメインである白菜の展示品は残念ながら見ることはできませんでしたが、焼き豚の形をした石は見ることができ、私たち参加学生だけではなく、他の観光客もこの展示品には人が多く集まっており、人気の高さをうかがえました。外に出ましたが、晴れていたことで、景色も良くまるで中国の歴史ドラマが蘇る宮殿のようで感動しました。午後の龍山寺は仏像を見るたびに1年生の頃に学んだ仏教を思い出しました。龍山寺には独特なおみくじのやり方があり、私はうまくいかなかったため、またリベンジしたいです。



1994年に横浜で開催された「第10回国際エイズ会議」をきっかけに市民による市民のためのフォーラム「AIDS文化フォーラムin横浜」が開催され、以降、HIV/AIDSに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また、多くの市民、特に若者に向けた啓発の場として各地で開催されてきました。京都では2011年に第1回(会場:龍谷大学大宮学舎)が開催されて以来、毎年開催され、龍谷大学も当初から開催を後援・協力してきました。2019年度からは再び龍谷大学(深草学舎)を会場として開催されています。
なお、第13回となる2023年度のAIDS文化フォーラムin京都は、対面での開催となります。龍谷大学もブースの出展や発表を予定しています。事前申し込み不要、参加無料、どなたさまもお気軽にご参加ください。
■■■ 第13回AIDS文化フォーラムin京都 ■■■
--------------
~『つなぐ』『つながる』新たな旅立ち~
--------------
日程:2023年10月7日(土)12:30~18:30
2023年10月8日(日)10:00~17:00
会場:龍谷大学深草学舎 和顔館
主催:AIDS文化フォーラムin京都運営委員会
共催:京都府、京都市
後援:龍谷大学、龍谷大学人権問題研究委員会、龍谷大学犯罪学研究センターほか
お問い合わせ:AIDS文化フォーラムin京都運営委員会
詳細 http://hiv-kyoto.com/
夏のオープンキャンパスを開催しました。
8月5日、6日、26日、27日の4日間開催し、文学部のイベントと合わせて多数の高校生や保護者の方に大宮キャンパスへお越しいただきました。
心理学部では、学部紹介イベントや、在学生による心理学の学び紹介イベントを開催しました。
在学生による学び紹介では、心理学部1年生から、志望した理由や、実際に受講している授業の紹介など、学生ならではの目線で紹介をしてくれました。
来場者からは「心理学部で学ぶイメージがつかめた」「心理学部以外の受験を考えていたが、心理学にも興味が湧いた」など、高い満足度でした。
今後もオープンキャンパスだけでなく、さまざまな機会で心理学部の魅力を発信していきます。


2023年9月の宗教行事・宗教部関連行事のご案内です。どなたもご自由にご参加ください。
■9月21日(木) 12:15~13:15
ご生誕法要
講演 「地域社会における寺院の役割」
講師 大正大学社会共生学部専任講師 髙瀨顕功さん
場所 瀬田学舎 樹心館
配信 https://youtube.com/live/hxKTbzHD0FQ
■朝の勤行 朝8:55~(15分程度)
深草学舎顕真館 9月8日までは応接室、9月11日からは講堂にて
大宮学舎本館 9月19日(火)から再開します
瀬田学舎樹心館 9月19日(火)から再開します