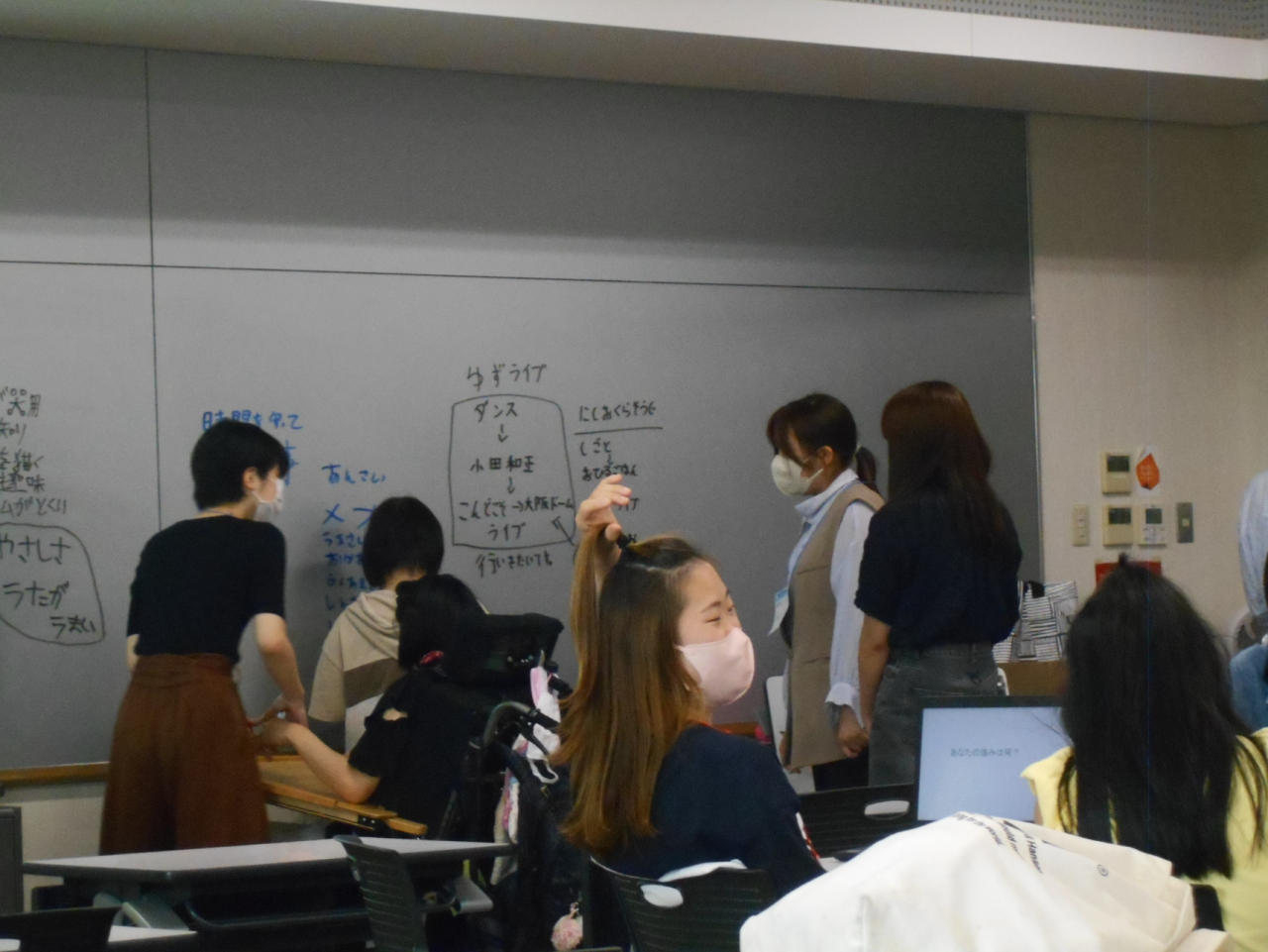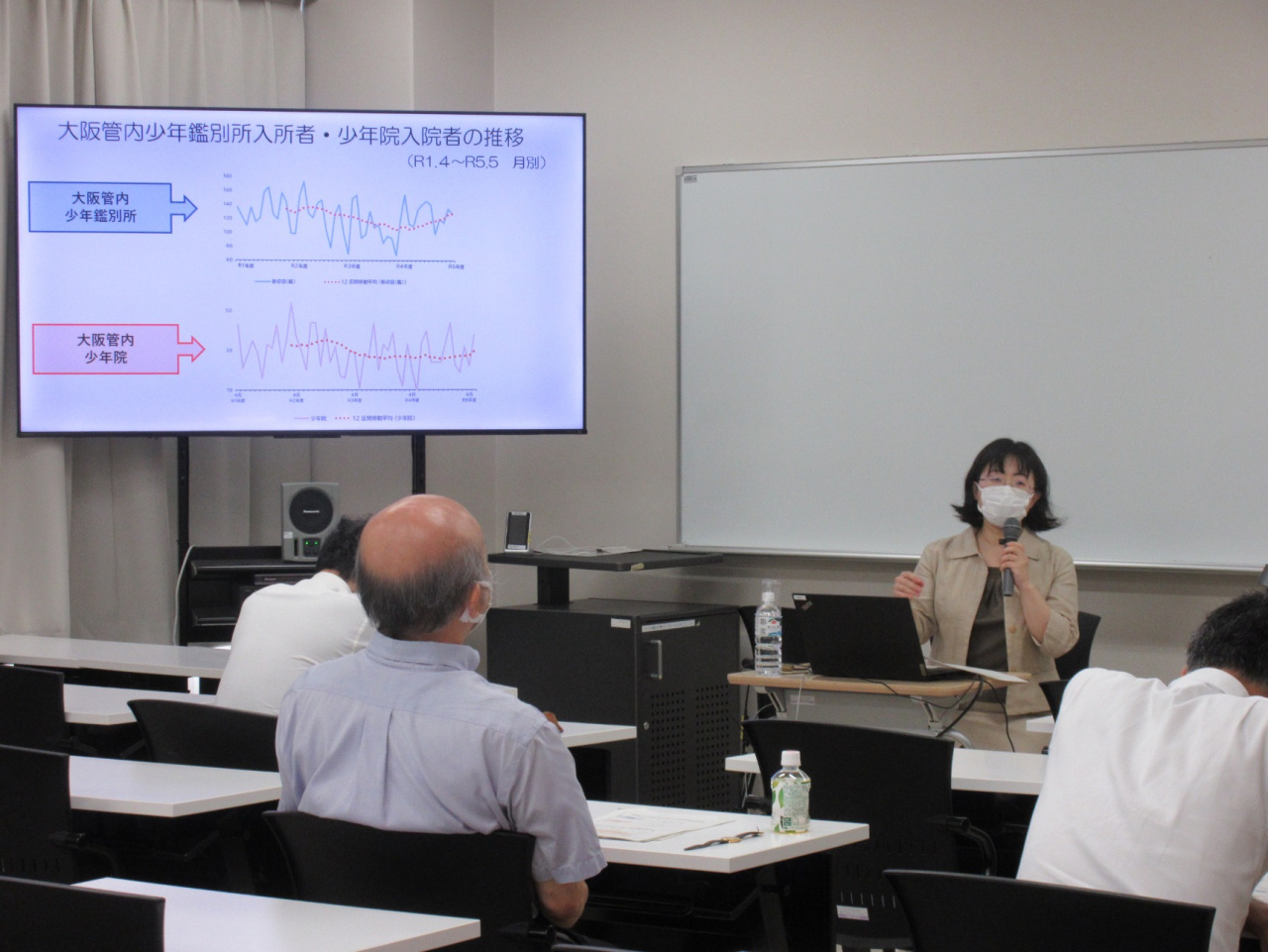夏期休業期間(8/6~9/8)における深草学舎紫英館・和顔館・紫光館・至心館 ・成就館出入口及び各門扉の開閉時間変更について (お知らせ)
所管:総務部総務課
標記の件について、下記のとおり開閉時間を変更いたします。
記
- 変更期間 夏期休業期間 2023年8月6日(日)~9月8日(金)
- 変更内容 以下のとおり
| 場所 | 開閉時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開扉 | 閉扉 | |||
| 講師控室 | 紫英館講師控室 | 8:30 | 17:30 | 土・日・祝日・一斉休暇期間(8/11~8/18)は閉室 期間外授業、サマーセッションⅠ・Ⅱ期間、短大補講日は変更 ※1 |
| 2号館講師控室 | 閉 室 | ー | ||
| 建物扉 | 紫英館正面玄関 | 8:00 | 20:00 | 土・日・祝日・一斉休暇期間(8/11~8/18)は閉鎖 |
| 紫英館1F北口 (政策学部教務課横) | 8:00 | 22:00 | ||
| 紫英館1F南口 (教学部・教職センター横) | 8:00 | 18:00 | ||
| 和顔館(北棟)1F東出入口(東門前) | 8:00 | 22:00 | 土は8:00~19:00開扉 日・祝日・一斉休暇期間(8/11~8/18)は閉鎖 | |
| 8号館正面玄関 | 8:00 | 20:00 | 土・日は9:00~18:00開扉 ※9/3は閉鎖 祝日・一斉休暇期間(8/11~8/18)は閉鎖 | |
| 成就館北側出入口 | 8:00 | 22:00 | 一斉休暇中(8/11~8/18)の開閉時間は別途お知らせします。 | |
| 紫光館北東出入口 | 閉 扉 | ー | ||
| 紫光館東側通用口 | 8:00 | 23:00 | 日・祝日は9:00~19:00開扉 | |
| 至心館正面玄関 | 8:00 | 22:00 | 日・祝日は閉鎖 | |
| 紫光館別館北側扉出入口 | 閉 扉 | ー | ||
| 門扉 (駐輪場含む) | 通用門(第一軍道側) | 7:00 | 22:00 | 一斉休暇中(8/11~8/18)は閉鎖 |
| 自動車専用門(車輌通用門) | 7:00 | 22:00 | ||
| 正門(西小門) | 8:00 | 22:00 | 8/7~8/25は上空通路関連の試掘工事のため閉鎖 土は8:00~19:00開門 日・祝日・一斉休暇中(8/11~8/18)は閉鎖 オープンキャンパス実施日は変更 ※3 |
|
| 東門(大門) | 8:00 | 22:00 | 土は8:00~19:00開門 日・祝日・一斉休暇中(8/11~8/18)は閉鎖 オープンキャンパス実施日は変更 ※3 |
|
| 西門 | 8:00 | 18:30 | 8/7~8/25は8:00~22:00開門 8/19(土)は8:00~19:00開門 日・祝日・一斉休暇中(8/11~8/18)は閉鎖 | |
| 2号館西北駐輪場(自転車専用) | 7:00 | 22:00 | 一斉休暇中(8/11~8/18)は閉鎖 | |
| 紫英館バイク置き場 | 7:00 | 22:00 | ||
| 正門 (大門・東小門) | 閉 鎖 | サマーセッションⅠ・Ⅱ期間は変更 ※2 オープンキャンパス実施日は変更 ※4 | ||
| 東門(小門) | 期間外授業、サマーセッションⅠ・Ⅱ期間、短大補講日は変更 ※1 オープンキャンパス実施日は変更 ※4 |
|||
| 北門(和顔館中央) 北門(顕真館横) |
閉 鎖 | ー | ||
ただし、次の期間は、門扉開閉時間を変更いたします。
※1 ・期間外授業実施可能日(8/7~10、21~22)
・サマーセッションⅠ期間(8/26、28~9/1)・Ⅱ期間(9/2、4~8)
・短大補講日(8/19、他の日程は上述期間に含まれる)
東門(小門) 8:00~22:00開門(土曜日は8:00~19:00開門)
紫英館講師控室 8:00~18:45開室
※2 ・サマーセッションⅠ期間(8/26、28~9/1)・Ⅱ期間(9/2、4~8)
正門(大門・東小門)、東門(小門) 8:00~22:00開門
(土曜日は8:00~19:00開門)
紫英館講師控室 8:00~18:45開室
※3 ・オープンキャンパス実施日(8/6、27)
正門(西小門)、東門(大門) 8:00~18:00開門
※4 ・オープンキャンパス実施日(8/6、26、27)
正門(大門・東小門)、東門(小門) 8:00~18:00開門
●保安警備上、23:00~翌朝7:00までの学舎内への入構はできません。やむを得ず前述の時間帯に入構する場合は、必ず事前に紫英館守衛所まで届け出てください。
●上記内容は行事、授業の開講状況により変更する場合があります。
以上