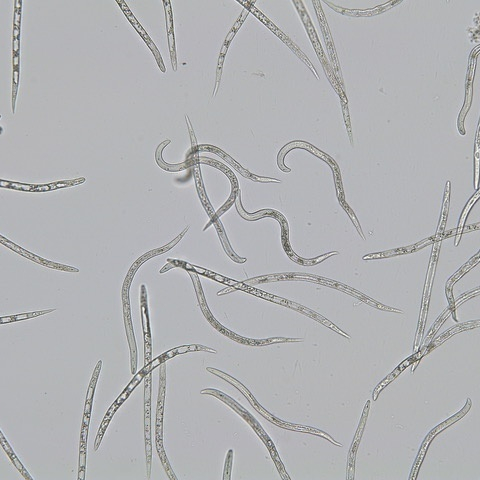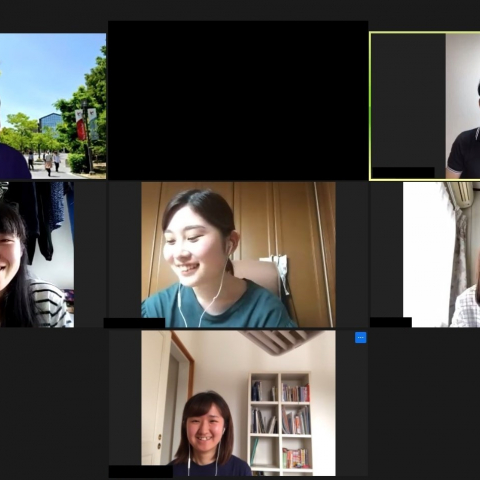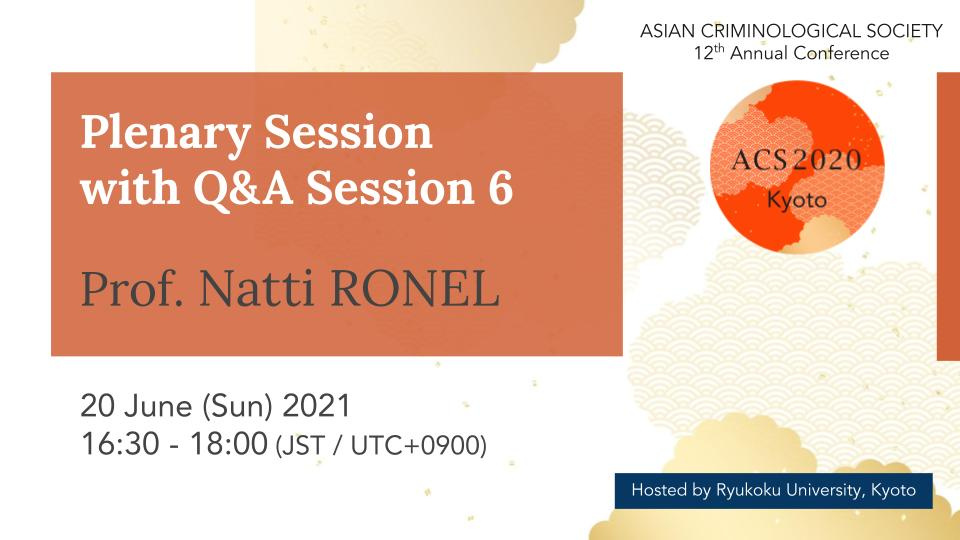龍谷ミュージアム シリーズ展10「仏教の思想と文化 ―インドから日本へ― 特集展示:釈迦信仰と法華経の美術 ―岡山・宗教美術の名宝Ⅱ―」開催のお知らせ(7月10日~8月22日)
【展覧会のポイント】
- 昨年度の企画展「ほとけと神々大集合 ―岡山・宗教美術の名宝-」に続く、岡山特集第2弾。
- 重要文化財1点を含む、釈迦信仰、法華経に関する約50件の作品を特集展示として紹介。
- 特集展示は、岡山県立博物館(改修工事中)からの寄託品を中心に構成。京都で岡山の名宝に触れる貴重な機会。
展覧会の概要
1.名称: シリーズ展10「仏教の思想と文化 -インドから日本へ-
特集展示:釈迦信仰と法華経の美術 -岡山・宗教美術の名宝II-」
2.会期: 2021年7月10日(土)~8月22日(日)
3.休館日: 月曜日(ただし、8月9日は開館)、8月10日
4.開館時間: 10:00~17:00(入館は16:30まで)
5.会場: 龍谷大学 龍谷ミュージアム
〒600-8399 京都市下京区堀川通正面下る(西本願寺前)
6.主催: 龍谷大学 龍谷ミュージアム、京都新聞社
7.入館料: 一 般550円、シニア450円、大学生400円、高校生 300円
※ シニアは65歳以上
※ 中学生以下、障がい者手帳等の交付を受けている方およびその介護者1名は無料
8.備 考:
⑴本展は予約優先制です。ご予約がなくとも当日券によりご入館いただけますが、混雑時には、ご入館までお待ちいただくことがあります。
⑵事前予約や、新型コロナウイルス感染対策に関するお願い等、最新情報は龍谷ミュージアムHPをご確認ください。 https://museum.ryukoku.ac.jp/
問い合わせ:龍谷ミュージアム事務部 TEL:075-351-2500/FAX:075-351-2577