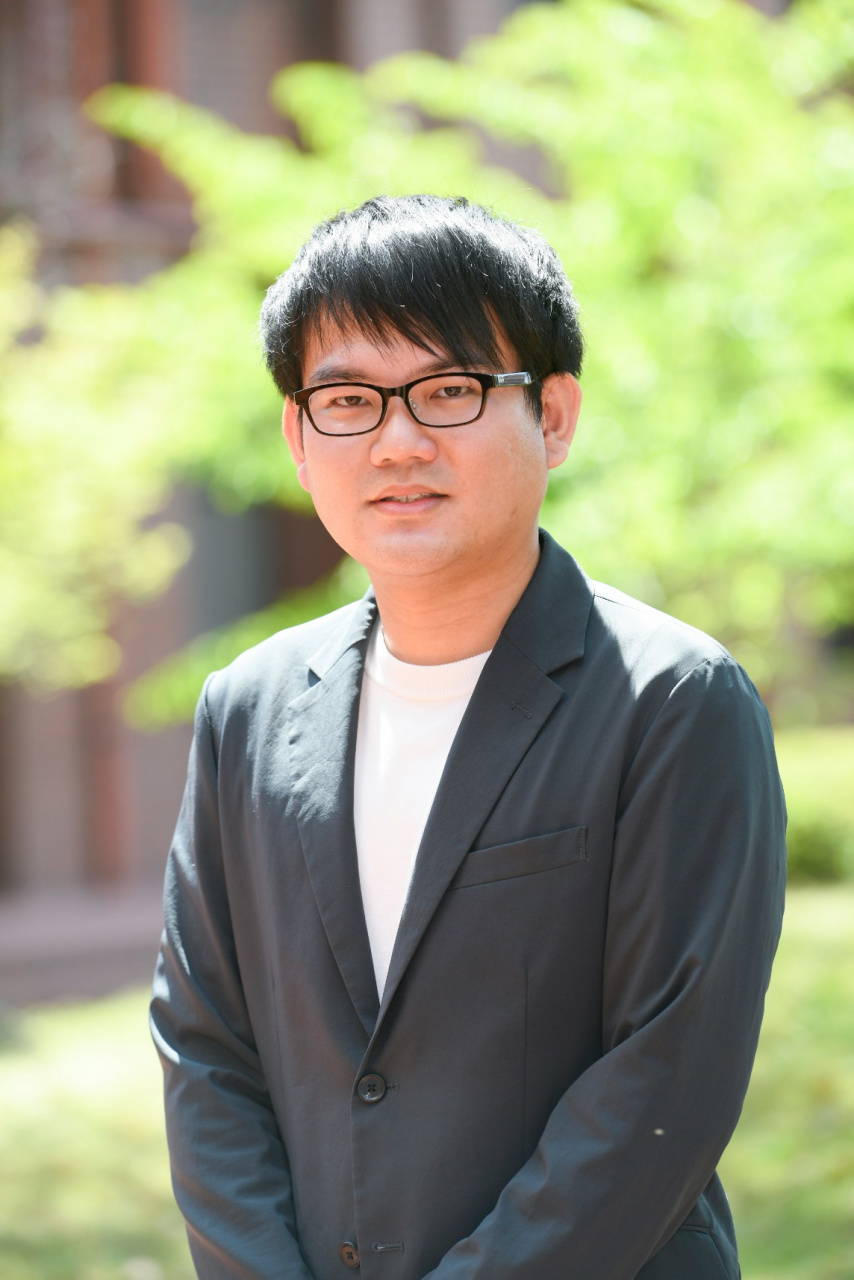新任教員の紹介(経済政策 高尾 築 講師)【経済学部・経済学研究科】
2021年4月、経済学部に新たに着任した教員をご紹介します。
■経済学部 現代経済学科
高尾 築(たかお きづく)講師
<自己紹介>
出身は大阪府で、学部4年間は京都の大学で過ごし、 水泳サークルの集まりでよく木屋町通のさざんか亭で飲んでました笑
学生時代はバックパッカーもしていて、中東にも数回行ったことがあります。
小さい頃から地図が好きで、食い意地も張っているので、これからも色んなところに出かけて、美味しいものを食べて、景色や街並みを見たいと思っています。
院生時代には、台湾の台北にあるAcademia Sinicaという研究所に一年間研究留学をしていました。その縁で、台湾にはその後もちょくちょく行かせてもらっています。
また、前任校は東北の大学だったので、そこですっかり温泉フリークに目覚めました。
<研究分野について>
経済成長のために市場競争を促進させるべきという意見が新聞やニュースで聞かれたりしますが、何が何でも競争が厳しければ良いという訳ではありません。
しかし一方で、近年はGAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)などにみられるIT巨大企業の市場寡占化の弊害も指摘されています。
どういった市場競争環境が望ましいのか?政府や中央銀行が行う経済政策は市場競争環境にどのように影響し、経済全体にどのようなインパクトを与えるのか?
マクロ経済学と産業組織論の理論を結びつけて、企業間の競争関係をうまく描写しながら研究しています。
また今後は、地域間格差の問題など地理的なトピックへの応用をしていきたいと考えています。
<学生へのメッセージ>
幅広い視点で周囲の意見を参考にしつつ、しかし周囲の意見ばかりに流されず、自分で調べて、自分で考えるスタンスを身につけてほしいと思います。
<略歴等>
◆学歴、学位、経歴
大阪大学大学院経済学研究科博士課程修了 博士(経済学)
◆専門分野
マクロ経済学・経済成長論・産業組織論
◆主な担当科目
経済政策
◆主な研究活動
"Asset Bubbles and Economic Growth under Endogenous Market Structure'', Macroeconomic Dynamics, Vol.23, issue 63, pp.2338-2359, 2019.
"Mixed Duopoly: Differential Game Approach'' (with Koichi Futagami and Toshihiro Matsumura), Journal of Public Economic Theory, Vol.21, issue 4,pp.771-793, 2019.