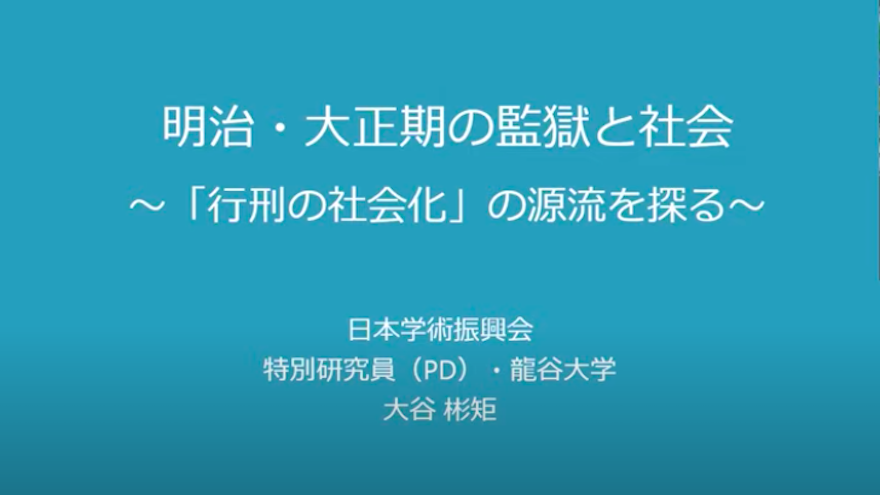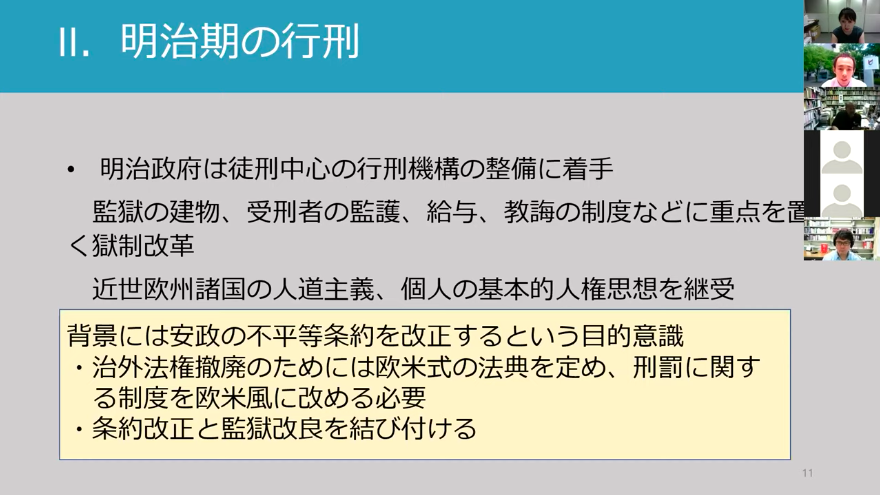地域の飲食店と連携した学生への食支援~地域経済の活性化に寄与する取り組みをPBL型実習として展開~
【本件のポイント】
・学生への食支援の取組に、地域経済の活性化、将来的な学生街の形成や地域社会と協働した大学づくりの視点を追加
・学生への食支援の取組をPBL(Project Based Learning)型実習としても位置付け、身近な社会問題を体験的に学ぶ
【本件の概要】
本学では、コロナ禍において一人暮らしの学生や留学生の窮状を踏まえ、5/2から学生への食生活の支援を継続的に行ってきました。この食支援プロジェクトでは、環境変化を踏まえて「緊急食支援」「自立支援」「総合支援」と段階的に支援策を講じ、学生食支援を通じて本学の将来計画「龍谷大学基本構想400」でめざす「価値創造」や「まごころ〜Magokoro〜ある市民の育成」を実践してきました。その学生食支援の最終段階として、コロナ禍で日常生活に困窮する学生だけでなく、経済的なダメージを受けた飲食店にも視野を広げ、学生への食支援、地域経済の活性化、将来的な学生街の形成や地域社会と協働した大学づくりをめざし、下記の取組を行います。
なお、短期大学部社会福祉学科の実習が大学の食支援プロジェクトと連携して本取組を実施しており、コロナ禍の人々の生活に及ぼす影響を学生の立場、地域社会の状況など、複眼的な視点から学びます。
(参考)https://www.ryukoku.ac.jp/ma556_5en/fproject.html
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-5927.html
1.事業内容:
学生・地域応援食事クーポン(1枚250円、一人につき2回まで使用可)を使用した学生への食支援と地域飲食店(地域経済)の活性化。
2.クーポンの使用方法:
深草学舎近隣の提携飲食店でクーポンを渡すと食事代が250円値引きされます。
3.有効期間:
2020年8月1日(土)~2020年8月31日(月)
4.配布場所および配布日時:
・深草キャンパス21号館1階特設会場:8月6日(木)、7日(金)【12:00~13:00の時間帯】
※7月30日(木)、31日(金)8月1日(土)、3日(月)、4日(火)、5日(水)にも配布
5.その他
飲酒の費用にクーポンは利用できません。あくまでも、日常の食生活を支援することが目的です。
問い合わせ先 : 短期大学部教授 阪口春彦
Tel 075-645-7897
Mail antonkun@human.ryukoku.ac.jp