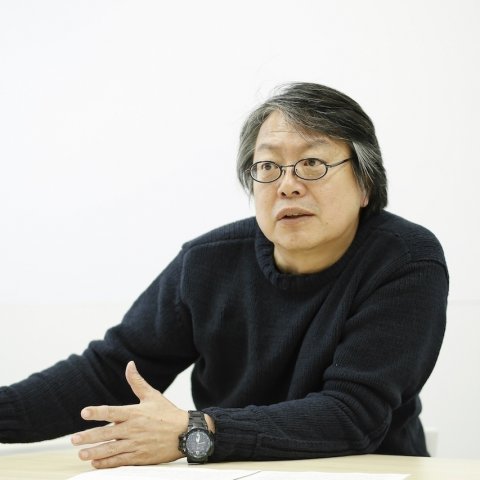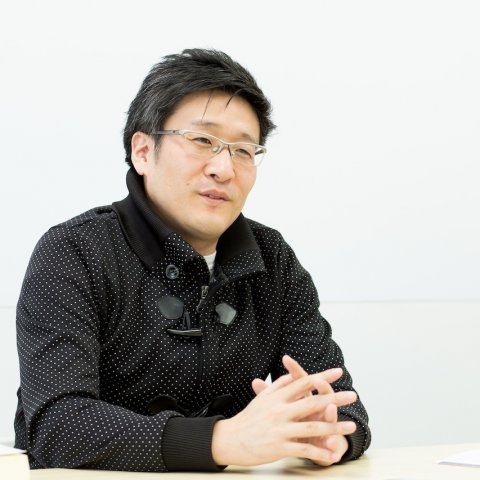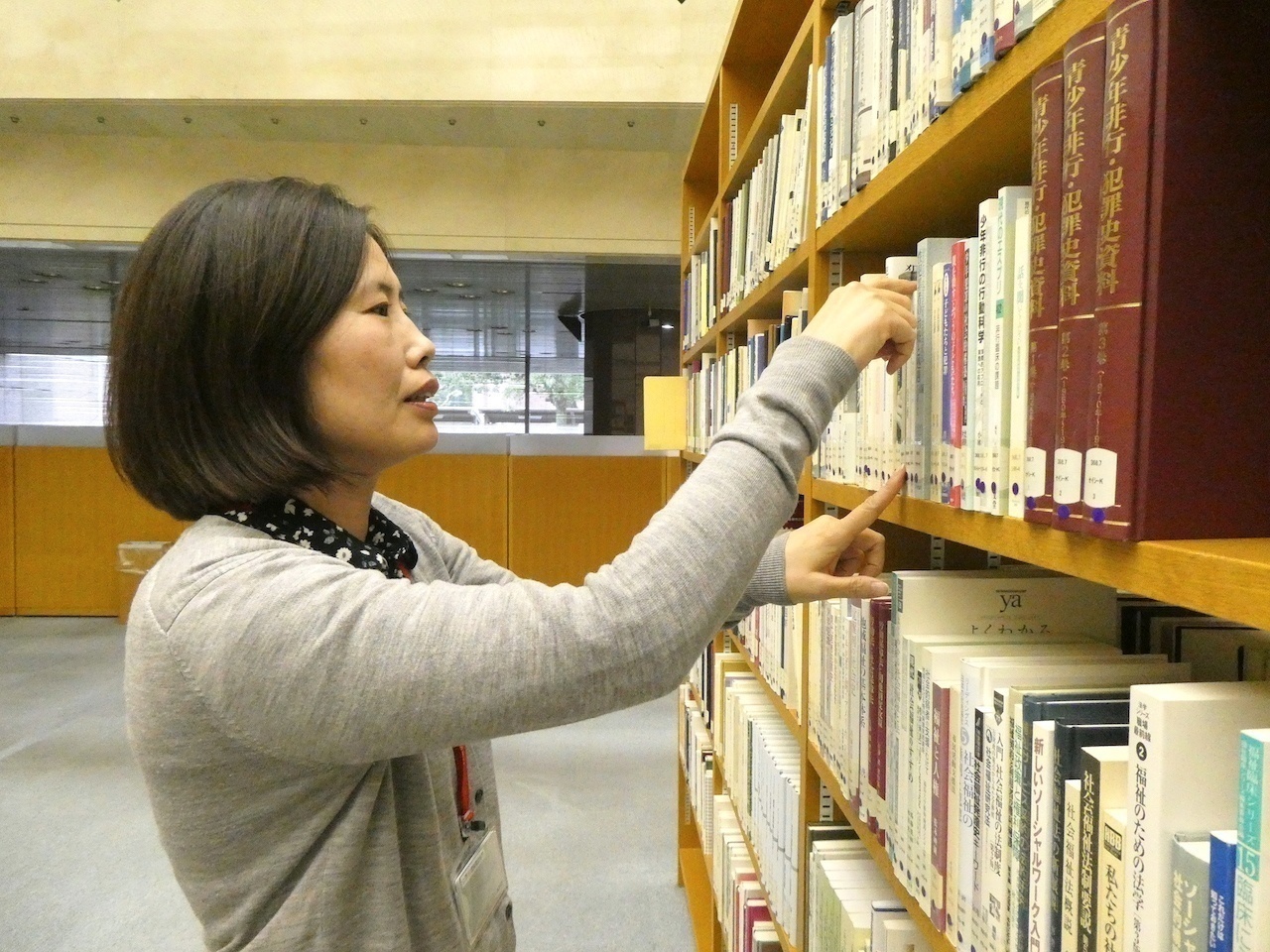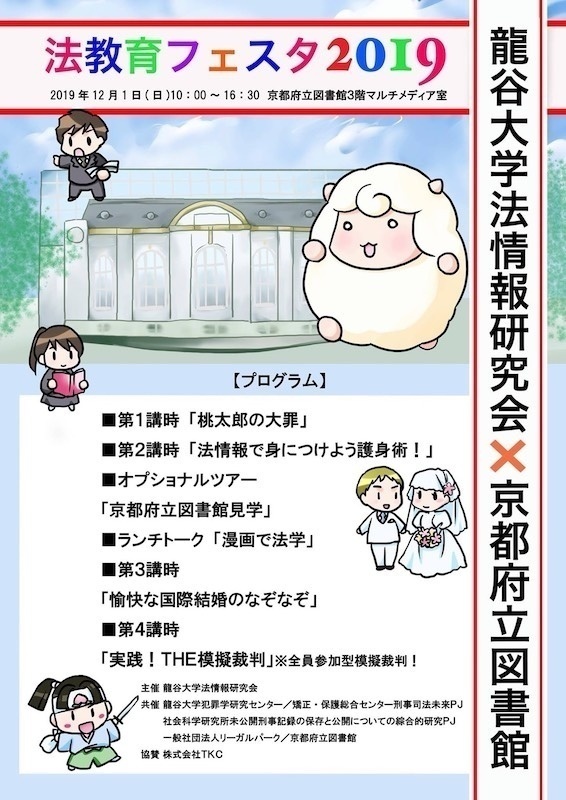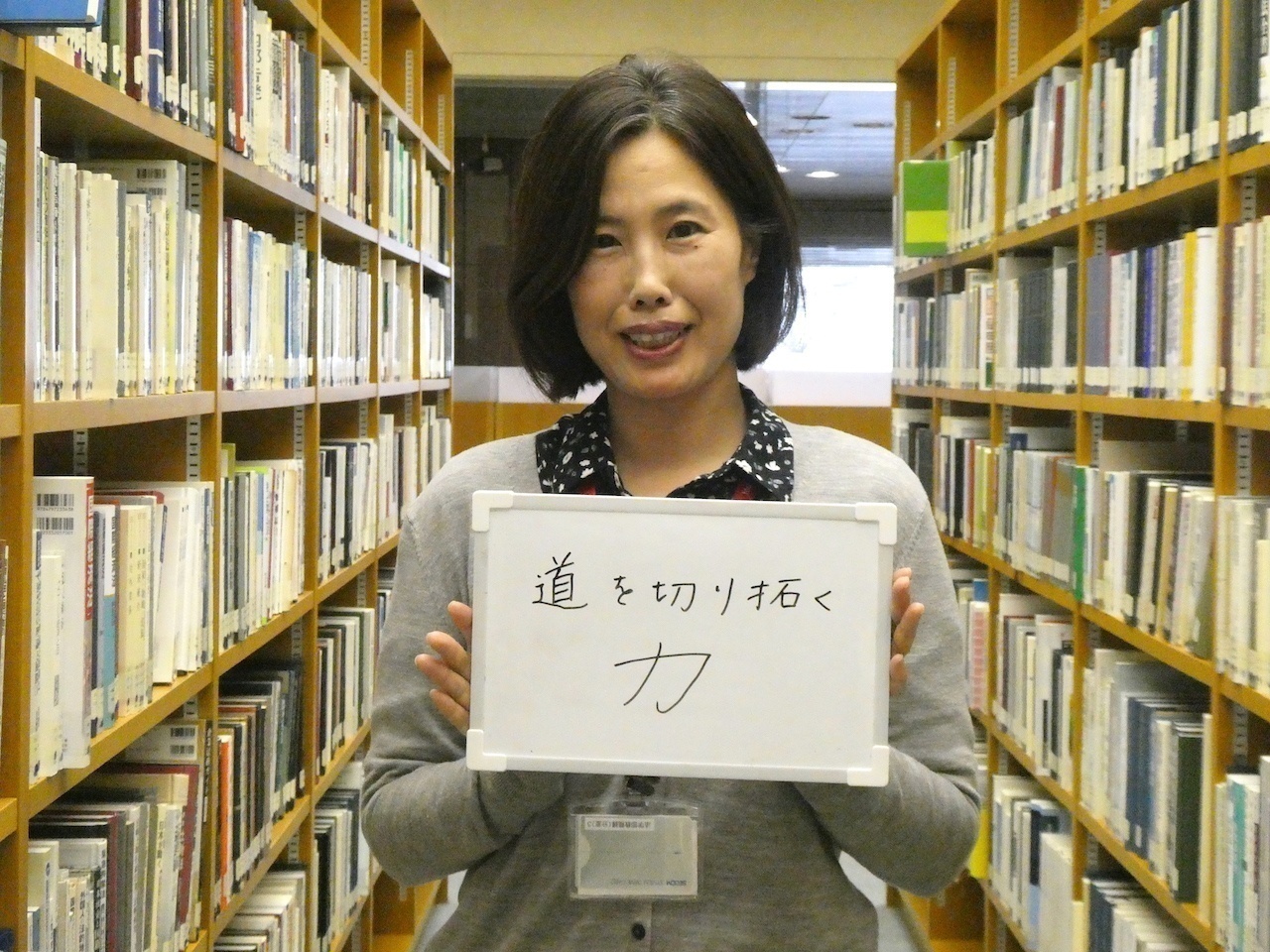【ご案内】東ドイツ映画×音楽 上映イベントを開催致します【社会学部学会】
ベルリンの壁崩壊から30年、社会学部学会では、ドイツ映画音楽界の巨匠、ペーター・ゴットハルト氏を招聘し、11月下旬から12月上旬にかけて龍谷大と出町座で映画のイベントをおこないます。
ゴットハルト氏は、500本以上のドイツ映画にたずさわり、非東ドイツ映画音楽の2018年にはドイツ映画音楽賞を受賞。近年は無声映画の伴奏家としてもベルリンで活躍しています。
上映イベントは3回に渡り、関西で活躍する弁士や楽士とのコラボも予定しております。またとない機会、ぜひお越しください。
【イベント概要】
○弁士×生演奏:無声映画の金字塔『メトロポリス』上映会
日時:11月29日(金)18時30分~
会場:龍谷大学深草キャンパス3号館201教室 入場無料(予約不要)
内容:『メトロポリス』上映会――サイレント映画×弁士×生演奏
(前半:ピアノの生演奏、後半:弁士の語りとピアノの生演奏)
出演:ペーター・ゴットハルト(映画音楽作曲家、ピアニスト)、
大森くみこ(弁士)、鳥飼りょう(楽士)
主催:龍谷大学社会学部学会
○東ドイツ映画『パウルとパウラの伝説』上映+作曲家トーク
日時:12月4日(水)19時開演、上映後トークショー
会場:出町座(京都市左京区)https://demachiza.com/
内容:東ドイツ映画『パウルとパウラの伝説』上映会+トークショー
(登壇:ペーター・ゴットハルト、聞き手:高岡 智子)
主催:龍谷大学社会学部学会
特別共催:DEFA財団
○国際シンポ「伴奏譜が語る1920年代ドイツ無声映画」
講演:ペーター・ゴットハルト(映画音楽作曲家、ピアニスト)
コメンテーター:白井史人(名古屋外国語大学)
高岡智子(龍谷大学)
日時:2019年12月1日(日)14時~16時30分
会場:龍谷大学深草キャンパス3号館102教室 入場無料(予約不要)
主催:日本音楽学会西日本支部、龍谷大学社会学部学会