学長法話(深草学舎)
■11月20日(水) 8:30~9:00
学長法話 学長 入澤 崇 先生
深草学舎 顕真館
8:30からのお勤めに引き続き学長法話がございます。
どなたさまも、ご自由にご参加ください。
ここにメッセージを入れることができます。

第4回公開研究会「性暴力・セクシュアルハラスメントを考えるために――性暴力の顕在化・概念化・犯罪化」
【企画趣旨】 研究、法実務、教育、当事者支援、報道の各分野で性暴力の...

読売新聞・大学特集シリーズ企画「大学SELECTION」に学長および学生のインタビュー情報を掲載
読売新聞の大学特集として、受験生や保護者、高校教員などに、大学での...
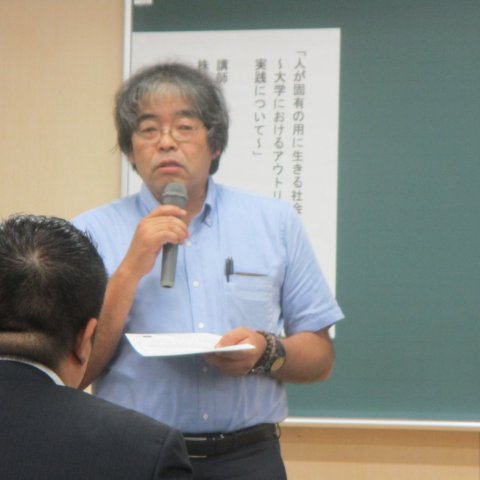
「障がい学生支援に関する教職員向け研修会」を開催 【キャリアセンター・障がい学生支援室】
「障がいのある学生のキャリア形成について~大学・企業・市民はどう応...
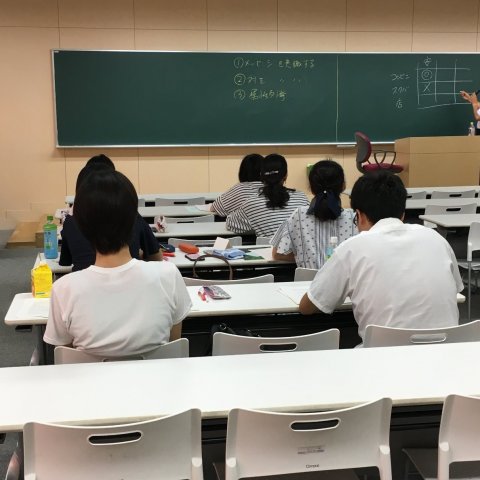
7月21日(土)猛暑の中、短期大学部卒業生・在学生向けの社会福祉士受験...

2018年7月20日(金)、農学部食品栄養学科の実習科目「食品加工学実習...

東京開催講演会「ドイツにおけるネオナチ組織による連続殺人事件裁判とヘイトクライム」【犯罪学研究センター】
・事前申込不要 ・参加費不要 ・逐次通訳あり [概要] ドイツにおいて、...
■11月20日(水) 8:30~9:00
学長法話 学長 入澤 崇 先生
深草学舎 顕真館
8:30からのお勤めに引き続き学長法話がございます。
どなたさまも、ご自由にご参加ください。
11月15日(金) 12:00~13:00
お逮夜法要
チャイを待ちわびて
本学非常勤講師 打本 和音 先生
深草学舎 顕真館
2019年11月4日、「2019年度第3回 龍谷大学法情報研究会」を本学深草キャンパス 紫光館で開催し、約20名が参加しました。
【イベント概要>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-4333.html
法情報研究会は、犯罪学研究センターの「法教育・法情報ユニット」メンバーが開催しているもので、法情報の研究(法令・判例・文献等の情報データベースの開発・評価)と、法学教育における法情報の活用と教育効果に関する研究を行なっています。
今回は、同研究会メンバーが取り組む4つのプロジェクトについて報告がありました。
はじめに、札埜 和男准教授(岡山理科大学 教育学部)が「札埜プロジェクト(法教育無料出張授業)」の現状について報告しました。
法教育無料出張授業では、模擬裁判授業に関わる全国の中学校・高等学校の教員・生徒への指導、法教育全般に関わる教員・生徒へのディープアクティブ・ラーニング指導、高校生模擬裁判選手権の指導を行っています。今年度は「高校生模擬裁判選手権」に初参加した創志学園高等学校(岡山)への支援及び指導・授業実践を行ったほか、岐阜県立関高校・仁川学院高校(兵庫)での小説「羅城門」模擬裁判、福祉型大学「カレッジ旭川荘」での八幡・龍谷モデルでの主権者授業を実施してきました。さらに、現在指導にあたっている千葉県立千葉東高校では小説「高瀬舟」を題材に模擬裁判を行う予定であるとのことでした。
【EVENT Link>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-4386.html
こうした指導を通じて札埜氏は「メモをとる、フィードバックを行う、語彙や言葉にこだわるといった“身体化した学びの習慣”は、必ずや生きていくための土台になる。模擬裁判を通じて、多様な大人から講評を受けるといった“論理のシャワー”を浴びる重要性、検察官や弁護人など役にそった演技を通じて“論理を体感”する必要性を伝えていきたい」と述べました。
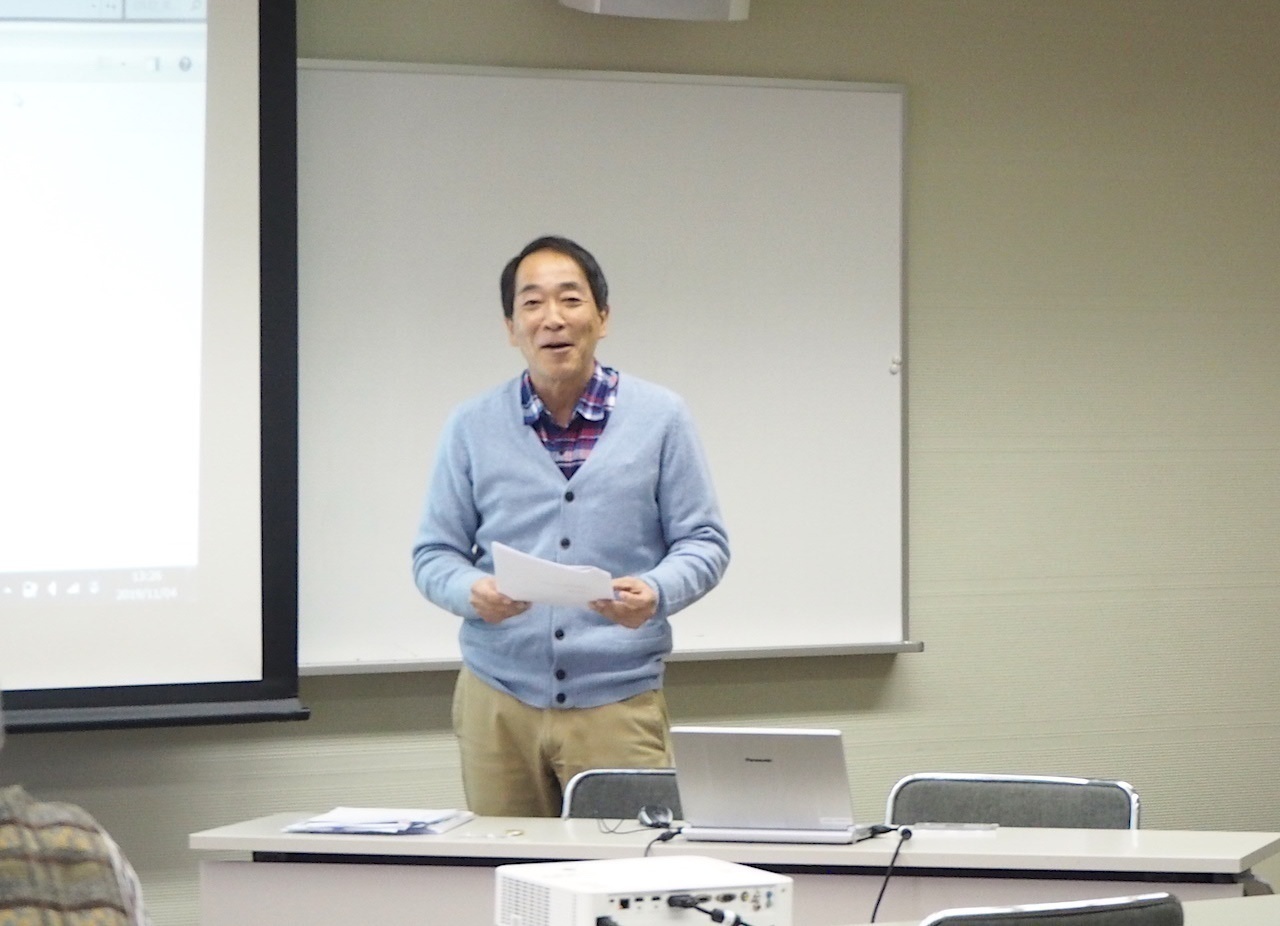
札埜 和男准教授(岡山理科大学 教育学部)
また、千葉東高校では現代文の授業の一環として取り組んでいます。小説『高瀬舟』を法というモノサシを使って「人間」を深く見つめ、「社会」を広く考えるもので、単なる刑事模擬裁判を超えた「哲学的」授業の実践になっているとのこと。札埜氏は「国語は人間というものを考える授業。小説であるがゆえに自由な発想ができるので、今後も文学の名作をシナリオ化する“文学法廷”のシリーズ化を検討していきたい」と展望を述べました。
つづいて、前回の法情報研究会でも報告が行われた龍谷大学社会科学研究所 研究プロジェクト「未公開刑事記録の保存と公開についての綜合的研究~4大逆事件関連記録の発見を端緒として~」の3つの研究ユニットのうち「確定記録ユニット」の研究活動について、福島 至教授(本学法学部)が発表しました。
【2019年度第2回 法情報研究会レポート>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-3620.html
「確定記録ユニット」で取り組んでいるのは、訴訟記録の保管・保存・公開に関する研究です。刑が確定した裁判の記録は原則公開される法律(刑事確定訴訟記録法)*1があるにも関わらず、実際には事件関係者以外からの閲覧請求は、原則不許可とされる傾向が強くなっているようです。また、刑事確定訴訟記録の中でも重要な訴訟記録と判断されるものは、法務大臣の定めにより「刑事参考記録」として特別に扱われていますが、その保存・保管・閲覧に関しての基準は不透明です。しかしながら、検察官が刑事確定訴訟記録を保管しておかなければならない期間は、法で細かく定められており、保管期間満了後の記録は、通常は廃棄されることになっているのです。
学術研究上価値のあるものは国民の知的財産でもあります。こうした現状から福島教授は「今後は訴訟記録の保存から公文書館での保管に結びつける研究活動に力を入れる予定だ」と抱負を述べました。

福島 至教授(本学法学部)
ついで、中村 有利子氏(法学部教務課ローライブラリアン)が12月1日に京都府立図書館と協力して開催する「法教育フェスタ」の企画状況を報告しました。
龍谷大学法情報研究会と京都府立図書館との共同企画として、2019年12月1日(日)に一般の方に向けた「法教育フェスタ2019 in 京都府立図書館」を計画しています。子どもから大人までの誰もが、日本昔ばなしやマンガ、国際結婚など、多様な観点から法学への理解をすすめることを目的とした催しです。紅葉シーズンで京都・岡崎エリアが一層賑わう季節、お散歩がてらぜひ気軽に参加してみてください。
【EVENT Link>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-4382.html
さいごに、大橋 鉄雄氏(フリーエディター)が「法情報研究会・東京部会」の活動報告を行いました。今年は、2009年5月に裁判員制度が導入されて10年の節目にあたります。今年に入って裁判員制度の10年を総括する動きがいろいろありましたが、報道に焦点を当てたものはありませんでした。そこで、龍谷大学法情報研究会が8月31日に公開シンポジウム「裁判員裁判と情報、報道のあり方を考える―裁判員制度10年を契機に」を東京で主催し、新聞記者やテレビメディア関係者を招いて、裁判員制度の課題について報道に焦点をあてた検討を行いました。
【EVENT Link>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-3950.html
もともと裁判員制度の設計に関する議論の段階では、犯罪報道が裁判員の判断に影響を与えるのではないかと問題視されていました。これに加えて、8月のシンポジウムでは、制度10年を振り返る中で裁判員の守秘義務の意義が問題点として挙がりました。
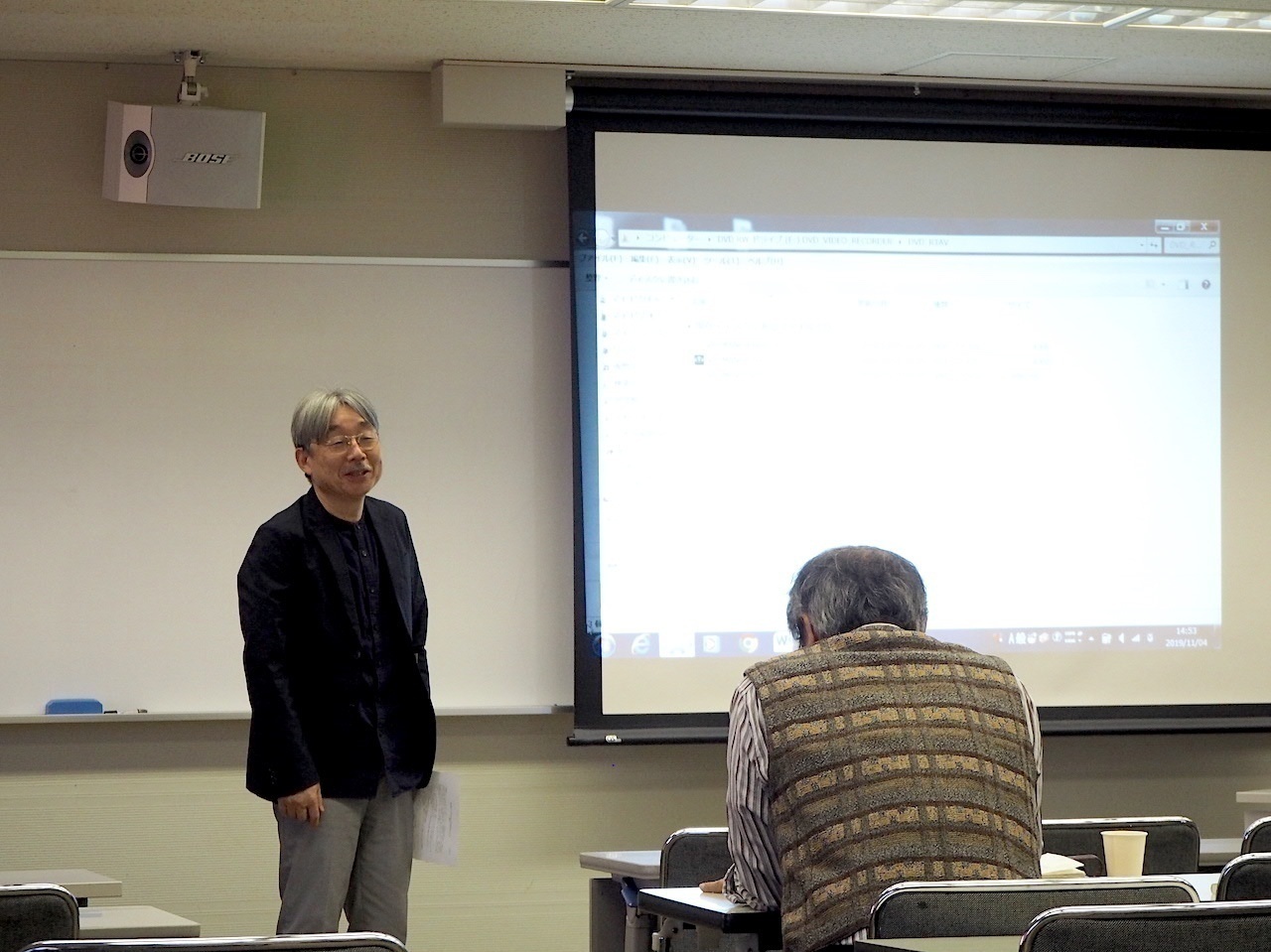
大橋 鉄雄氏(フリーエディター)
大橋氏は、現時点で総括することは難しいと前置きした上で「2008年に日本新聞協会や日本民間放送連盟が策定した“報道指針”*2は、国民の知る権利に基づく報道の自由と、市民(=裁判員)に予断を与えないようにとの裁判所側の要請との落とし所としてスタートしたが、形式面での自主規制がある程度定着する一方、指針の意味が必ずしも深められていない。また、裁判所側では“裁判員の負担”や“被害者のプライバシー”を理由に、裁判全体にわたって制度開始前よりも様々な局面で公開度を逆に下げてきているという指摘がある。この点について批判的な検討が必要ではないか」と問題点を明らかにしました。
大橋氏の発表を受け、参加メンバーの村井 敏邦 名誉教授(龍谷大学法学部)から「昨今は、マスメディアでは報道されない事件の情報についてもSNSで拡散されることが多い。メディア自体の領域が拡大しつつある現在、マスメディア同様に規制が必要なのかどうか。 情報公開の在り方について真剣に考えなければならないのではないか」とコメントがありました。
メディア環境が変化する中、裁判員制度をよりよいものにしていくために報道機関・メディアが果たす役割とは何か、取り扱われる報道・情報はどうあるべきかについて、12月7日(土)に東京で第2回目の公開シンポジウムを予定しています。本テーマに興味のある方はぜひふるってご参加ください。
【EVENT Link>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-4381.html
──────────────────────────
【補注】
*1 「刑事確定訴訟記録法」:
刑事訴訟法53条1項は「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」と定めており、この規定によって、誰もが確定した刑事事件の訴訟記録を閲覧する権利がある。しかし、刑事事件が終結した後、訴訟記録をどの役所が保管するのか、また閲覧手続きをどうするのかなど何も規定されていなかったことから、のちに「刑事確定訴訟記録法」が成立し、保管場所を当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官とした。
【詳細>>】2018/4/4「刑事裁判記録は誰のものか」(NHK視点・論点)
*2「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」:
2009年5月21日に日本で開始された裁判員制度では推定無罪の原則から裁判員候補者に予断を与えない報道が求められており、日本新聞協会や日本民間放送連盟は犯人視報道をしないという指針を発表している。
【詳細>>】日本新聞協会「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」
【詳細>>】日本民間放送連盟「裁判員制度下における事件報道について」
2019年10月31日(木)の「調理学実習Ⅱ」では水産仲卸組合の方々を講師としてお招きし「魚さばき教室」を実施しました。
大きなブリが瞬く間に刺身に調理され、その様子を目の当たりにした学生たちからは大きな感嘆の声があがっていました。
その後、学生たちは各班に分かれて、サバ、アジ、イカを実際にさばく実習を行いました。慣れない手つきで悪戦苦闘するなか、本組合の方々からは「包丁の根元から先まで使って」「骨に沿って包丁を入れて」と丁寧に指導いただき、最終的にはおいしそうな刺身や塩焼きに仕上がりました。
「魚さばき教室」での学習を通して、学生たちからは「教えてもらったことをぜひ自宅でもやってみたい」「今まで以上に魚のことを知りたくなった」などの感想が聞かれ、貴重な経験となりました。



日本を代表する航空会社の日本航空株式会社(JAL)代表取締役副社長執行役員の藤田直志氏をお招きし、「航空会社の目指す未来」と題してご講演頂きました。
講演の中では、「観光立国を目指す日本」「観光を支えるツーリズム産業」「航空会社の役割」「日本航空について」「社会人としての生き方」の5つに関して、日本や世界の現状を踏まえながら、これからの観光・航空業界の使命や役割、そして、働くということへの考え方や価値観等をJALグループの事例を通してお話頂きました。特にJALグループの企業理念やJALフィロソフィのお話は、いずれは大学を卒業し、社会人として進んでいく本学学生達にとって、人として、社会人として、どう仕事に向き合っていくべきかを教えて頂いた、とても素晴らしい機会となりました。
また、質疑応答では、「今後ITやAIが進化していく中で人とロボットの住み分けをどのように日本航空として考えておられますか。」や「国内のインフラとして新幹線が前進していく中で飛行機の役割をどうお考えですか。」等、観光や航空業界に興味をもっている学生からの質問に関して、日本航空としての取り組みをご紹介頂き、講演会後も多くの学生からの質問に対して、一人一人丁寧にご対応頂きました。
なお、本講演会の第2弾として日本航空株式会社の採用担当者の方による講演会を12月18日(水)に実施予定です!