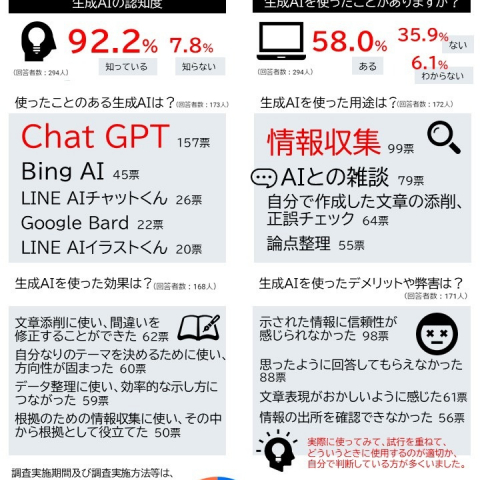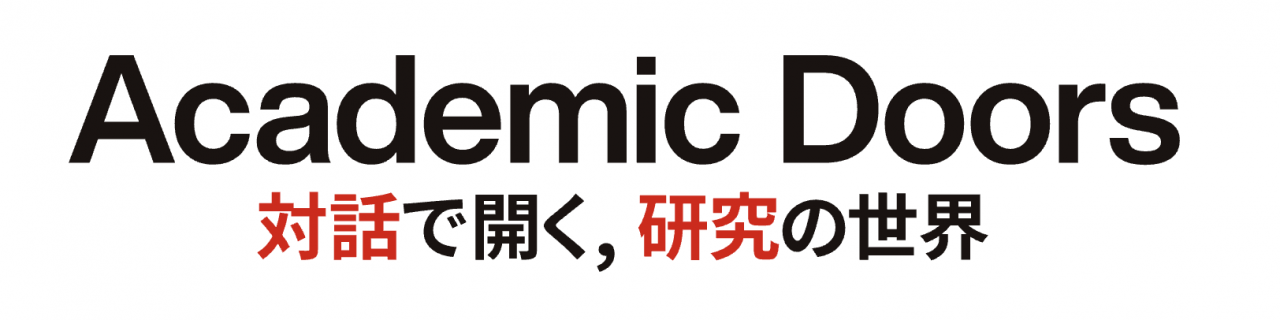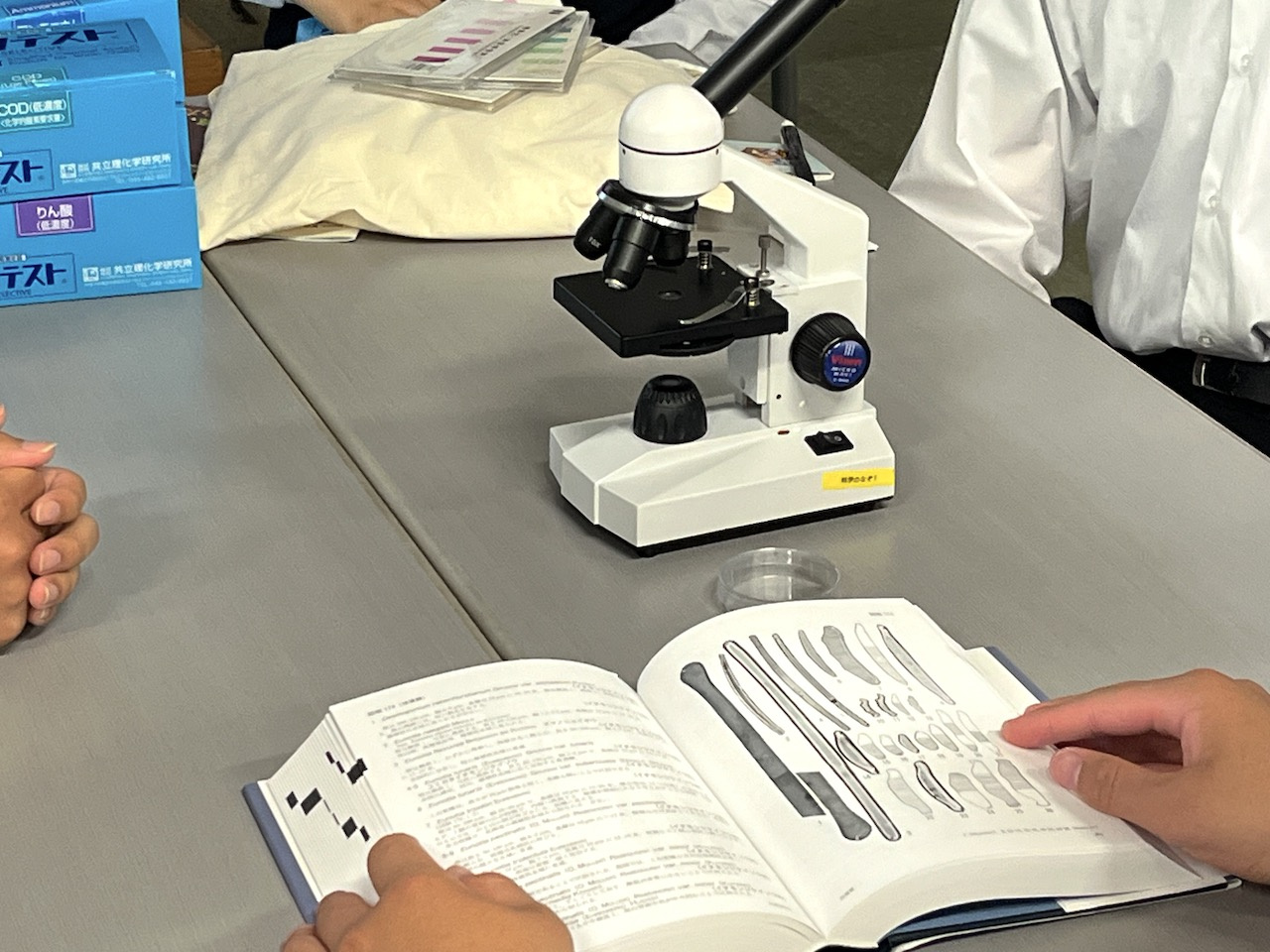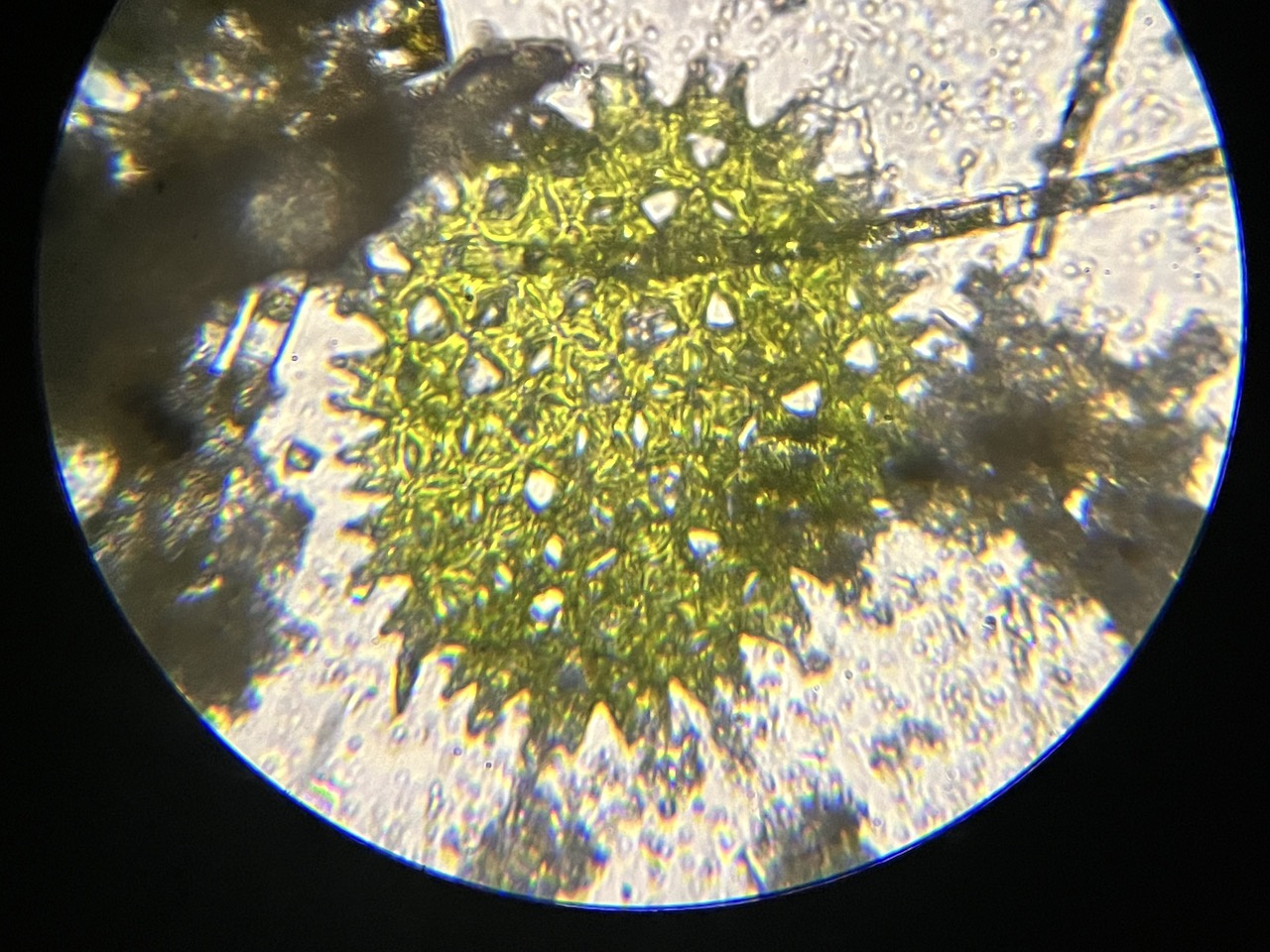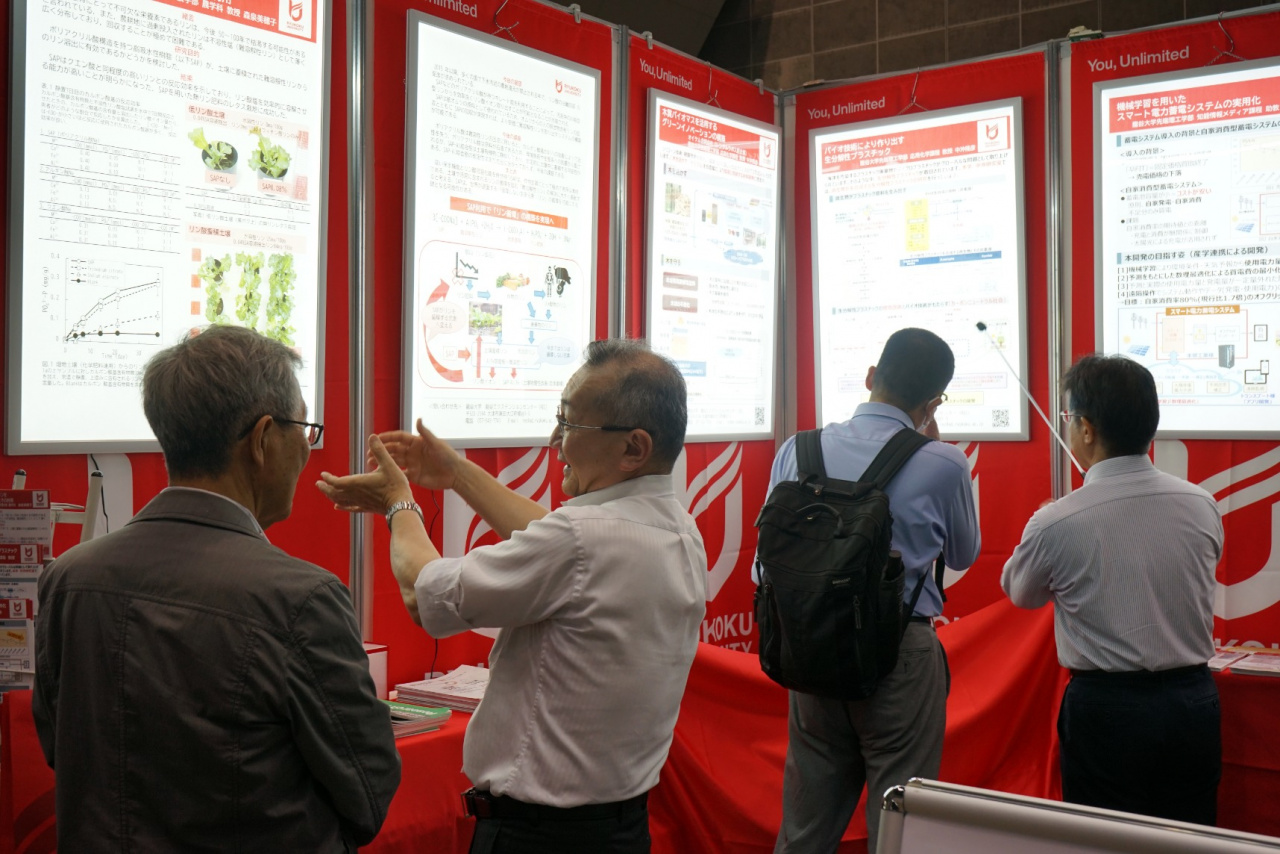教育領域・医療領域での心理職のリアルを聞く「キャリアと心理」【心理学部】

心理学部1年生対象のキャリア啓発科目「キャリアと心理」では、大学での学びを卒業後の進路選択や職業選択、長期的な人生設計に役立てられるように、講義やディスカッションを通して「自己のあり方」を考え、キャリアと心理学を繋いでいく機会を設けています。
2024年5月22日(水)の授業では、「教育領域と医療領域の心理職の仕事を知ること」をテーマに、櫃割 孝平 氏(スクールカウンセラー)、入江 優 氏(心療内科クリニック)にお越しいただき、ゲスト講義を実施しました。

講義では事前に学生から募集した質問や学生のリアルな感想や質問をとりあげて、対話形式で行われました。質問の中には、「カウンセラーの一日はどのような流れなのか」などの素朴なものから、「やりがい」や「失敗」などのリアルに触れる質問も寄せられました。
他にも、「心療内科では精神科医とどのように連携をとるのか」「カウンセリングでこちらが精神的に辛くなることはありますか?あるならどのように気持ちを切り替えているのか」「心理士として大切にしていることは何か」などの質問が寄せられ、ゲストのお二人から率直な意見を伺いました。

今回のゲスト講義を通し、特に印象に残ったのは 「カウンセリングにおいて精神的に辛くなることはあるのか」と言う質問に対してどちらとも「ない」と答えられていた事です。
カウンセラーは日々悩みを抱える人達の相手をしている職業ですが、一人一人の立場に入り込み、一喜一憂すると次のクライアントにもその悩みを引きずってしまうので、割り切ると言うことも大切なのだと気づきました。
今回、お話を聞いて実際に働いてみないと分からない体験談を聞くことで将来のビジョンが漠然としたものかもしれないが見えてきたと感じました。
教育領域や教育領域の具体的な話を聞くことができ、その道を志している龍大生にとっても、そうでない学生にとっても、とても有益な講義でした。
レポート執筆:篠川 倖(心理学部2年生:スチューデントチューター)