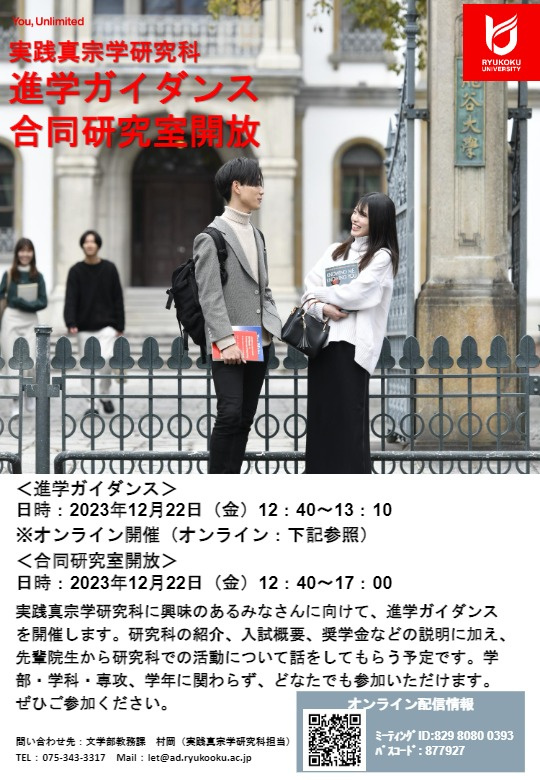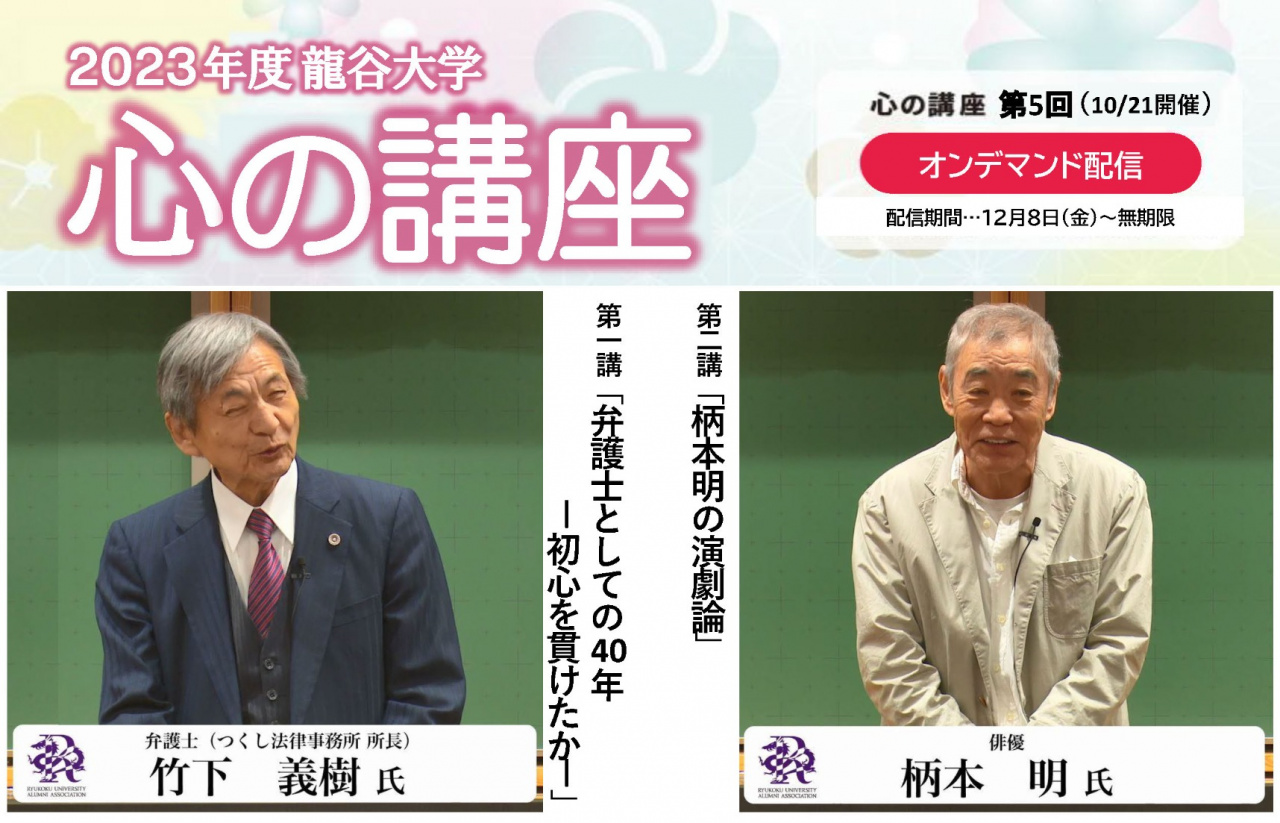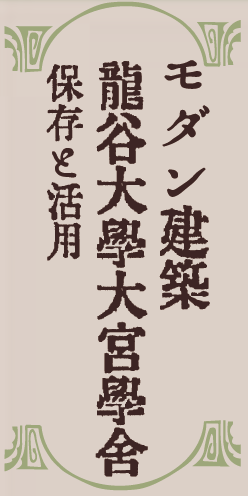実践真宗学研究科 進学ガイダンスの開催について(案内)【文学部】【実践真宗学研究科】
実践真宗学研究科への進学を検討している方を対象に、進学ガイダンスを下記の日程で開催します。
日々の研究や学生生活など、先輩方から直接お話を伺うことができます。
学部・学科・専攻、学年に関わらず、どなたでも参加いただけますので、ぜひご参加ください。
<進学ガイダンス>
日時:12月22日(金)12:40~13:10
※オンライン(Zoom)については下記URLからご参加ください。
https://us02web.zoom.us/j/82980800393?pwd=WFRzUW9NNWgzZUZmb1NudXhHSEpNZz09
ミーティング ID: 829 8080 0393
パスコード: 877927