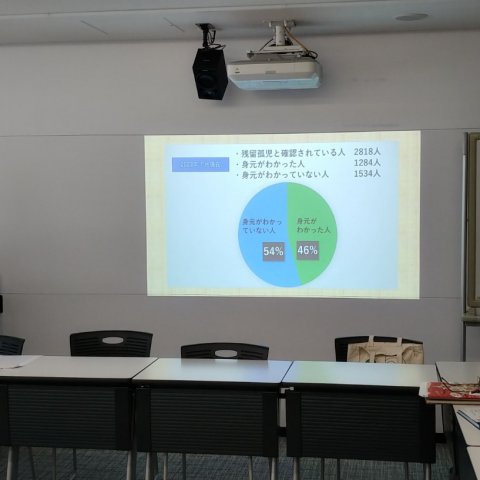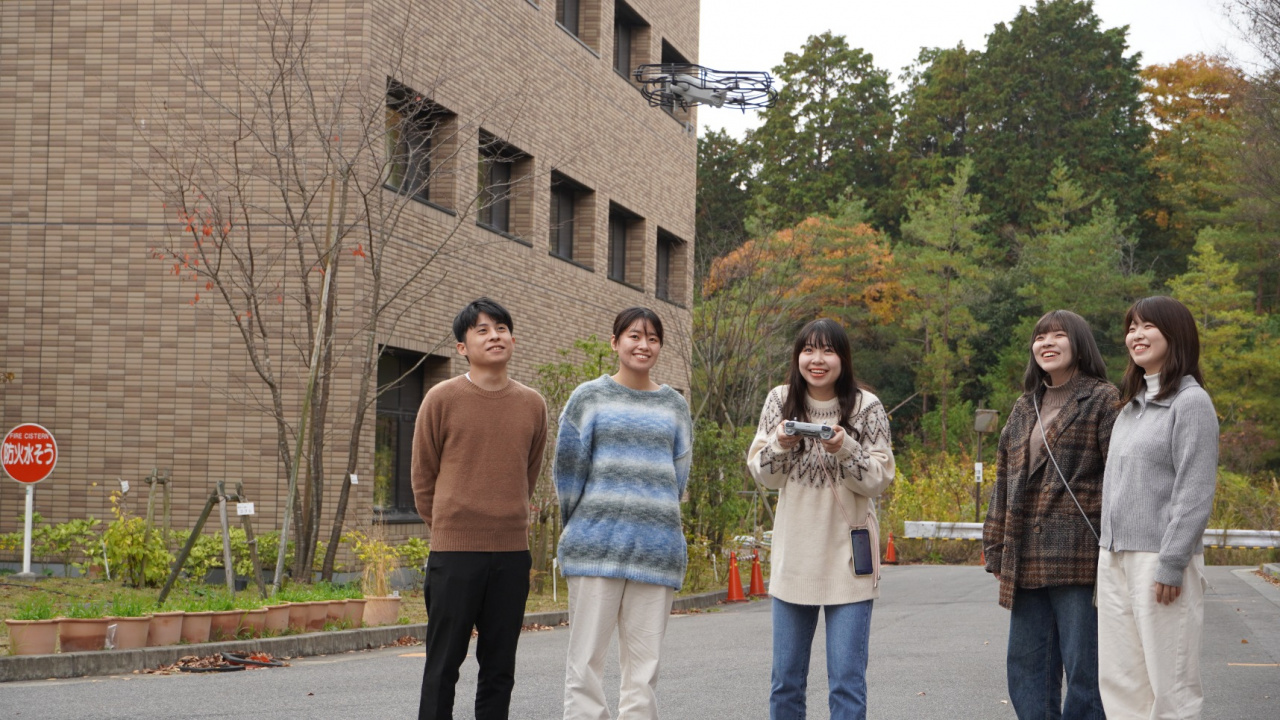障害者アートと文学作品のアート展を開催 交差するイメージ 文学とアート 龍谷大学大学院生がアートのイメージに合う文学作品を選定
【本件のポイント】
- 障害者アート作品のイメージに合う文学作品を文学研究科の学生が選定し、アート展を開催
- 文学と障害者アートのコラボレーションで新たな文学体験、アート体験を
- 明治12年築の重要文化財である大宮キャンパス本館を会場にし、12月に計6日間開催
【本件の概要】
龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターでは、あらゆる「壁」や「違い」を乗り越え、世界の平和に寄与するプラットフォームとなることを目指し、様々な事業を運営しています。
今回、文学と障害者アートをコラボレーションさせたアート展を開催します。国内外で高く評価される作品を生み出し続ける「やまなみ工房※1」(滋賀県)、日本の障害者アート活動を牽引してきた「たんぽぽの家※2」(奈良県)の作品を出展します。アート作品のイメージにマッチする文学作品を龍谷大学の大学院生(文学研究科生)が選び、アートと文学のイメージが交差していく企画です。
双方を同時に鑑賞することで、新たな文学体験、アート体験を楽しむことができる内容になっています。
開催日:12月11日(月)、13日(水)、15日(金)、18日(月)、20日(水)、22日(金)
時 間:10:30~17:30
場 所:龍谷大学大宮キャンパス本館1階展観室
企 画:松本拓(ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター客員研究員、本学非常勤講師)
主 催:龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター
(※1)やまなみ工房ホームページ:http://a-yamanami.jp/
(※2)たんぽぽの家ホームページ:https://tanpoponoye.org/
問い合わせ先:龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター(REC事務部(京都)内)
Tel 075-645-2098 ysbrc@ad.ryukoku.ac.jp https://ysbrc.ryukoku.ac.jp/index.php