Need Help?
Faculties
学部紹介環境を学ぶための多様なカリキュラム
コースの目的

20世紀、私たち人類は「物質的に豊かな生活」「高度な科学技術」「グローバル化した経済」の代償としてさまざまな形で「環境」を犠牲にしてきました。21世紀を迎え、私たちは直面している「環境問題」に真剣に取り組み、自然と人間社会の共生に努め、持続可能な社会を築かなければなりません。
環境サイエンスコースでは「エコロジー及び自然史」「社会科学」「哲学・倫理学および人文科学」の3つの視点から「環境問題」にアプローチし、フィールドワークを含む多面的な学習および総合的な研究をおこないます。
環境サイエンスコースの講義
本コースでは、コース生だけが受講できる、環境に関する様々なカテゴリーの講義を用意しています。これらを学ぶことで、環境問題に関する造詣を深めることができます。

「環境問題の基礎」を学ぶ
- 環境学A・環境学B
「地球の環境と生物多様性」を学ぶ
- 地球と環境・気候と気象・化学物質と環境・環境史
- 生態学A・生態学B・生物共棲論・水界生態論・自然保護論
「環境に関わる経済・行政・法・マネジメント」を学ぶ
- 環境政策論Ⅰ・環境と経済・環境管理論Ⅰ・環境管理論Ⅱ
「環境を考えるための様々な知識」を学ぶ
- 環境と倫理・地域環境論・環境地理学・環境アセスメント論
- コンピューターシステム論・シミュレーション技法・複雑系の科学
- 学部共通特別講義A「環境コミュニケーション」
- 学部共通特別講義B「GISの初歩:空間データで学ぶ環境情報リテラシー」
- 学部共通特別講義C「地域の自然と文化から考える持続可能な地域社会の創造」
「環境活動の理解と実践」および「環境研究」
- 環境フィールドワーク・環境実践研究・演習Ⅰ・演習Ⅱ・卒業研究
注)ここでは講義を5つのカテゴリーに分類していますが、実際の各講義は複数のカテゴリーの内容を含みます。またコースでは、上記以外にも各学部から提供される環境に関わる講義が用意されており、学部の垣根を超えて受講することができます。
環境フィールドワークの紹介
環境サイエンスコースでは、特色ある講義として「環境フィールドワーク」を開講しています。2021年度は「里山実習」「廃棄物関連施設視察」「竹林整備」「地熱資源視察」の実習を予定しており、環境に対する取り組みの現場を実際に見て体感することで、環境問題についての造詣を深めることができます。
里山実習
環境フィールドワーク「里山実習」では、里山をめぐる人々のくらしや里山の生き物について知ることを目的として、年4回「龍谷の森」とその周辺で野外実習を行っています。実習内容は、落葉かきと腐葉土作り・シイタケのほだ木つくり・低木伐採などの里山保全活動・里山の生き物観察などを行っています。この実習の特徴の1つは、市民ボランティアとの協働作業を通じた多世代交流です。参加した学生からは、「里山での伝統文化と持続可能な暮らしについて、実際に年配の方から話を聞けてよかった」「オオタカを生態系の頂点として「龍谷の森」には多くの生き物がいることが分かった」「龍谷大学にこんな本格的な森があるとは知らなかった」などの感想が寄せられています。

廃棄物関連施設調査
京都府環境保全公社・関連企業等を視察します。
企業の生産活動から排出される産業廃棄物リサイクル、処理の現場を視察し、その発生抑制、減量について考えましょう。



竹林整備
近年、里山に人の手が入らなくなり荒廃が著しくなっています。
本実習では京都府大山崎町の天王山において、放置竹林での竹の除伐を行い、山の手入れの方法を実践学習します。

地熱資源視察
大分県では観光資源としての温泉、エネルギー資源としての地熱など、地熱資源を様々な形で利用しています。これらの地熱資源利用の現場を視察し、再生可能エネルギーとしての地熱資源について考えます。また、日本でも有数の温泉観光地である別府温泉で、温泉利用が自然環境に与える負荷についての現状を学びます。この地熱資源視察では、別府温泉・大分県九重町の八丁原地熱発電所および周辺の火山の視察を予定しています。
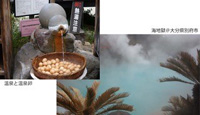
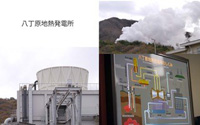
カリキュラムと履修の概要
コースでの学修について
卒業には学部ごとに卒業要件単位数が定められており、およそ70単位が学部専攻科目になっています。
コースでは、学部の専攻科目の代わりに48単位分を環境について学ぶことになります。
コースで学ぶ48単位は人文・社会科学系分野科目、自然科学系分野科目が配置されています。環境に対する十分な知識と理解を得るために両分野からの履修が望まれます。
また、環境という視点からのフィールドワーク(環境フィールドワーク)を設けています。積極的に参加することで、より実践的に学ぶことができます。
コース修了要件
環境サイエンスコースでは必修科目、選択必修科目、選択科目併せて48単位を修得する事が必要です。
【必修科目】・・・・(4単位)
「環境学A」2単位
「環境学B」2単位
【選択必修科目】・・・・(12単位)
選択必修A群(人文・社会科学系科目 7科目)環境と経済 環境とビジネス 環境政策論I など
選択必修B群(自然科学系科目 6科目)生態学 地球と環境 など
A群・B群から最低各4単位を履修し、合計12単位以上を修得すること
【選択科目】・・・・(32単位)
選択科目(演習含む)から合計32単位以上修得すること
環境史 環境アセスメント論 気候と気象 地域環境論 など
環境サイエンスコース 学生に保証する基本的な資質
■知識・理解
環境問題発生のメカニズムを文献と現場から理解し、それを解決するための環境学に関する知識を身につけている。
■思考・判断
環境問題解決のために主体的に行動でき、社会の持続可能な発展のための解決に向け思考することができる。
■興味・関心
自然の変化や人類に対する影響について関心を持っている。
■態度
自然と社会の持続可能性に向け、世代間のバランスや公平性を重視することができる。
■技能・表現
自然、社会、人文に関する幅広い知識を身につけている。
コース修了に必要とされる単位数及びコース修了認定の方法
- 所定の科目を履修しその単位を修得した者に対し、環境サイエンスコース運営委員会が修了を認定する。
- 修了認定を受けるためには、所定の48単位以上の単位数を必要とする。
教育課程編成・実施の方針
- 環境問題に関する基礎的知識を身につけさせるため、第4セメスターから、必修科目の「環境学」および人文・社会科学系と自然科学系科目からなる選択必修科目を開講する。
- 自然や社会に対する観察力と情報処理能力を身につけさせるため、「環境フィールドワーク」および「コンピュータシステム論」を開講する。
- 主体的な思考・行動力を身につけさせるため、第5セメスターから、学生が自ら企画し、さまざまな地域や組織で実習をおこない、その成果をレポートして取りまとめ単位認定を受ける「環境実践研究」を開講する。
- 環境問題の発生メカニズムを自然科学の視点から理解させるとともに、解決のための方策を社会の制度や倫理等の視点から考察させるよう、第4セメスターから始まる必修科目の「環境学」を開講する。
- 文献と現場実習から問題解決に向け考察できるよう、実習系科目(環境フィールドワーク、環境実践研究など)を選択科目として開講する。