Need Help?
Faculties
学部紹介開講演習(ゼミ)
担当教員の紹介

櫻井 次郎
専門:環境政策学
環境問題を解決するための取り組みについて知る・考える
一口に「環境問題」と言っても、大気汚染などの公害問題から地球温暖化や海洋プラスチックなどの地球環境問題、最近では原発事故による放射能汚染など多種多様です。そしてそれぞれの問題の解決方法について考える際には、問題発生の経緯、被害の大きさ、問題解決に要する技術やコストなどの諸要素を調べ考察することとなります。皆さんが、これら環境問題への取り組みについて理解を深め、知見を広めることは、卒業後に皆さんが社会人となってからも役立つと思われます。なぜなら、持続可能な社会に向けた取り組みは、国や地方自治体で進められているだけでなく、企業にも求められているからです。皆さんも一緒に環境政策について学んでみませんか?

谷垣 岳人
専門:進化生態学
身近な自然(動植物)から環境を考える
我々は生物多様性の恵みを受けながら日々暮らしています。しかし、世界中で生物多様性が減少しています。例えば、日本ではサンマ・ウナギなどの魚類が激減しています。生物多様性減少の原因は、乱獲・生息地の破壊・外来種の持ち込みなどの人間の活動です。では、どうすれば生物多様性を保全できるのでしょうか。本ゼミでは、里山や都市部での動植物の野外調査をおこない、自然を保護・保全するための市民・地方自治体・国の役割について考えます。
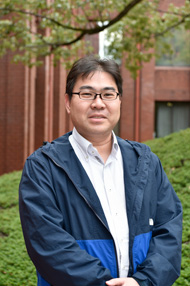
山田 誠
専門:地下水水文学・温泉科学
水を通して環境を考える ~人と水と自然のつながり~
我々の身近にある水と自然と人間がどのようにつながり、互いに関係しあっているのかを、フィールドワークや座学を通じて学びます。また、水資源に関わる調査や活動を通じて、地域における最適な水利用方法とは何か、について考えていきます。水は飲料水としてだけでなく、様々な用途で利用されています。人と水と自然のつながりを深く学び、水を利用するすべての人にとって最適な水利用のあり方について一緒に考えていきます。

丹野 研一
専門:考古植物学、遺伝育種学
昔の食糧を知り、今の食糧を変える ~古代小麦の考古学と現代的利用~
人類の農耕は、約1万年前に西アジアにおいて野生の小麦類が栽培化されたことから始まりました。当時の農耕の具体像を解明するための考古植物学という研究手法を、本ゼミでは紹介します。さらに実践研究として、古代小麦(つまり皮性小麦種)を現代品種と交配して新品種を育成しているので、これを世に出すための品種改良の調査等を行います。年に2、3回ほど農学部の牧農場で農作業を行います。本ゼミでは植物や農業、食物、食の歴史について考えます。
2022年度開講演習
櫻井ゼミ
【テーマ】私たちの将来と環境政策について考える
現役の大学生で「3R」や「持続可能な発展」などの用語を「全く知らない」という人は、今や少ないと思います。しかし私が大学で教え始めたばかりのころ、これらの用語を知っている学生はごく少数でした。環境政策に関する知識は、今後ますます広く知られることになると思われます。その理由の一つは、グローバルな金融業界における意識の変化にあります。将来皆さんが務めるかもしれない会社にお金を貸す金融機関が、審査項目の一つとして環境問題への取り組みを挙げているからです。このような社会全体の流れの中、皆さんの将来と環境政策がどのように関わっているのか、考えてみる意義は少なくないと思いませんか?本ゼミでは、1年目の前半は環境政策のテキストをもとに基礎的な知識の定着を図り、後半はそれぞれの関心に沿った環境問題に関する発表をもとに考察を深めてもらいます。2年目には卒論執筆とそのための調査が求められます。ちなみに、演習担当者の専門は中国の環境政策で、特に環境問題にかかわる紛争や裁判について調べています。
【こんな人向け】
過去と現在の公害問題に関心のある人、地球規模の環境問題への取り組みに関心のある人、途上国における環境問題に関心のある人
演習ではテーマに関する意見を交換したり、調べたことを発表し合うことによって理解を深め、知識を広げて欲しいと思っています。積極的な参加を期待しています。
谷垣ゼミ
【テーマ】
身近な自然(生物)から環境について考える
【フィールドワーク】
伏見稲荷・本町通りツバメ調査・鴨川・龍谷の森・
自然を活かした地域活性化(京丹後市)
【これまで卒論テーマ】
- 京都市伏見区本町通りにおけるツバメの営巣状況
- ジビエ利用による鳥獣被害の軽減と地域活性化について
- 水田の特徴別にみたプランクトンの種数の比較
- 大阪市立大学理学部附属植物園における樹洞性鳥類の巣箱の利用状況とオオタカの営巣記録
- 交通事故対策から考える奈良公園のシカと人との共存関係
- 生物多様性米に関する意識調査〜消費者アンケートから見えた課題
【こんな人向け】
動物や植物に興味がある
本格的なフィールドワークをしたい
フィールドワークを主体とするゼミです。野外で動植物を観察し、そこから現代社会の課題について考察を深めます。
好奇心旺盛な学生を歓迎します。
 「龍谷の森」での鳥の巣箱作り
「龍谷の森」での鳥の巣箱作り 伏見稲荷本町通りでのツバメ調査
伏見稲荷本町通りでのツバメ調査山田ゼミ
【テーマ】
水を通して環境を考える 〜人と水と自然のつながり〜
【ゼミでの学び】
- 我々にとって身近で必要不可欠な水が、どうやって我々のもとにやってきて、どうやって我々のもとから去っていくのかを学びます。
- 野外における水環境の調査法を学びます。この学びを通じて、データに基づいた科学的思考について学びます。
- 水が運ぶ様々なものが周辺環境に与える影響について学びます。
- 水を資源として捉え、資源をどの様に利用し、保全していくかについて学びます。
- 水資源を、“水” の資源とだけ捉えるのではなく、別の資源にもなるという考え方について学びます。
【こんな人向け】
- 自然の水(温泉・地下水・川・湖・海など)に興味がある
- 地球科学(地学)や自然地理学に興味がある
- フィールドワーク(野外での活動)が好き
- 水環境データを使ったデータサイエンスに興味がある
【これまでの主な卒論テーマ】
- 小浜湾における海底湧水が沿岸域に与える熱的影響
- 環境水中の硝酸濃度及び溶存無機窒素の簡易測定法に関する研究
- 深草周辺の高硝酸イオン濃度地下水の水質形成機構
- 鴨川のマイクロプラスチックの実態
- 積雪から見る比叡山山頂付近の気候環境と経年変化について
- 湧水の水収支から見る比叡山山頂付近の水環境の変化
- 比叡山の山頂付近における湧水の水質形成機構
- 大分県別府市における河川への温泉排水流入が河口域の底生生物に与える影響
【教員の研究活動】
- 地下水を介した陸と海のつながりの解明:海底湧水の研究
- 大分県別府市の地下水(温泉)形成に関する研究
- 大分県別府市の温泉資源モニタリング:ステークホルダー協働による資源管理の実践
- 京都府内の湧水・地下水研究:地下水湧出機構に関する同位体水文学的研究
 京都市内の地下水調査
京都市内の地下水調査 小浜湾の海底湧水調査
小浜湾の海底湧水調査丹野ゼミ
【教員の研究分野】
1)現在とくに活動している研究としては、小麦の新品種を開発しています。本研究室では、古代系小麦(皮性小麦)の新品種を開発していますが、国内に古代系小麦の品種登録は本研究室の他に類例がありません。その一方で古代系小麦は、世界では安全な食糧を求めて、有機認証農作物をあつかう販売店などで希少品として取り扱われています。
本研究室では、スパゲッティなどパスタ用のデュラムコムギを古代エンマーコムギの系統から育成し、品種登録しました。また、パン用のスペルト小麦系の交配品種を現在作成中で、これを滋賀県と沖縄県で栽培・製パン加工する実地試験を行っているところです。日本の新しい「食」を本研究室から発信します。
2)人類の農耕の開始とその起源を、考古植物学によって調査しています。人類は約11,000年前頃に、西アジア地方(トルコ、シリア、イラク、イラン、パレスチナ、イスラエルなど)で農業を開始しました。考古学の発掘調査によって回収された土壌サンプルから、植物の生活残差(炭化物)を顕微鏡で調べています。農耕開始は従来考えられていたよりもゆっくり進行したことを、これまでに明らかにしています。
【こんな興味をもっている方、当ゼミにどうぞ】
- 植物(自然の植物や、野菜や花などの園芸植物)に興味がある
- 農業(栽培)に興味がある
- 食や食材に興味がある
- 遺跡から出土する植物(植物遺存体)に興味がある
- 動物や自然に興味がある
- 鳥獣害対策や竹林伐採など自然林復活に興味がある
 滋賀県の農家圃場での栽培試験風景
滋賀県の農家圃場での栽培試験風景 機械による播種
機械による播種※農学部の牧農場の一画を借りてます
 放置竹林を伐採して植生環境を整備しています(大山崎町天王山)
放置竹林を伐採して植生環境を整備しています(大山崎町天王山)