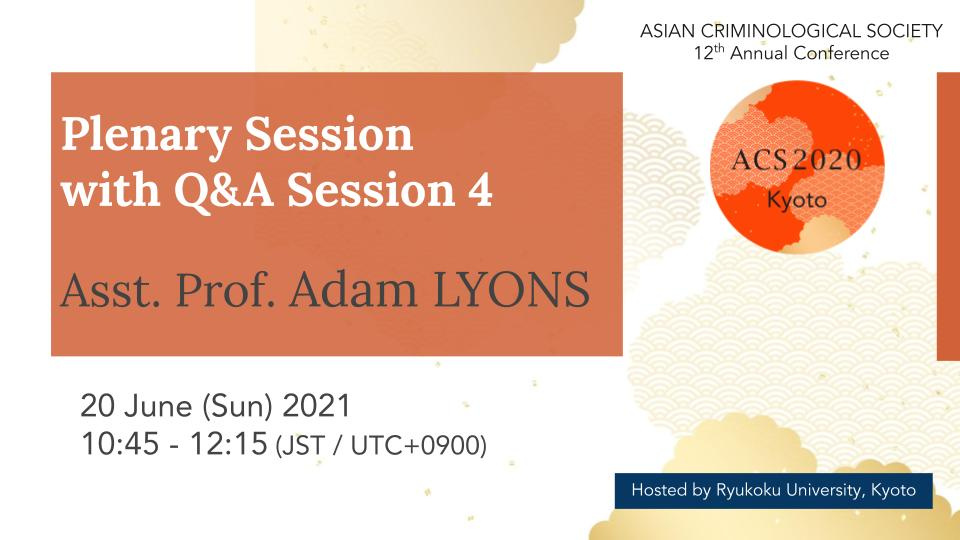龍谷大学がホスト校となり、2021年6月18日(金)〜21日(月)の4日間にわたり国際学会「アジア犯罪学会 第12回年次大会(Asian Criminological Society 12th Annual Conference, 通称: ACS2020)」*をオンラインで開催しました。2014年の大阪大会に次いで国内では2回目の開催となる今大会では、アジア・オセアニア地域における犯罪学の興隆と、米国・欧州などの犯罪学の先進地域との学術交流を目的としています。
大会の全体テーマには『アジア文化における罪と罰:犯罪学における伝統と進取の精神(Crime and Punishment under Asian Cultures: Tradition and Innovation in Criminology)』を掲げ、「世界で最も犯罪の少ない国」といわれる日本の犯罪・非行対策と社会制度・文化に対する理解を広めることを目指しました。
【>>関連ニュース】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-8690.html
LIVEで行われた本大会の全体講演(Plenary Session with Q&A Session)の概要を紹介します。
[PL04] 現代日本の刑事施設における教誨
(Prison Ministry in Contemporary Japan)
〔講演者〕アダム・ライオンズ(慶應大学 商学部 専任講師)
Adam Lyons (Assistant Professor of Faculty of Business and Commerce, Keio University, Japan)
〔司 会〕石塚伸一(龍谷大学 法学部 教授)
Shin-ichi ISHIZUKA (Professor, Faculty of Law, Ryukoku University, Japan)
〔日 時〕2021年6月20日(日) 10:45 -12:15
〔キーワード〕刑務所、教誨、教誨師(とその役割)、ジレンマ、「罪業(カルマ)」、犯罪=悪業(bad karma)、ボランティア、教会、仏教、死刑囚、死刑教誨師、フィールドワーク、「公」と「私」のディスコースのギャップ、「縁(karmic connection)」
【報告要旨】
日本は世界で最も世俗的な国の一つである。ところが、受刑者1人あたりの教誨師の数は、諸外国と比べても際立って多い。日本の教誨師の大半は仏教の僧侶である。今回の講演では、欧米の「スピリチュアルケア」としての教誨とは異なる、仏教の教義に基づいた日本独特の教誨のあり方について紹介したいと思う。
報告者は、近日中に学術書『罪業と刑罰:日本における刑務所教誨(Karma and Punishment: Prison Chaplaincy in Japan)』を出版の予定である。同書は、このテーマに関する文献調査、刑務所の実態調査、教誨師への聴取り調査などに基づいている。本講演では上記の調査結果に基づき、日本における仏教の近代化のもう一つの位相、すなわち、日本の宗教団体が犯罪との闘争による社会防衛という「生きる場所(niche)」を掘り起こしていたという新たな位相を白日のもとに晒してみたいと思っている。擁護者としてのニッチを切り開いていく中で発展した、仏教モダニズムの別の側面を明らかにしたいと思う。すなわち、明治維新(1868年)から現在(2021年)に至るまで間、何世代にもわたって聖職者が任命され、かつては違法とされたキリスト教の異端者からマルクス主義の政治的反体制派、さらには、戦争犯罪者や死刑囚に至るまで、さまざまな「犯罪者」に宗教的指導を行ってきた。刑務所における教誨は、現行憲法における信教の自由と宗教と国家の厳格な分離という公約にもかかわらず、国家主義が現代日本の宗教生活の主流を占めているという変わることのない特徴を示している。
報告は、まず、日本の教誨の歴史を外観し、制度上の基本原則および教誨の実施形態について紹介する。これらを踏まえ、現職・前職の教誨師へのインタビュー、死刑囚の教誨について報告して、私見をまとめることにした。
上記の内容の全体講演の後に参加者との質疑応答に入った。
【質疑応答(Q&A)要旨】
(問1)日本で死刑廃止運動をおこなうにあたり、刑事施設の教誨師は、もっと積極的な大きな役割を果たすべきだと思うか。もしそうであるならば、意味のある役割を果たすために必要なことは何か。
(答1)たしかに、日本で死刑廃止に取り組むにあたり、教誨師は手助け一助となるだろう。しかし、死刑廃止運動で教誨師が意味のある役割を果たすことは非常に難しい。教誨師が政治的な発言をすると、当局によって、被収容者との接触が禁止されてしまう可能性がある。ほとんどの教誨師は、被収容者に関わり続けるため、政治的な発言を控えている。その意味では、教誨師は大きなジレンマを抱えている。
(問2)映画「Deadman Walking」を観たが、シスター・プレジャンは、積極的に死刑問題について発言し、行動している。日本の教誨師は、何故そこまで、法的または政治的な言論や行動を控えているのか。
(答2)日本国憲法では厳格な政教分離が定められている。そのため、教誨師が死刑廃止活動に関われば、刑務所側は憲法上の原則に違反していると主張することになる。教誨師が政治活動に関われば、現実的に「道徳的救済」を求めている被収容者を見捨ててしまうことになる。堀川惠子『教誨師』(講談社、2014年)は、実在の死刑教誨師・渡邉普相へのインタビューに基づいているが、死刑教誨師がいかにストレスの多い仕事であるかを描いている。死刑教誨師の誰もが大きな負担を感じているだろう。
(問3)各宗派の公式なマニュアルと、実際の刑務所における教誨師の活動にはギャップがあるように思う。そのギャップを埋めるための取組みを知っていれば教えてほしい。
(答3)実際に現場でおこなっている活動を包括的に反映した新しいマニュアルを作成する組織的な動きは知らない。教誨師は、それぞれのやり方で活動している。
教化改善のための教育は、通常は善導のための教誨だと言われる。たとえば、「悪いことをすれば、悪いことが報いとして返ってくる。罪を犯したから、悪業の報いとして刑務所に収容される。悪業は、改心することによって解消される」。この伝統的かつ典型的な「業(カルマ)」のストーリーがある。しかし、報告で紹介した教誨師・深井三洋子は「知的障害のある人と関わることが多い」と語っていた。十分に学ぶ力がない人を指導するためには、型通りの教育刑モデルではうまく機能しない。教誨師は、社会のセーフティネットからこぼれ落ちた人たちにも親切に接することによって、塀の中で構造的問題を解決しようとしている。
(問4)被収容者は、刑事施設に収容されると、自らの信仰している宗教を公にしなければならないのか。
(答4)教誨師との面会は強制ではなく、被収容者から要望があったときにおこなわれる。「カウンセリングを受けたい」という理由で希望する人もいれば、「別のワークショップなどの時間と教誨師の活動が重なっていたから」など、被収容者によって面会を希望する理由はさまざまである。
なお、戦前は、受刑者には「宗教教誨」を受けることが義務付けられていた。教誨師は、全て東西の浄土真宗本願寺派の僧侶で公務員であった。日本の仏教は多様であり、さまざまな宗派があるが、伝統的な仏教の最大の宗派は浄土真宗である。多くの西洋人は、日本の仏教について「禅宗」のイメージを持っている。近代日本において最も政治的・文化的に影響力を持つ仏教宗派は浄土真宗であり、特に1900年頃から1945年までは、刑務所の教誨師を浄土真宗の本派本願寺派と大谷派が独占していた。
(問5)「縁(karmic connection)」について説明してほしい。
(答5)「カルマ(罪業)」の概念は西洋でもよく知られている。私の近刊のタイトルも「カルマと罰」だ。このタイトルは、ドストエフスキーの『罪と罰』を連想させると思う。「犯罪」と「カルマ」は似ているようにもみえるが、本の中では「カルマ」という概念を用いて、教誨師がどのようにしてこの2つの相反する任務を展開し、それが制度化されているのかを説明している。
教誨師は、公的文書などでは「カルマ」言説を用いている。しかし、私的な会話では「善い(あるいは悪い)業(カルマ)」や「因果応報」などの話よりも、「縁(karmic connection)」という表現がよく用いている。これは、狭義の上から下への一方的な押し付け(top-down)への抵抗と見ることもできる。西洋ではキリスト教教誨師は「こころのケア(spiritual care)」という言説をよく用いる。このような表現は、日本では公的には使われていないが、インタビューの中では「こころのケア」に近い言説が語られることもあった。日本の教誨師は、「こころのケア」のための独自の概念を持っていると考える。その意味もあって、著書のタイトルでは西洋の概念を使わず、日本の仏教に由来する「カルマ」という日本語を用いた。
(問6)キリスト教の教誨師は「業(カルマ)」の神学を否定しているのではないか。
(答6)現在の日本の刑務所においては、「カルマ」ストーリーを否定するような動きはみられない。日本においてキリスト教教誨師は、明治から昭和初期にかけていの一部の先駆者を除いて、一般的には戦後に入ってから登場した。キリスト教教誨師は「カルマ」の考えに基づいた教誨はしていないが、「縁(karmic connection)」の比喩を用いることはあるようだ。「縁」は宗教的というよりは、日常会話で使われるありふれた表現であるため、キリスト教教誨師も日常用語のひとつとして用いている。
(問7)日本では、今後も更生の一環として神学がおこなわれ続けるのだろうか。
(答7)たしかに、日本は、西洋と同じように、無宗教的な社会になりつつある。しかし、教誨師のプログラムは刑務所システムの一部として存在し続けている。2017年に発行された『教誨マニュアル』(教誨マニュアル編集委員会編)は、以前の版と同じように「業(カルマ)」や「浄化」「矯正」について書かれており、やや時代錯誤的ではある。しかし、日本でも「こころのケア」の言説が普及してきているため、教誨師もこの言説を使うようになり、神学が変化するのではないかと思われる。
日本の刑務所は高齢化が進んでいる。現実の刑務所は、社会的セーフティネットからこぼれ落ち、どこにも行くところがない人たちを多く受け入れている。「罪業(カルマ)」の教義に基づいて話をしても、あまり意味がない。実際に教誨師たちは、そのように語っている。
(問8)コロナ禍において教誨師活動はどうなっているのか。
(問8)教誨師の連盟に聞いたが、すべてが止まっているとそうだ。文通は引き続きおこなわれているが、対面の面会はおこなわれていない。感染リスクが高い高齢受刑者が多いことから、刑事施設側も制限しているようだ。
なお、下記のサイトを参考にしていただきたい。
<参考>
https://www.waterstones.com/book/karma-and-punishment/adam-j-lyons/9780674260153
https://www.amazon.co.uk/Karma-Punishment-Chaplaincy-Harvard-Monographs/dp/0674260155
https://www.amazon.co.jp/-/en/Adam-J-Lyons/dp/0674260155/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Karma+and+Punishment%3A+Prison+Chaplaincy+in+Japan&qid=1624157388&sr=8-1
(文責:石塚伸一)
────────────────────────────
◎本大会の成果については、
犯罪学研究センターHPにおいて順次公開する予定です。
なお、ゲスト・スピーカーのAbstract(英語演題)はオフィシャルサイト内のPDFリンクを参照のこと。
ACS2020 Program
https://acs2020.org/program.html
*アジア犯罪学会(Asian Criminological Society)
マカオに拠点をおくアジア犯罪学会(Asian Criminological Society)は、2009年にマカオ大学のジアンホン・リュウ (Liu, Jianhong) 教授が、中国本土、香港、台湾、オーストラリアなどの主要犯罪学・刑事政策研究者に呼びかけることによって発足しました。その使命は下記の事柄です。
① アジア全域における犯罪学と刑事司法の研究を推進すること
② 犯罪学と刑事司法の諸分野において、研究者と実務家の協力を拡大すること
③ 出版と会合により、アジアと世界の犯罪学者と刑事司法実務家のコミュニケーションを奨励すること
④ 学術機関と刑事司法機関において、犯罪学と刑事司法に関する訓練と研究を促進すること
このような使命をもつアジア犯罪学会は、現在、中国・香港・マカオ・台湾・韓国・日本・オーストラリア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・アメリカ・スイス・パキスタン・インド・スリランカなどの国・地域の会員が約300名所属しており、日本からは会長(宮澤節生・本学犯罪学研究センター客員研究員)と、理事(石塚伸一・本学法学部教授・犯罪学研究センター長)の2名が選出されています。