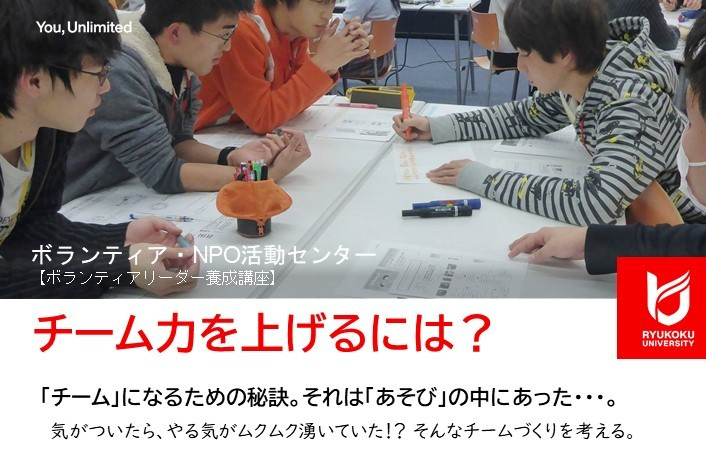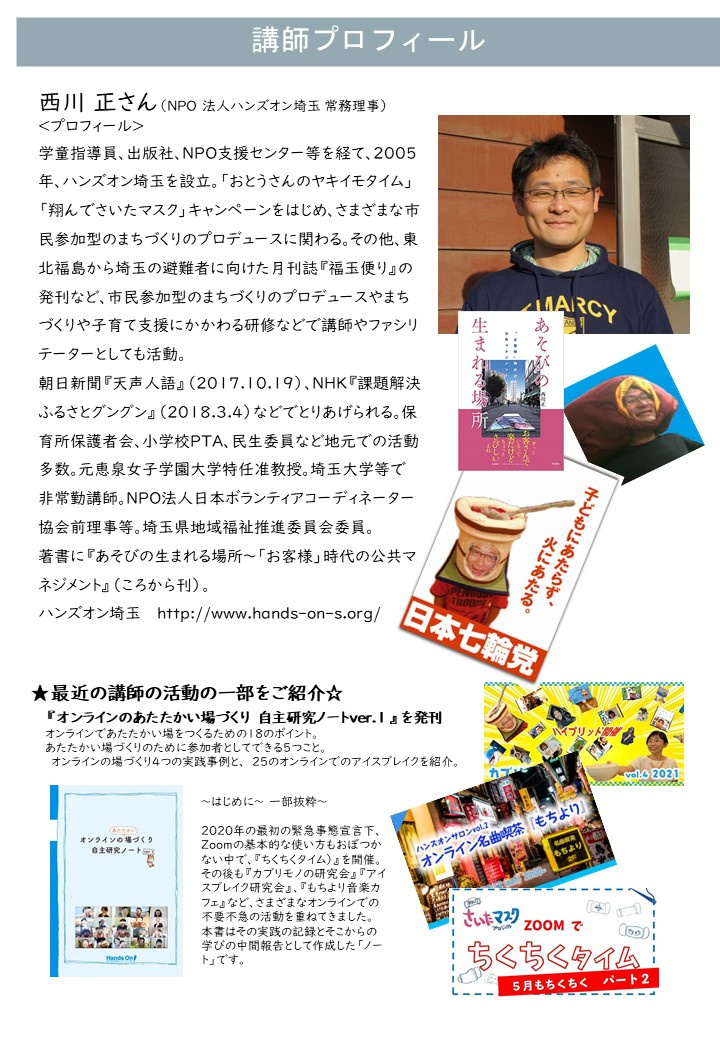【本件のポイント】
- 龍谷大学がホスト校となり、2021年6月18日(金)〜21日(月)に国際学会「アジア犯罪学会(※1)第12回年次大会」をオンラインで初開催
- 龍谷大学犯罪学研究センター(※2)研究メンバーを中心に日本の状況を多数報告し、国際社会における日本の犯罪学・刑事政策の存在感を高めることが目的
- 全編オンライン方式によるものの、交流のための企画・ツールなどを用意し、アジアを中心とした若手研究者の交流・育成の機会に
【本件の概要】
龍谷大学がホスト校となり、2021年6月18日(金)〜21日(月)に国際学会「アジア犯罪学会 第12回年次大会(Asian Criminological Society 12th Annual Conference, 通称: ACS2020)」をオンラインで開催します。今大会は当初2020年10月に対面で実施予定でしたが、新型コロナの世界的な流行状況に鑑み、開催方式をオンラインに変更し、この6月に開催する運びとなりました。
2014年の大阪大会に次いで国内では2回目の開催となる今大会では、アジア・オセアニア地域における犯罪学の興隆と、米国・欧州などの犯罪学の先進地域との学術交流を目的としています。大会の全体テーマには『アジア文化における罪と罰:犯罪学における伝統と進取の精神(Crime and Punishment under Asian Cultures: Tradition and Innovation in Criminology)』を掲げ、「世界で最も犯罪の少ない国」といわれる日本の犯罪・非行対策と社会制度・文化に対する理解を広めることを目指します。
これまでアジア地域の犯罪学は、欧米の先進的犯罪学を移入し、その犯罪学理論・刑事政策理論をそれぞれの国において検証することを主たる課題にしてきました。しかし、これからの犯罪学には、世界人口の半数以上を占め、急速に発展しつつあるアジア地域の社会制度や文化に根ざしたアジア発の理論構築、また、犯罪や非行の研究から得られた知見による共生社会の創造に向けた提言が求められています。
今大会では、欧米・アジアから世界的な犯罪学者を10名招へいし、講演を行います。とりわけ、「統制文化論(Culture of Control)」の主唱者であるDavid Garland教授(アメリカ)と「立ち直り論(desistance)」の第一人者であるShadd Maruna教授(イギリス)は、日本的社会・文化における理論構築に大きな示唆を与えるとともに、「なぜ日本には犯罪が少ないのか」という疑問を考察する上での理論的前提を提供することが期待されています。
また、オンライン開催に伴い参加者専用の視聴・交流のためのウェブ・プラットフォームを新たに構築しました。基調講演や全体会、テーマセッションなどすべてのライブ・セッションや個別報告を動画で録画し、6月30日まで大会専用のプラットフォーム上でオンデマンド配信し、なおかつ各動画へのコメント機能を参加者に付与することを通して、時差・物理的距離の制約なく会員間の交流促進をはかります。
1.「アジア犯罪学会 第12回年次大会」実施概要
- 名称:アジア犯罪学会 第12回年次大会 (Asian Criminological Society 12th Annual Conference)
- 期間:2021年 6月18日(金)~6月 21日(月)/4日間
- 会場:オンライン(配信元:龍谷大学 深草キャンパス)
- 大会参加費:28,000円(税込)*6月10日までの事前登録制 - 言語:全編英語
- 主催:アジア犯罪学会2020(大会実行委員会)
- 共催:龍谷大学 犯罪学研究センター・アジア犯罪学会
- 公式サイト:https://acs2020.org/
※既に学会は締切期限が間近であり、本リリースはメディアの方を対象としております。
2.用語解説
1)アジア犯罪学会
マカオに拠点をおくアジア犯罪学会(Asian Criminological Society)は、2009年にマカオ大学のジアンホン・リュウ (Liu, Jianhong) 教授が、中国本土、香港、台湾、オーストラリアなどの主要犯罪学・刑事政策研究者に呼びかけることによって発足しました。その使命は下記の事柄です。
- アジア全域における犯罪学と刑事司法の研究を推進すること
- 犯罪学と刑事司法の諸分野において、研究者と実務家の協力を拡大すること
- 出版と会合により、アジアと世界の犯罪学者と刑事司法実務家のコミュニケーションを奨励すること
- 学術機関と刑事司法機関において、犯罪学と刑事司法に関する訓練と研究を促進すること
このような使命をもつアジア犯罪学会は、現在、中国・香港・マカオ・台湾・韓国・日本・オーストラリア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・アメリカ・スイス・パキスタン・インド・スリランカなどの国・地域の会員が約300名所属しており、日本からは会長(宮澤節生・本学犯罪学研究センター客員研究員)と、理事(石塚伸一・本学法学部教授・犯罪学研究センター長)の2名が選出されています。
2)龍谷大学 犯罪学研究センター
「犯罪学」(英:Criminology)とは、犯罪にかかわる事項を科学的に解明し、犯罪対策に資することを目的とする学問です。龍谷大学 犯罪学研究センターは、建学の精神を具現化する事業として2016年6月に発足。犯罪学はその対象が犯罪や非行であるため、人びとの関心は、罪をおかした人の素質や環境、捜査手法、防犯対策に集中しがちですが、当センターでは「人が日々の生活で抱える問題や失敗を“つまずき”という視点でとらえ、社会から孤立させないようにする。“つまずき”からの立ち直りには、地域社会における総合的な支援が必要」と考え、研究の社会実装に向けた諸活動を展開してきました。
3.メディアの方へ
1)メディア関係者向け視聴パス
今大会は、大会参加登録を行ったメンバーのみが閲覧可能な「オンライン・プラットフォーム」で実施します。メディア関係者に限り、特別に視聴パスを発行しますので、視聴ご希望の方は6月17日(木)までに、犯罪学研究センターまで問い合わせください。
2)6月21日(月)全体講演のご案内
最終日の6月21日(月)11:00-12:00、本学深草キャンパス・成就館にて、浜井浩一教授(本学法学部・今大会プログラム編成委員)が、日本の犯罪状況を包括的に報告する全体講演を英語で行います。このイベントに限り現地での参加を受け付けます。現地でのご参加希望の方は、あらかじめお問い合わせください。
問い合わせ先:龍谷大学 犯罪学研究センター
Tel 075-645-2184 Fax 075-645-2240
E-mail crimrc2016@ad.ryukoku.ac.jp URL https://crimrc.ryukoku.ac.jp/