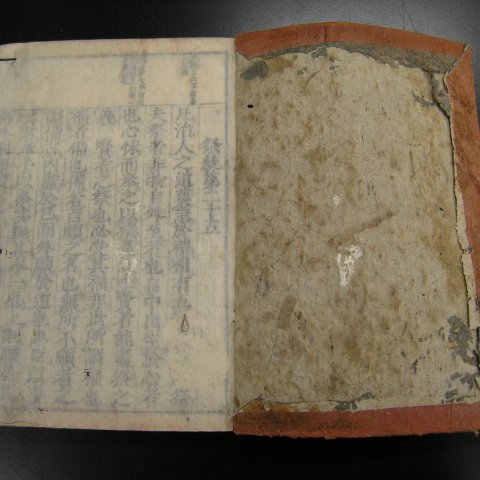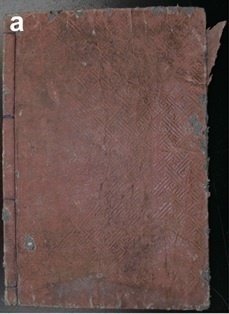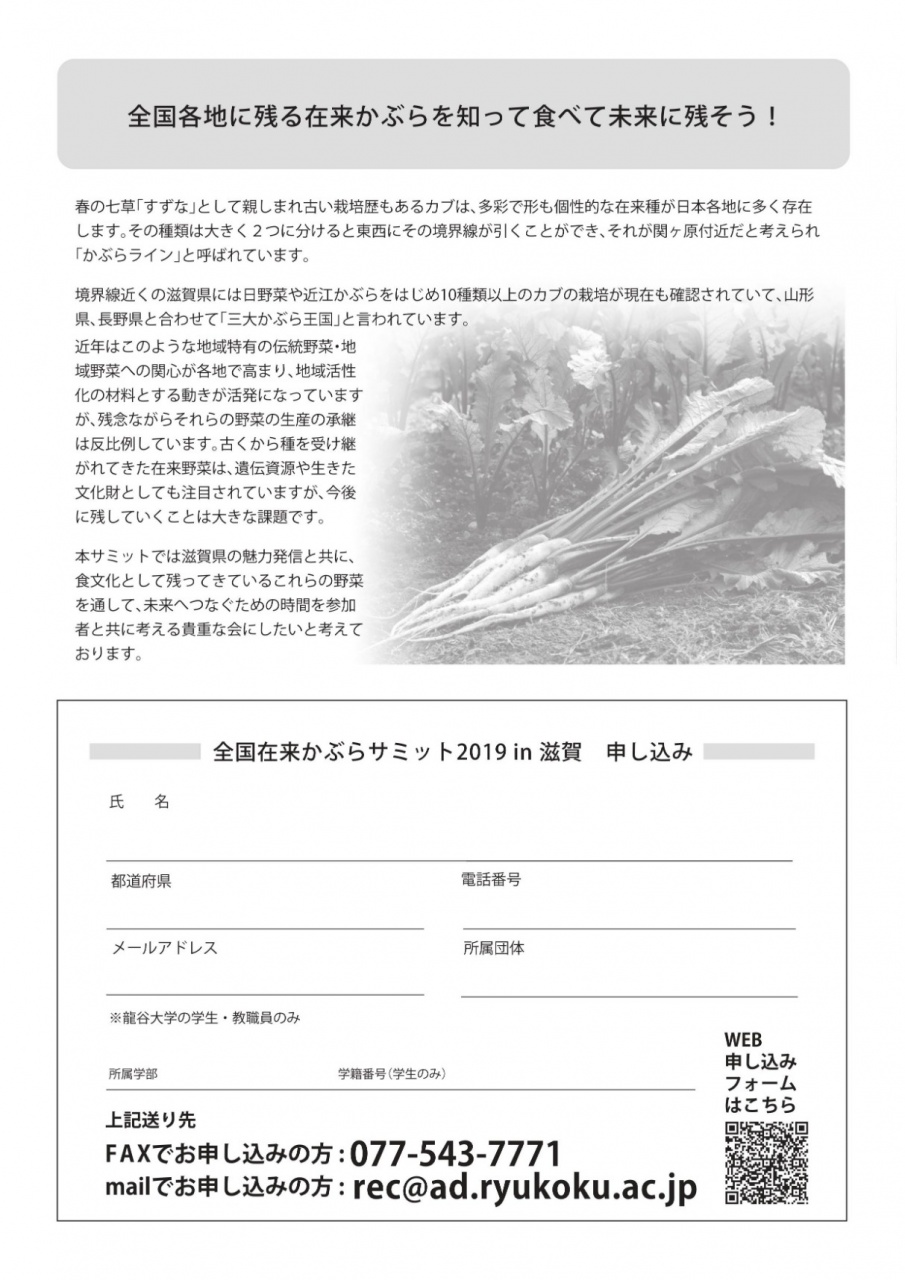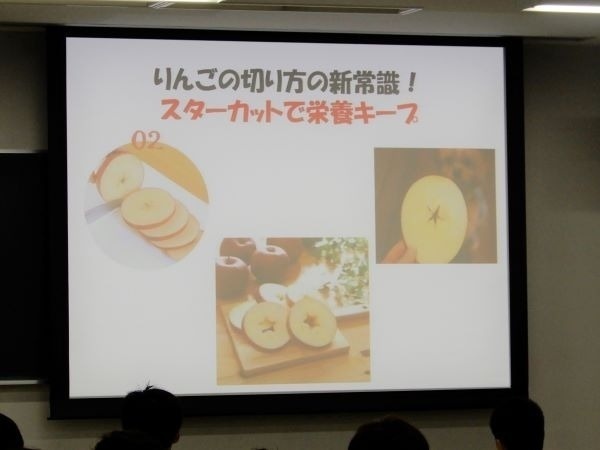第11回印南町(和歌山県)かえるのフェスティバルに参加しました【REC事務部・農学部】
11 月 17 日(日)、本学が地域連携協定を締結している和歌山県日高郡印南町の地域交流イベント「第11回印南かえるのフェスティバル」に参加しました。
同町とは、「龍谷ソーラーパーク」の設置を縁として2014 年に連携協定を締結して以来、毎年、本フェスティバルに本学の学生を派遣しています。
今年度は野外活動部が子どもたちを対象とした工作ブースを出展し、「動く紙コップおもちゃ」を100名を超える子供たちと作った他、農学部から学生広報スタッフが参加し、「食の循環実習」で栽培、収穫した新米や野菜の販売を行い、地元の方々との交流を楽しみました。
また、本学マスコットキャラクターのロンちゃん、ロン君も会場をねり歩き、ゆるキャライベントに出演したり、和歌山県出身の吉本住みます芸人「わんだーらんど」の二人がブースに来て龍谷大学の宣伝をしていただくなど、地元の祭りを大いに盛り上げてくれました。
参加した学生の感想
「事前に印南町のことを学習して、このフェスティバルに参加したが、鰹節や真妻わさび発祥の地だと知って驚いた。また、印南町は農業が盛んで、特産物も多いが、過疎化や後継者不足が進んでいる。今回参加したことで、印南町の地域課題を考えるきっかけになった。」
「昨年も参加して、地元の方との交流が楽しかったので今年も参加した。印南町の方に龍谷大学が年々受け入れられていると感じた。」
「農学部のフェスティバル参加は2回目だが、温かく迎えてくれた。昨年は新米だけだったのでなかなか販売できなかったが、今年は野菜のサービスやニンニクのつかみ取りなどを加え交流しながら楽しく販売できた。来年は加工品の販売などもっと工夫したい。」