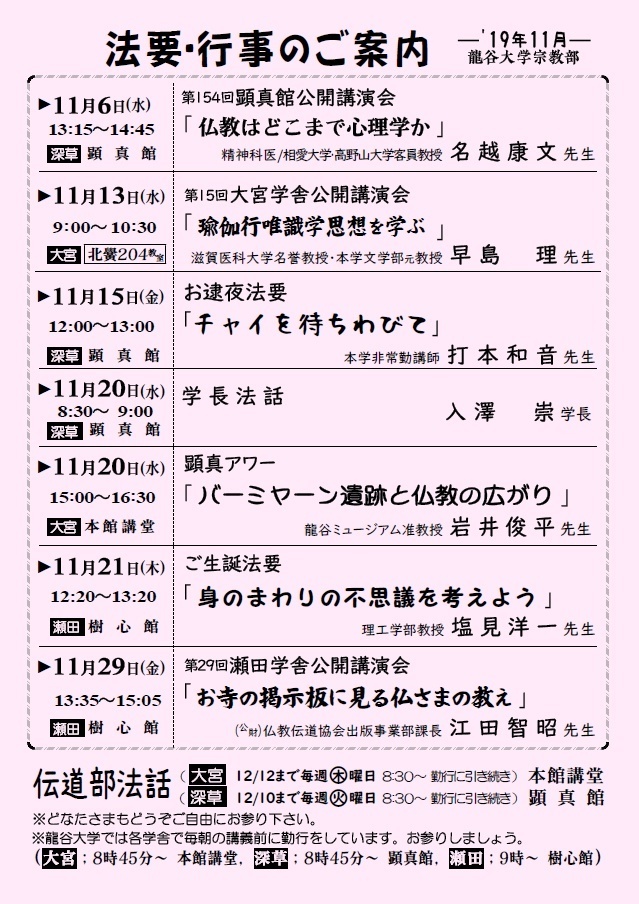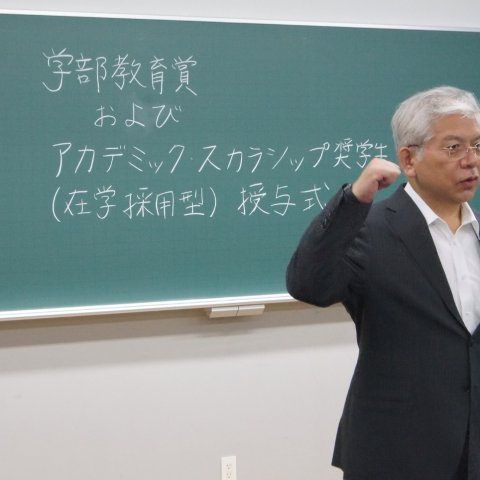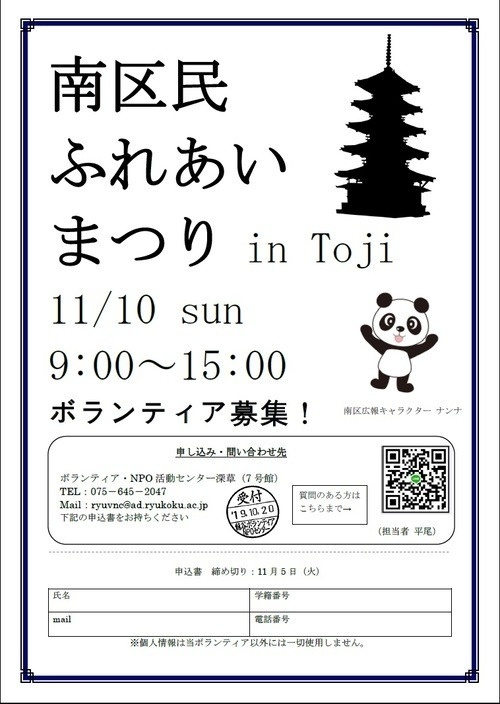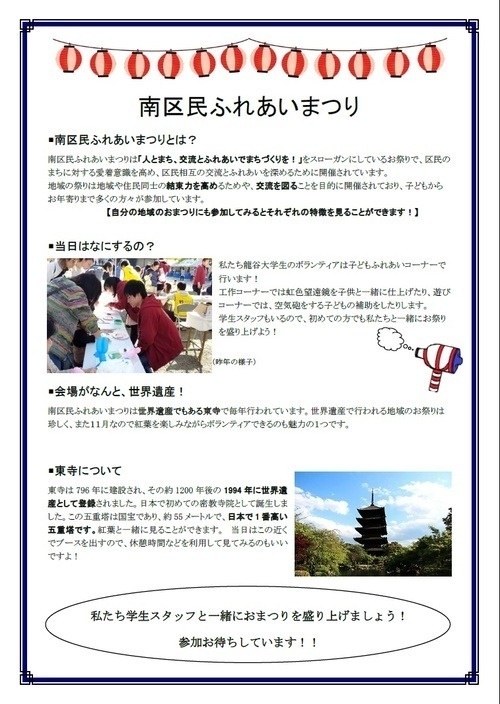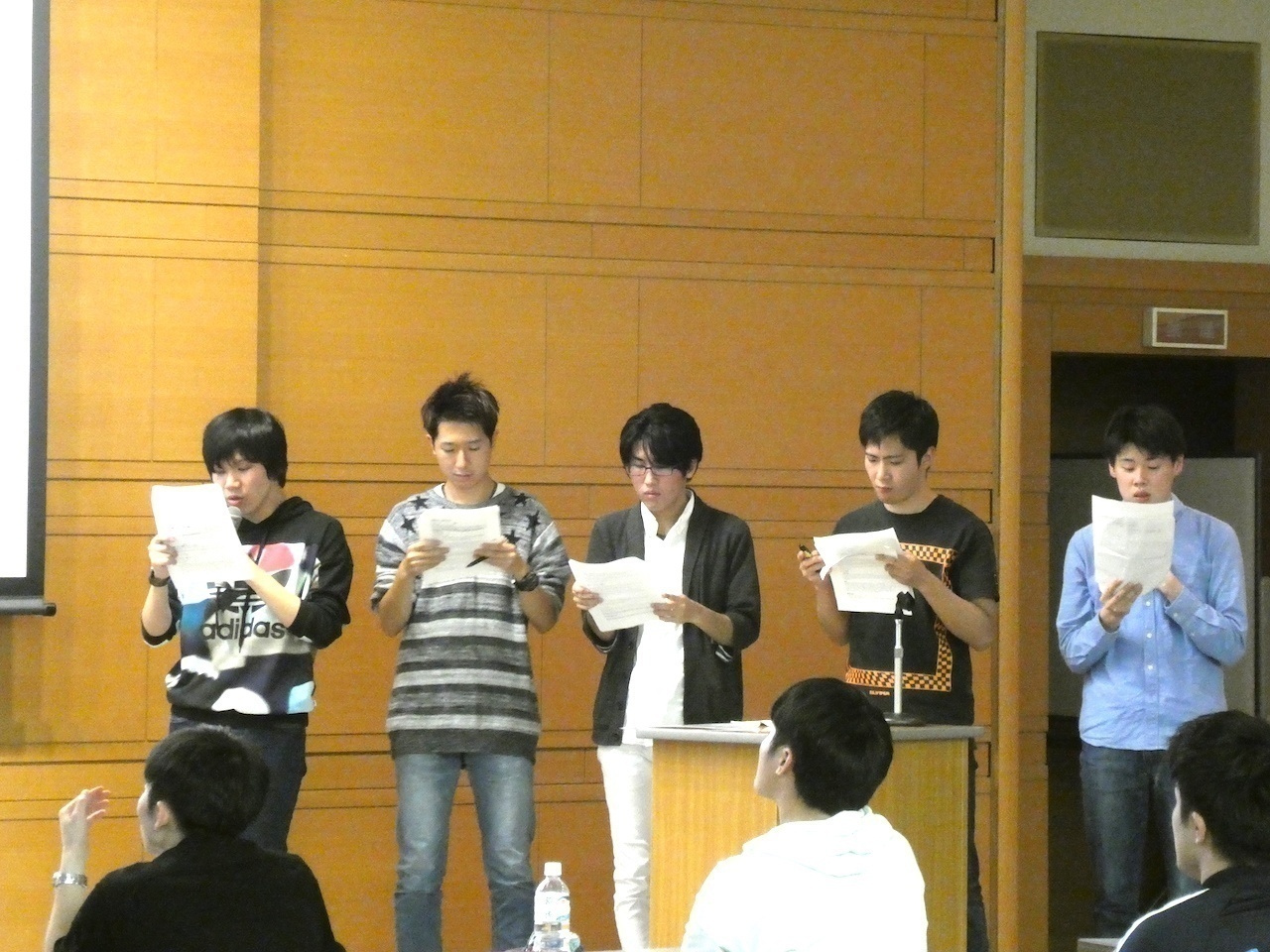2019年11月の法要・行事のご案内
■11月6日(水) 13:15~14:45
顕真館公開講演会
仏教はどこまで心理学か
精神科医/相愛大学・高野山大学客員教授 名越 康文 先生
深草学舎 顕真館
■11月13日(水) 9:00~10:30
大宮学舎公開講演会
瑜伽行唯識学思想を学ぶ
本学元教授 早島 理 先生
大宮学舎 北黌204教室
■11月15日(金) 12:00~13:00
お逮夜法要
チャイを待ちわびて
本学非常勤講師 打本 和音 先生
深草学舎 顕真館
■11月20日(水) 8:30~9:00
学長法話
学長 入澤 崇 先生
深草学舎 顕真館
■11月20日(水) 15:00~16:30
顕真アワー
バーミヤーン遺跡と仏教の広がり
龍谷ミュージアム准教授 岩井 俊平 先生
大宮学舎 本館講堂
■11月21日(木) 12:20~13:20
ご生誕法要
身のまわりの不思議を考えよう
講 師:理工学部教授 塩見 洋一 先生
瀬田学舎 樹心館
■11月29日(金) 13:35~15:05
瀬田学舎公開講演会
「お寺の掲示板」に見る仏さまのおしえ
仏教伝道協会 江田 智昭 先生
瀬田学舎 樹心館
※学生法話の情報は別途ご案内いたします。
※どなたさまもどうぞご自由にお参り下さい。
※龍谷大学では各学舎で毎朝の講義前に勤行をしています。お参りしましょう。
大宮:8時45分~ 本館講堂、深草:8時45分~ 顕真館、瀬田:9時~ 樹心館
(朝の法話がある日は、15分早く開始します)