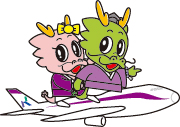令和元年台風第19号で被災した学生への各種奨学金のお知らせ
令和元年台風第19号で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。
また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)または学部窓口までお知らせください。
※学生部メールアドレス:gakusei@ad.ryukoku.ac.jp
1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。
■金額
定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。
| 対象 | 奨学金額 |
|---|---|
| 父母のいずれか(又は家計支持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)した場合 | 年間授業料相当額 |
| 父母のいずれか(又は家計支持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 | 半期授業料相当額 |
休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。
2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。
■金額
一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)
■その他
発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。
3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または家計支持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。
■貸与始期
| 緊急採用(第一種奨学金) | 2019年10月以降で申込者が希望する月 |
|---|---|
| 応急採用(第二種奨学金) | 2019年4月以降で申込者が希望する月 |
■貸与終期
| 緊急採用 (第一種奨学金) | 2020年3月 ただし、2020年度においてなお、第一種奨学金が必要と認められる者から、2020年度1月10日(金)までに「緊急採用(第一種)奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(2021年度3月)まで貸与を継続します。また、年度末ごとに同様の願い出を繰り返すことにより就業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。 |
|---|---|
| 応急採用 (第二種奨学金) | 修業年限の終了月まで |