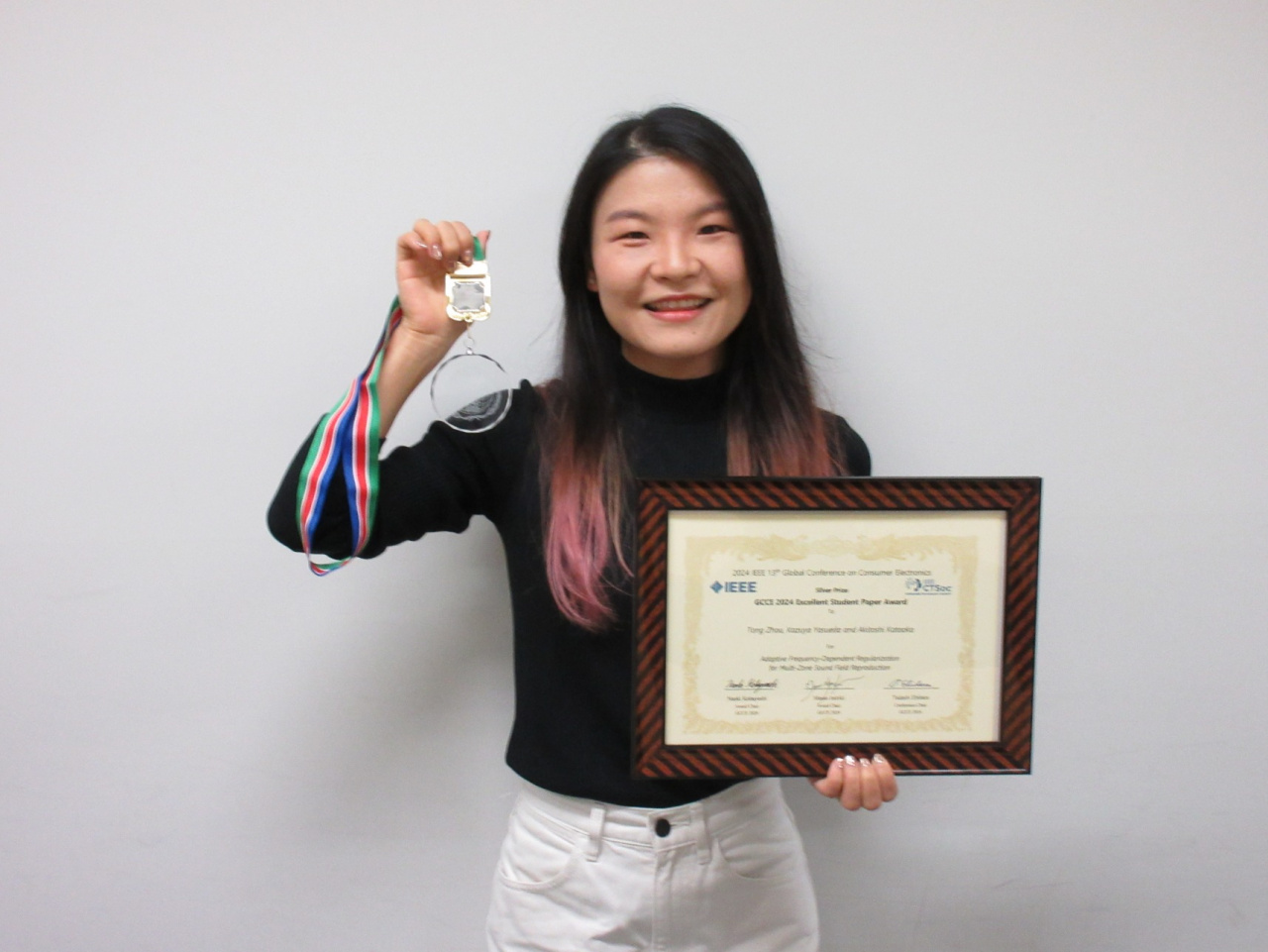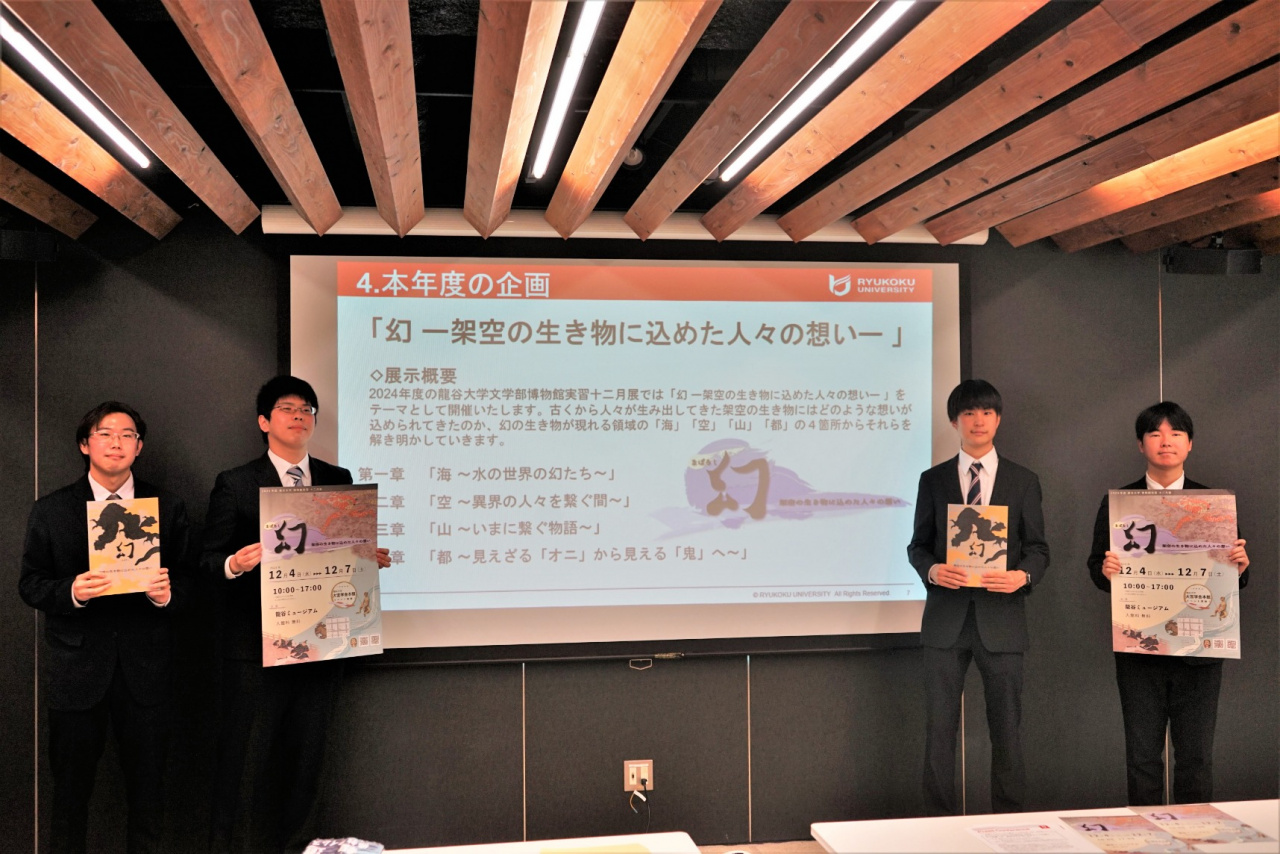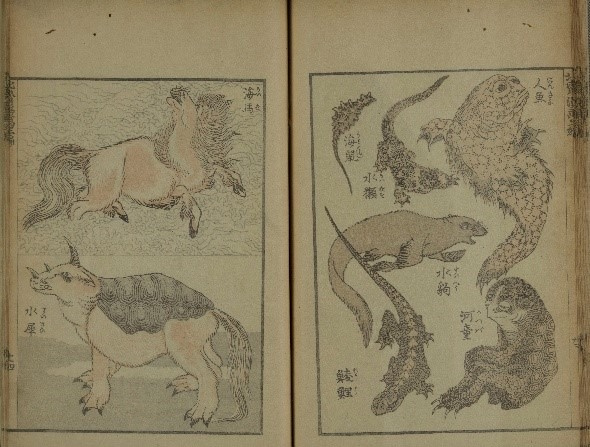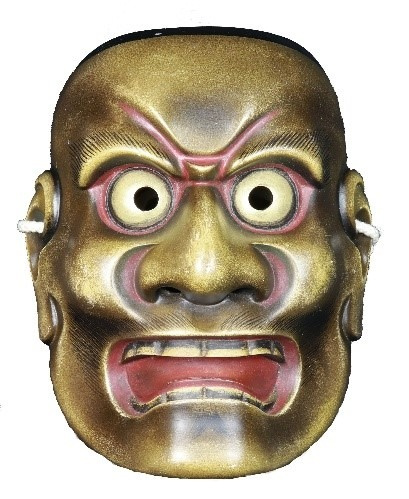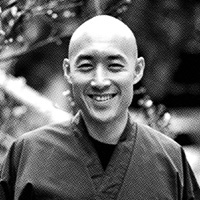龍谷大学先端理工学部生による宇治田原町活性化プロジェクト第2弾 フィールドワークにより築いた地域との関係性をもとに地域住民に地元の魅力を再確認してもらうマルシェを開催
【本件のポイント】
・宇治田原町は煎茶発祥の地だが、お茶の名産地は宇治市という印象もあり、観光客数は45倍の差がある。
・龍大生が宇治田原町の地域活性化に取り組み、プロジェクトの第1弾では同町の観光バスに関連する専用HP、チャットボットを制作し魅力を発信。1日あたりの観光バス利用者は前年度比約1.7倍に増加。
・第2弾として学生がフィールドワークの中で関係性を築いてきた地元の老舗お茶屋などが出店するマルシェを開催。地域住民に学生目線で感じた宇治田原町の魅力を再確認してもらう機会に。
【本件の概要】
宇治田原町には煎茶発祥の地である湯屋谷(やんたん)がありますが、京都のお茶の名産は宇治市という印象もあり、観光客数は年間で約45倍も差があります。このことついて、今年4月から本学先端理工学部の学生3名と教員が、煎茶発祥の地であることや煎茶のオリジナル性を多くの人にアピールし、宇治田原町を活性化するプロジェクトを開始しました。この活動は、本学の学生活動支援制度「龍谷チャレンジ(※1)」に採択されており、学生たちは約4か月間、同町で地域住民やお茶屋等にヒアリングを行い、地域の魅力を学生目線で再発見してきました。
8月には本プロジェクトの第1弾として、宇治市と宇治田原町をつなぐ観光バスのバス停周辺施設の魅力をまとめた専用HPやチャットボットを制作しました(※2)。京都京阪バス、お茶の京都DMOと連携して実施し、前年度の同バス事業と比較し1日あたりのバス利用者数が約1.7倍に増加しました(京都京阪バス調べ)。
今回は第2弾として、地域コミュニティ型コインランドリーの取り組みを推進するアクア株式会社の協力のもと、今年10月に宇治田原町に初めてオープンしたコインランドリーにてマルシェを開催します。このマルシェには、学生が実際に足を運んで関係性を築いてきた地元の喫茶店や老舗お茶屋などが出店することで、学生目線で感じた宇治田原町の魅力を地域住民に再確認してもらう機会とします。
日 時:11月30日(土)11時00分~15時00分
場 所:AQUAランドリーサテライト京都宇治田原店
(京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字大溝15番)
出店店舗:あばんずキッチン(宗円交遊庵やんたん内喫茶)、そば処実り(蕎麦屋)、
一十(鯖寿司専門店)、流芳園(日本茶専門店) その他
※1)龍谷チャレンジ:学生の自主活動や社会連携活動について、支援金をはじめとする
様々なサポートを行う制度
【詳細】https://www.ryukoku.ac.jp/campus_career/activity/smap.html
※2)第1弾プロジェクト: https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-15202.html
問い合わせ先:龍谷大学REC事務部(京都)
Tel 075-645-2098 rec-k@ad.ryukoku.ac.jp https://rec.seta.ryukoku.ac.jp/index.php