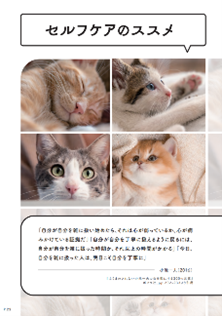交換留学生から学ぶ海外の国「地球がキャンパスだ!」を開催!【R-Globe】
本学で学んでいる交換留学生が、それぞれの母国について紹介する「地球がキャンパスだ!」をグローバルコモンズで開催し、51名の学生(日本人学生44名、留学生7名)が参加しました。
5月27日(月):トゥール大学(フランス)
5月28日(火):東国大学(韓国)
5月30日(木):ゲント大学(ベルギー)
5月31日(金):パーダーボルン大学(ドイツ)
この「地球がキャンパスだ!」は、本学の学生にとって、さまざまな国の話を聞いたり、写真を見たり、留学生と直接話したりすることで、国際文化に触れる貴重な機会となっています。このような交流を通して、さらなる文化交流や異文化探求への関心が高まることを期待しています。
参加者からは「楽しかった」との感想が多数寄せられました。
「知らないことをたくさん知れて楽しかったです。」
「ドイツ文化は特色があることを知れて、楽しかったです。」
「もっと聞きたいくらいでした!」
「いつかドイツに行きたいです^^ ありがとうございました!!!」
「質問にもとても丁寧に答えてくださってよかったです!」
「日本語がとっても上手で、すごかったです!!」
「韓国のことをいっぱい知れて面白かったです!!」
「韓国にメチャ行きたくなりました!」
「大学がでかくて、メッチャきれいで行ってみたいと思いました。」
「写真がきれいで、説明も分かりやすくて行きたくなりました!」