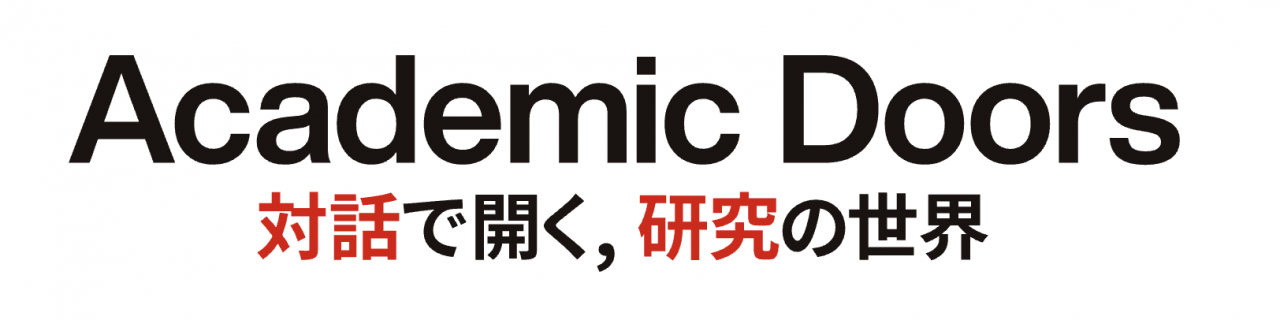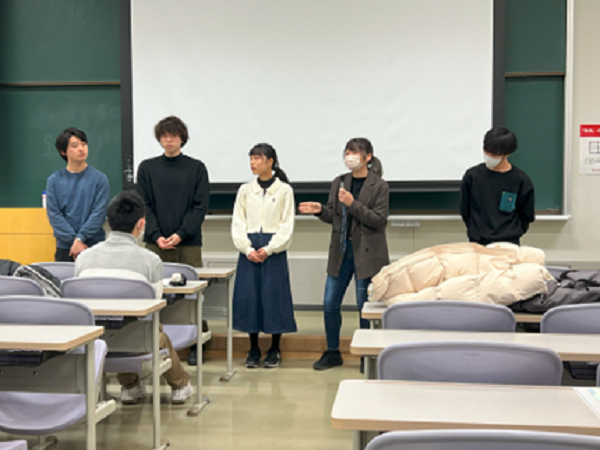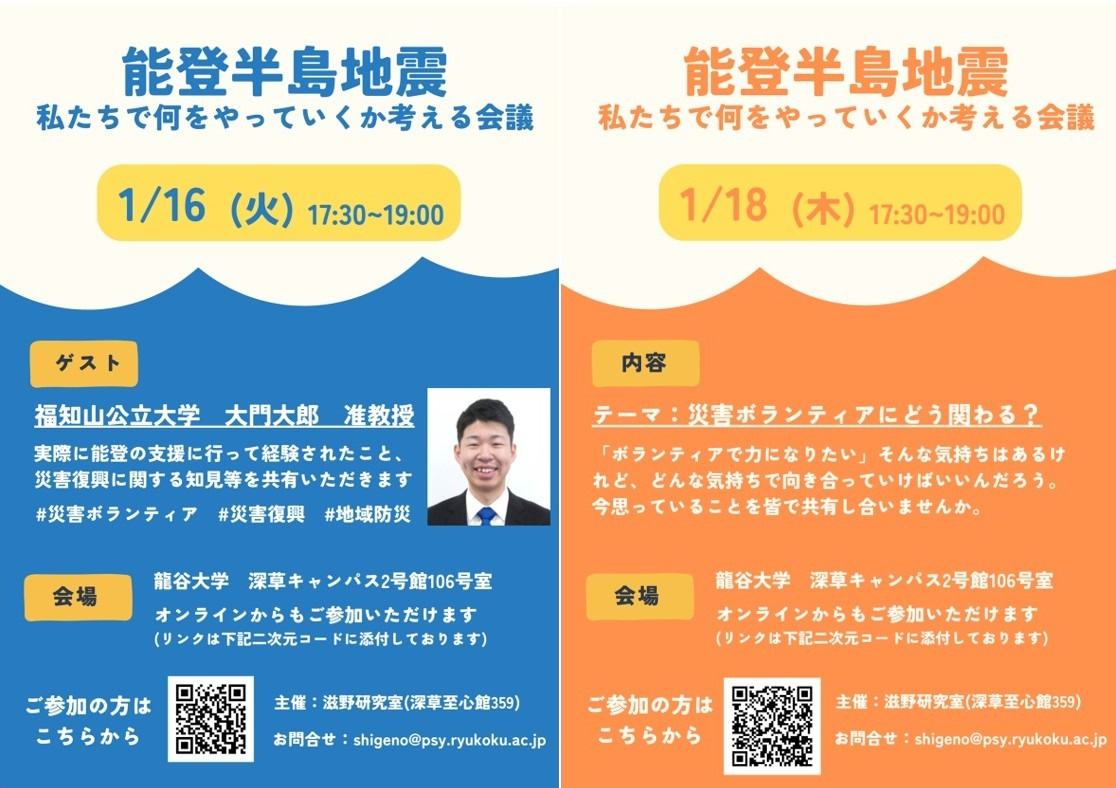Academic Doors新着記事「ギグワーカーは社会を変えるのか。 権利を自ら勝ち取る“労働政治”の意義を問う。」(安 周永・政策学部教授)【研究部・政策学部】
龍谷大学の研究者との対話を通じて研究内容を紹介する「Academic Doors~対話で開く、研究の世界~」に安 周永・政策学部教授の記事を掲載しました。
働き方改革やコロナ禍による雇用の不安、また、Uber Eatsやクラウドワークスなどの企業によるサービスの普及から、ギグワーカーという働き方を選ぶ人が増えています。
労働政治や雇用政策を研究する安 周永先生は、「特定のタスクや限られた期間で働くギグワーカーの存在が、日本の労使関係や社会政策を変える可能性がある」と指摘します。
より自由で多様な働き方を享受するために、私たちは何を考えいかに行動するべきなのでしょうか。諸外国の先行事例を交えながら考察いただきました。
▼記事はこちらから▼
https://academic-doors-ryukoku.jp/interview/23

安 周永・政策学部教授
~Academic Doorsとは!?~
10学部、1短期大学部を擁する総合大学として、幅広い分野の研究者が集う龍谷大学。新たな視点や考え方、未知なる分野の知識など、ここで活躍する研究者との対話には、知る喜びがあふれています。
龍谷大学では、研究成果の創出を通じて、世界が直面する課題を克服し、持続可能な社会の構築に寄与すること目的として「Academic Doors~対話で開く、研究の世界~」を開設しました。
このサイトでは本大学に所属する研究者との対話を通じて、多様な研究の魅力をわかりやすく紹介していきます。ぜひ研究のドアをノックする気分で、知的好奇心をくすぐるアカデミックな世界にふれてみませんか。