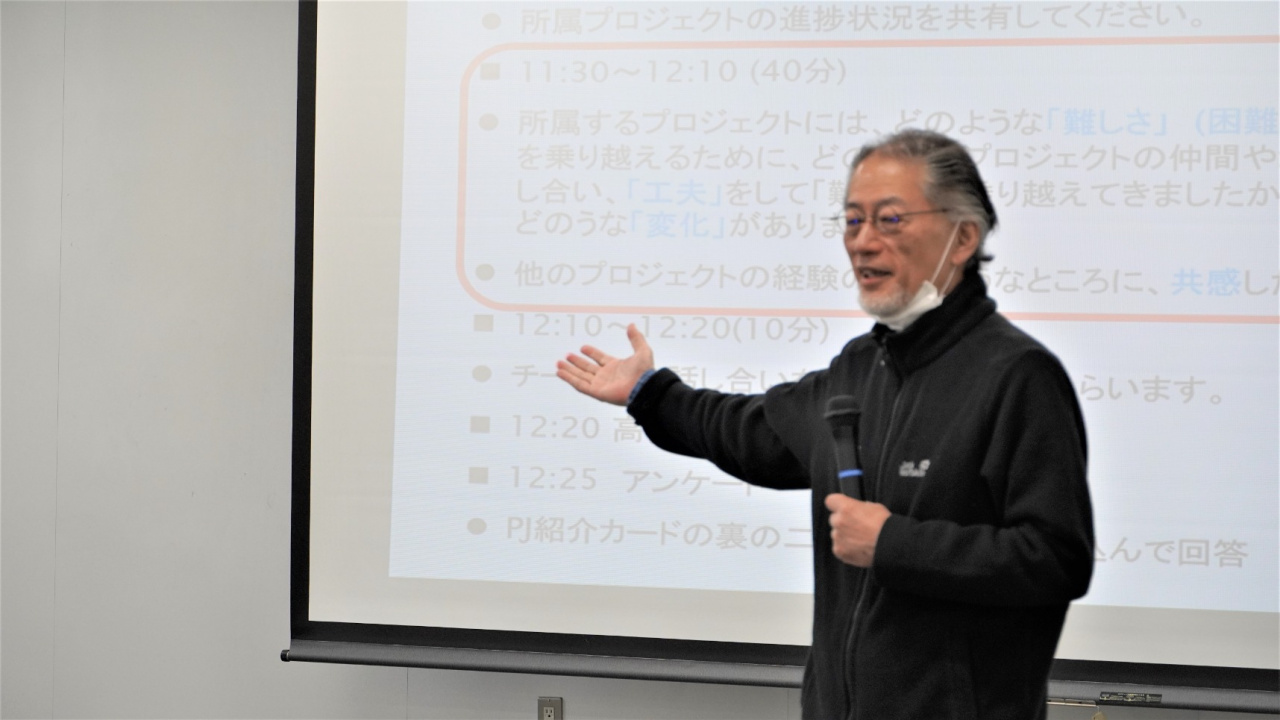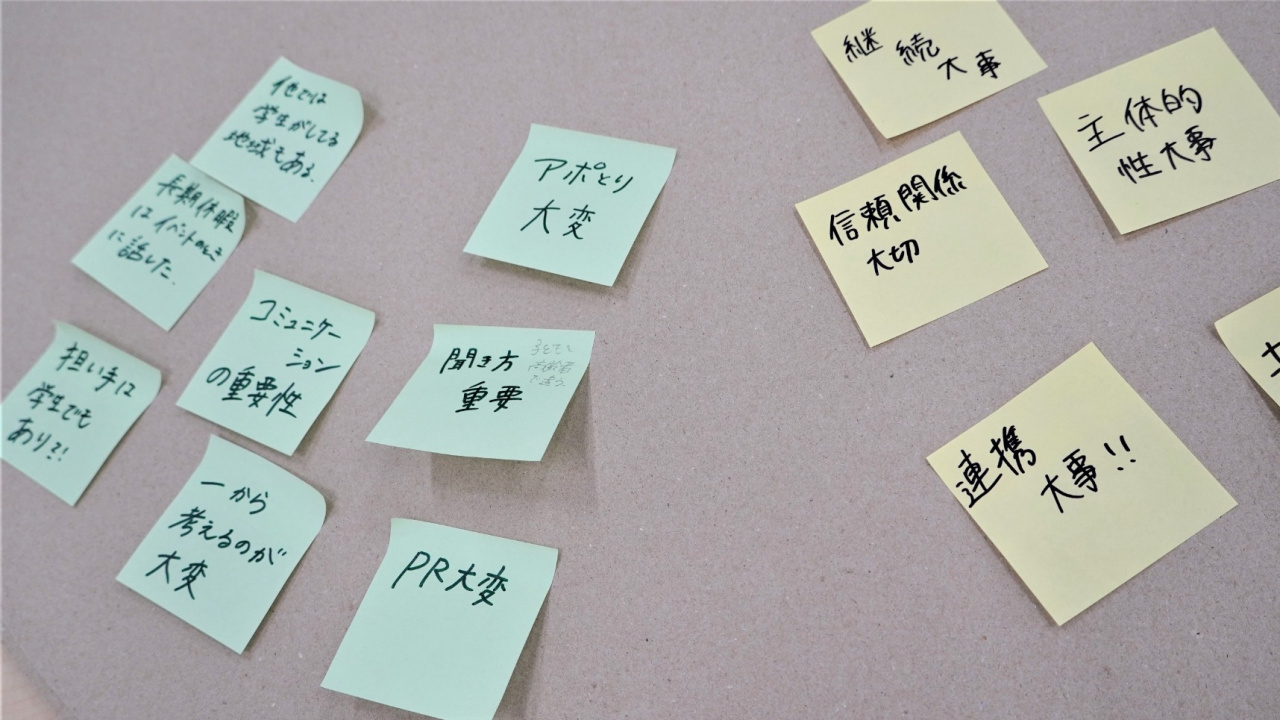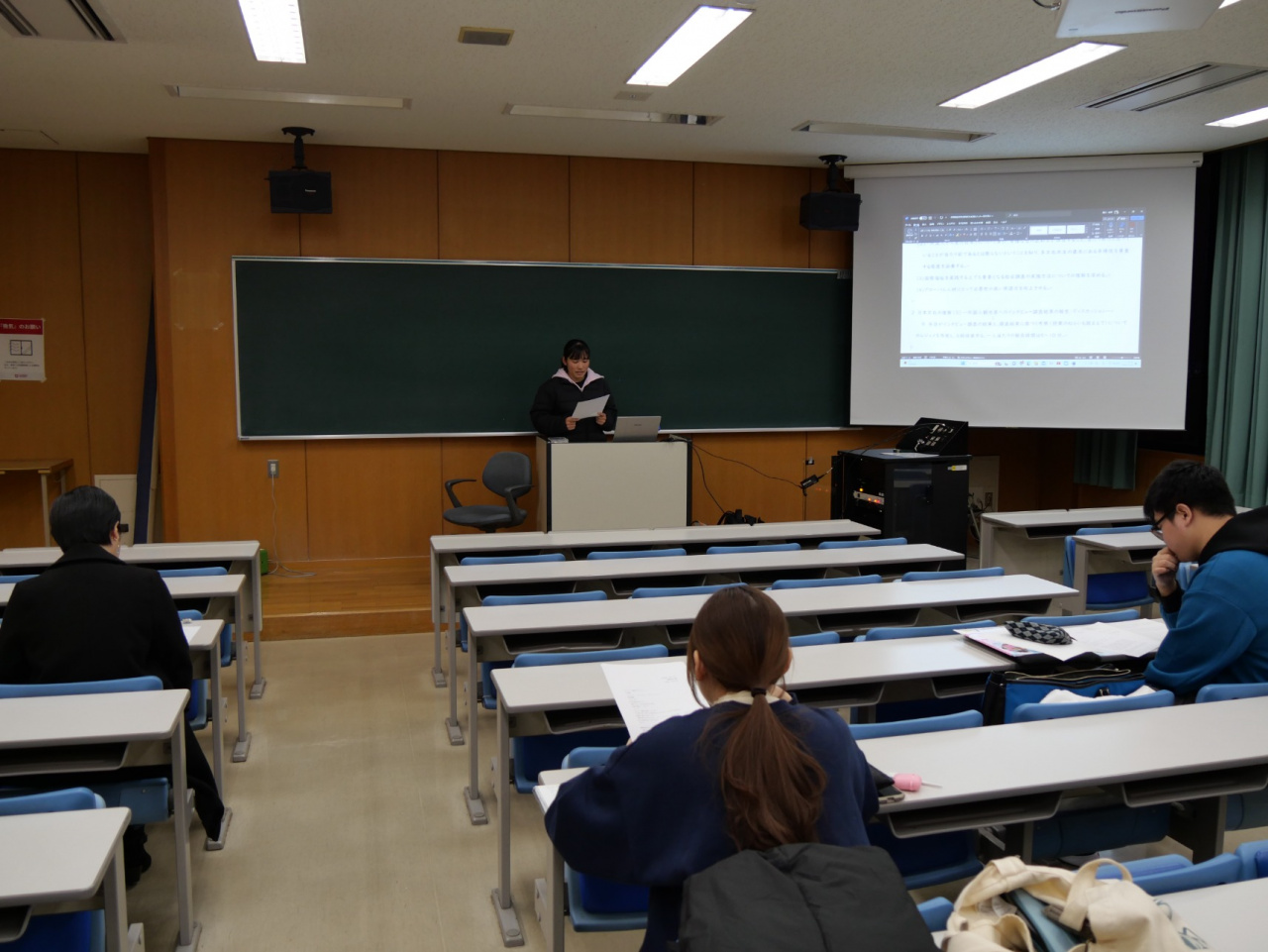<2024(令和6)年度修士課程入学者対象> 日本学生支援機構第一種奨学金「特に優れた業績による返還免除制度」採用時返還免除内定候補者の申請について
2024(令和6)年度に大学院修士課程への進学を希望する方を対象に日本学生支援機構大学院第一種奨学生「特に優れた業績による返還免除制度」採用時返還免除内定候補者の申請について、以下の通り受け付けます。
1.制度
「特に優れた返還免除制度」とは
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/gyosekimenjo/index.html
2024(令和6)年度 日本学生支援機構奨学金 採用時返還免除内定候補者(修士課程)申請要領
3.申請期間
| 日時 | ||
|---|---|---|
| 学生部(深草) |
2024年1月18日(木)16:00まで |
9:00~17:00 |
| 学生部(瀬田) | 9:00~17:00 | |
※最終日1月18日(木)は受付時間を16:00までといたします。
※郵送の場合は、1月18日(木)必着です。
<ダウンロードはこちらから>
①採用時返還免除内定候補者願<修士課程>(龍谷大学所定様式)
②スカラネット入力下書き用紙(※提出不要)