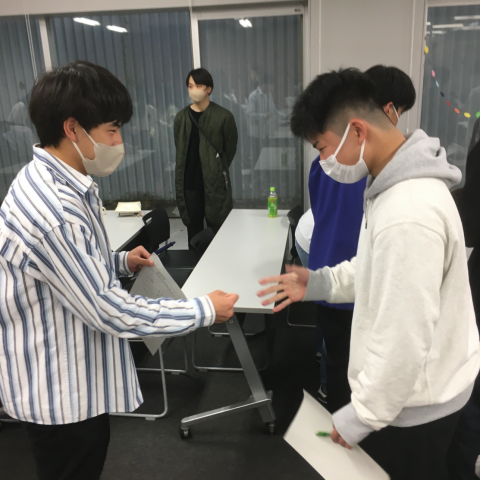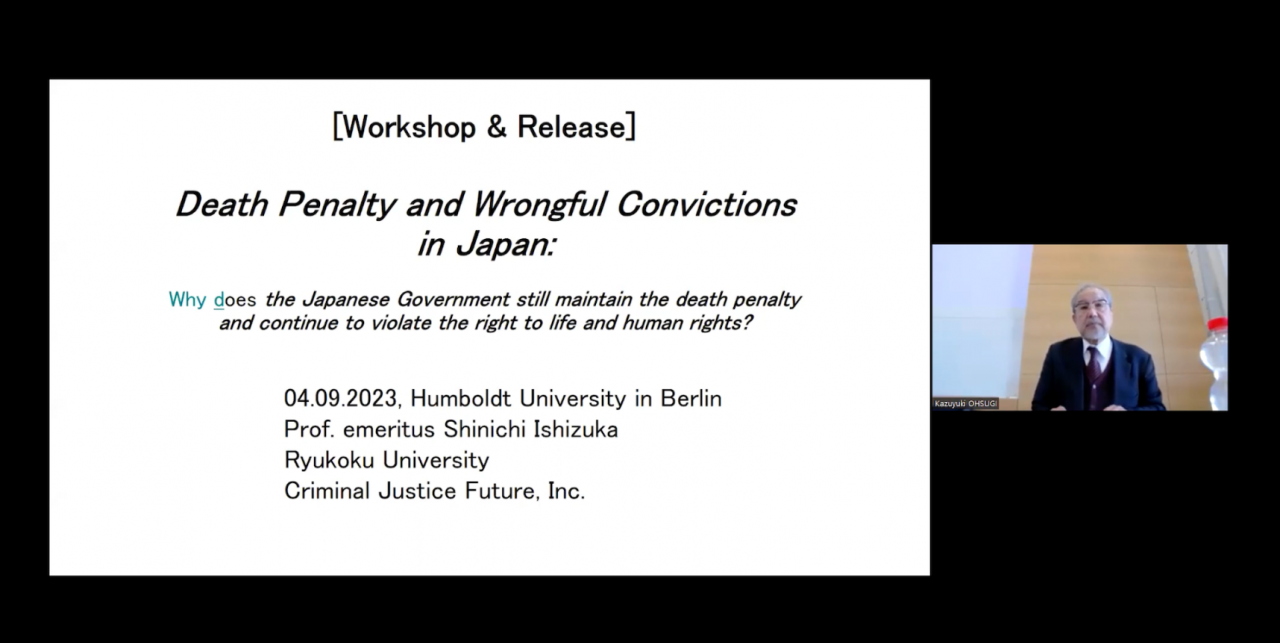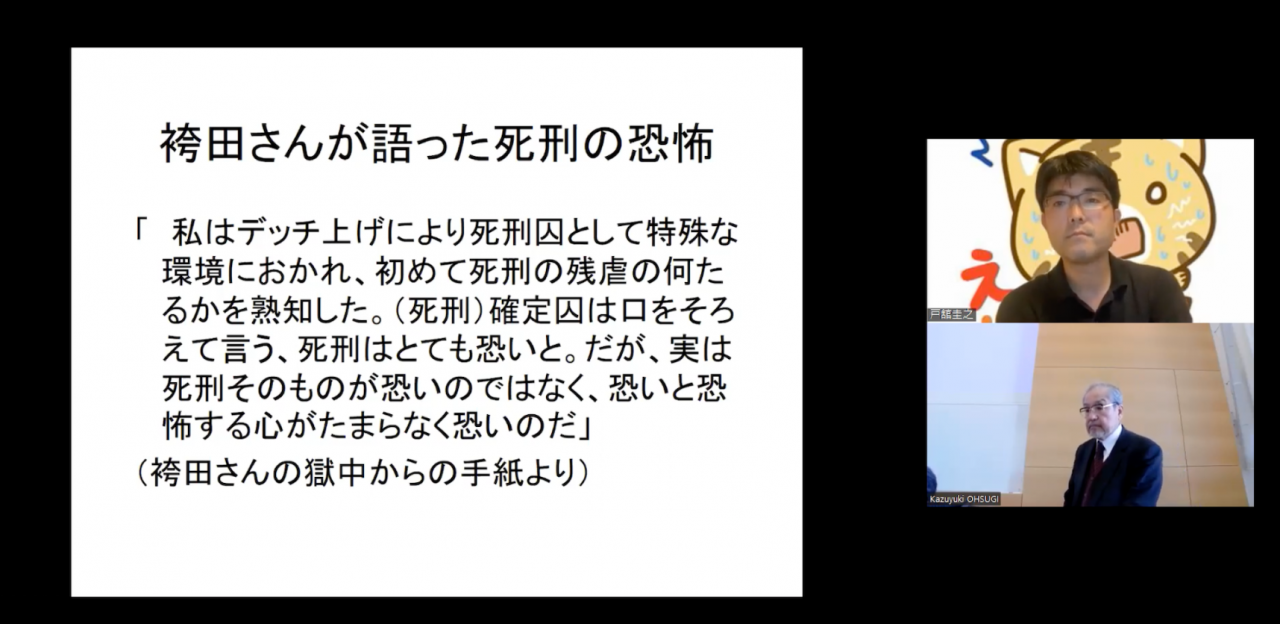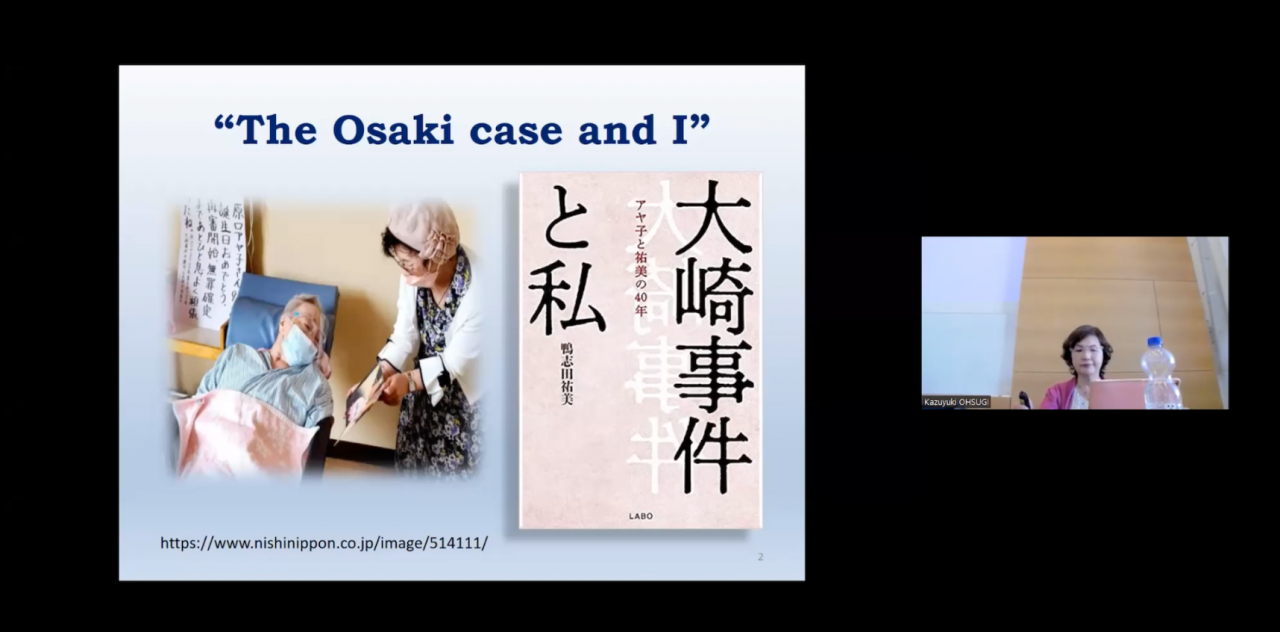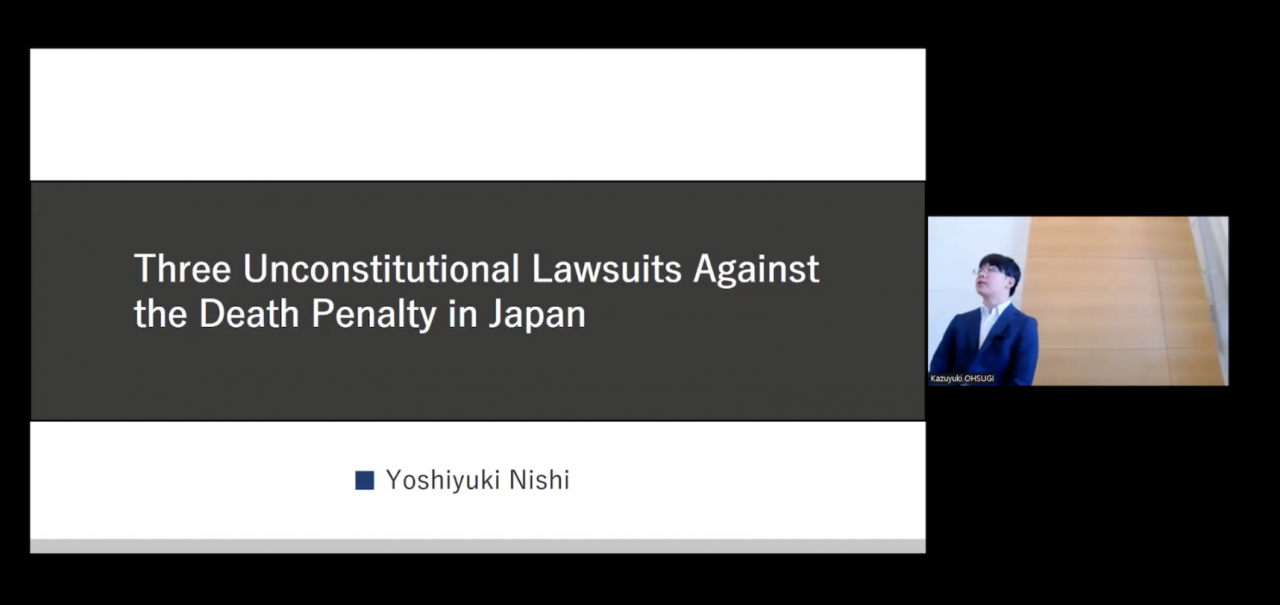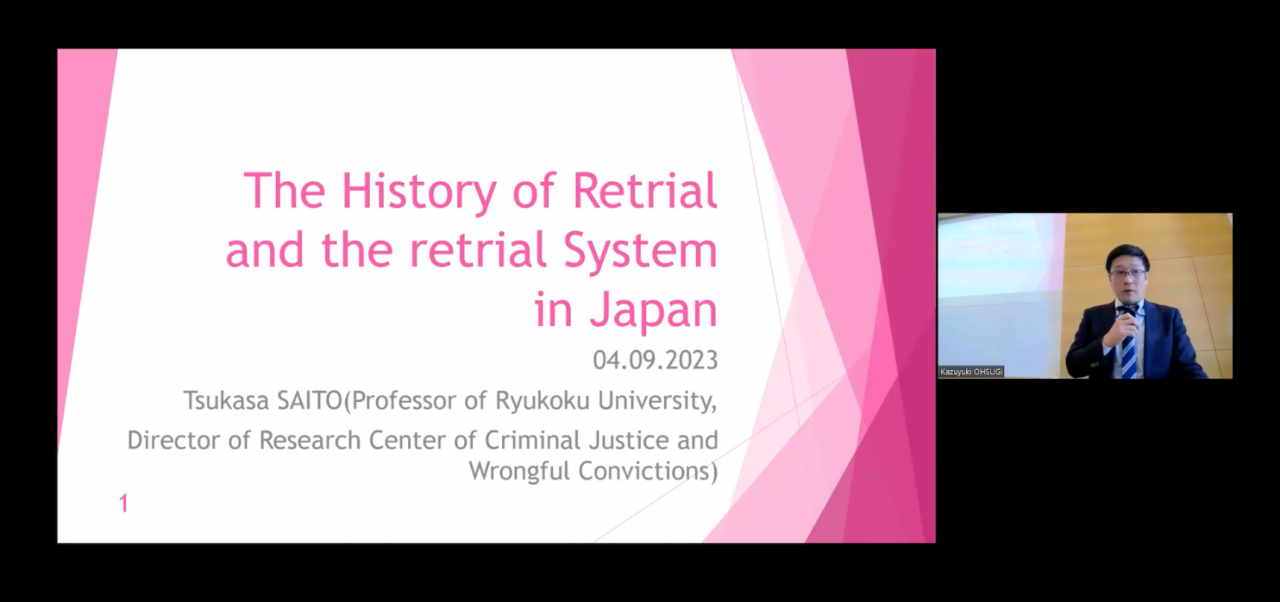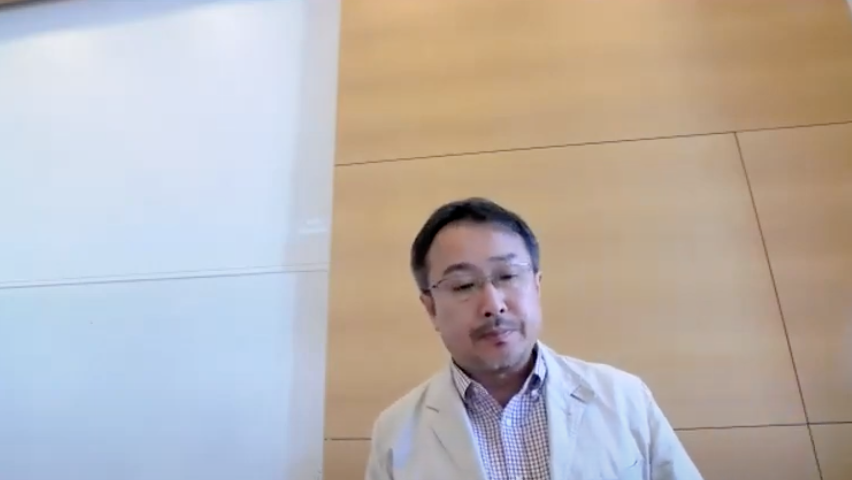【ノータバコ20】喫煙と生活習慣病

喫煙が体に悪い…ということは、これまでも紹介してきました。
これから、どのように体に悪いのかについて、「生活習慣病」=日ごろの行いの積み重ねによって至る病という観点から、もう少し詳しく説明していきます。
今回は、喫煙によって至る病を大きく4つにわけて概要を紹介します。
喫煙とがん
たばこの煙の中には、多くの発がん性物質が含まれます。喫煙は、多くの発がん性物質への暴露やDNAの損傷を引き起こし、がんのリスクを高めます。喫煙との因果関係が明らかになっているがんには、肺がん、口腔・咽頭がん、喉頭がん、鼻腔・副鼻腔がん、食道がん、胃がん、肝臓がん、膵臓がん、子宮頸がん、膀胱がんがあります。また、がん患者の喫煙は、生命予後を悪化させること、および二次がんを引き起こしやすくすることもわかっています。
喫煙と循環器疾患
たばこを吸うと、動脈硬化や血栓の形成が進むことから、虚血性心疾患を引き起こす原因となります。また、脳卒中(脳出血、くも膜出血、脳梗塞)のリスクを高めます。それだけでなく、喫煙は動脈硬化性疾患の早期発症や重症化にもつながることが報告されています。
喫煙と呼吸器疾患
たばこを吸うと、基礎的疾患がない場合でも、呼吸器疾患を引き起こす原因となります。喫煙は、さまざまな呼吸器症状を引き起こし、喘息のリスクを高めます。また慢性閉塞性肺疾患(COPD)の発生と、それによる死亡を引き起こす可能性があります。
それだけでなく、肺機能の発達障害や、呼吸機能の早期の低下にもつながります。さらに、新型コロナウイルスに感染したとき、喫煙者は非喫煙者と比較して、重症となる可能性が高いことが報告されています。
喫煙と糖尿病
たばこを吸うとは交感神経を刺激して血糖を上昇させるだけでなく、体内のインスリンの働きを妨げる作用があります。そのため糖尿病にかかりやすくなります。また糖尿病にかかった人がたばこを吸い続けると、治療の妨げとなるほか、脳梗塞や心筋梗塞・糖尿病性腎症などの合併症のリスクが高まることがわかっています。
喫煙をはじめてすぐに罹る病ではありませんが、喫煙し続けることによって、罹る可能性は格段に高まります。
できるだけ早く喫煙習慣を脱して、このような病に罹る可能性を下げていきましょう。
参考・出典:厚生労働省e-ヘルスネット 「喫煙とNCD(生活習慣病)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco-summaries/t-03