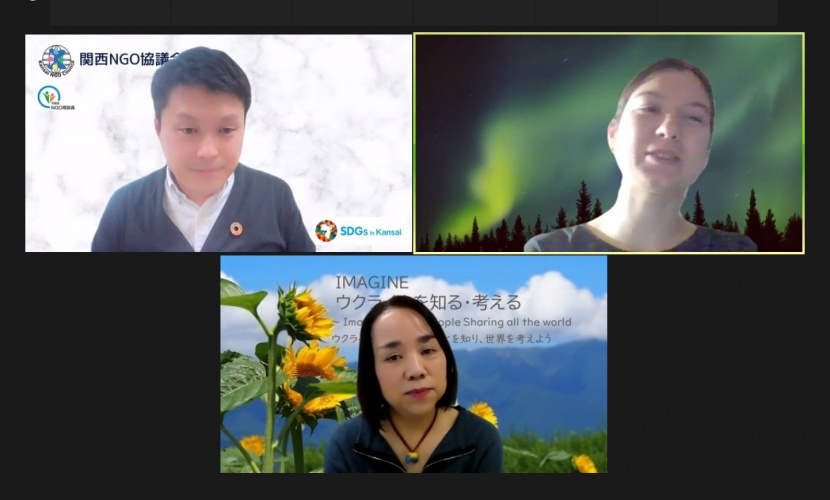Need Help?
Refugee Support
龍谷大学における避難民・難民学生への支援これまでの支援実績(歩み)
龍谷大学は、避難民・難民学生の「学び」と「生活」を支えるため、これまで多くの支援に取り組んできました。経済的な支援から、交流を通じた心のサポートまで、学生一人ひとりに寄り添う姿勢を大切にしています。このページでは、これまでに行ってきた支援の歩みを、News記事とともにご紹介します。
学生受け入れ・生活支援
ウクライナの学生受入れ(第二段階) 「日本・ウクライナ大学パスウェイズ」の枠組みを通じてウクライナから5名を留学生として受入れ
日本・ウクライナ大学パスウェイズとの連携により、5名のウクライナ避難学生を正式に受け入れ。入試制度を特別枠で設置し、奨学金、住居支援、日本語教育、アルバイト支援などを展開。長期的な学びと生活の安定を図っています。
留学生バディの活動について
日本人学生とウクライナ・シリアからの留学生が1対1で支援・交流する「バディプログラム」の活動記録。生活面のサポートに加え、言語や文化を共有する機会としても機能しています。互いに学び合う関係が築かれています。
ウクライナの学生受入れ(第一段階)京都市と「オール龍谷」で歓迎(2022年5月13日)
龍谷大学は京都市と連携し、キーウ大学から来日したウクライナ人学生を迎える第一段階の受け入れを実施。グローバル教育推進センターが中心となり、住まい・生活用品の提供、学生バディ制度など、大学全体で支援体制を整えました
募金・人道支援
本学からの寄付を活用して、キーウ国立大学「日本語・日本文学教育研究室」が完成(2023年5月1日発表)
龍谷大学からの寄付金により、キーウ国立大学に「日本語・日本文学教育研究室」が新設されました。日本語教育の継続・発展を支援し、戦禍の中でも学びが守られるよう連携。教育的復興支援の一環として注目されました。
入澤学長からウクライナ人留学生へ支援金を授与(2022年9月30日発表)
龍谷大学に受け入れられたウクライナ人留学生に対し、入澤崇学長から直接支援金が手渡されました。言葉だけでなく、具体的な金銭的サポートによって、学生たちの安心した学びと生活を後押ししました。
ウクライナ支援募金活動で集まった募金を大学に贈呈(2022年6月15日発表)
龍谷大学内で行われた「ウクライナ人道支援募金」により集まった寄付金を大学代表がウクライナ大使館などに贈呈。教職員・学生の協力のもと、平和への願いを具体的な支援に変える活動となりました。
ウクライナへの人道支援のための募金を開始(2022年3月11日発表)
龍谷大学は学生団体、同窓会、保護者会と連携し、ウクライナ全土およびキーウ大学への人道支援を目的とした学内募金キャンペーンを開始。寄付金はキーウ大学へ直接送金されるとともに、UNICEF、UNHCR、ウクライナ大使館などを通じて広く人道支援に活用されます。
学術・啓発イベント
“映像ジャーナリストが見たウクライナのいま”綿井健陽氏による講演会を実施(2022年6月2日発表)
戦場取材の第一人者・綿井健陽氏を招き、報道現場から見たウクライナの現状について講演。映像や現地証言を交えたリアルな話に、学生たちからも多くの質問と感想が寄せられました。
公開研究会・シリーズ「戦争と犯罪」まとめ(2022年5月29日発表)
ウクライナ侵攻をめぐる法的・倫理的な問題を考察する研究会を開催。国際人道法や戦争犯罪に焦点をあて、法学・政治学・宗教の専門家が登壇。市民や学生も参加し、社会的な視点で学びを深めました。
IMAGINE ウクライナを知る・考える ~ Imagine all the people Sharing all the world ~(2022年4月1日発表)
開戦直後に開催された緊急企画。ウクライナの歴史・文化・戦争の背景などを多角的に紹介し、展示やトークを通じて理解を深めました。
RYUKOKU CINEMA 特別企画「ウクライナ情勢を知る映画紹介とミニレクチャー」(2022年3月24日発表)
ウクライナの現状を伝える映画を上映し、教員による情勢解説を行う教育イベント。多くの学生が参加し、戦争の現実や人権問題について深く考えるきっかけとなりました。
文化交流・平和活動
ウクライナの味をキャンパスで!クッキングを通じた国際交流イベント(2025年6月19日)
瀬田キャンパスで実施された、ウクライナ料理を作りながら異文化理解を深めるイベント。ウクライナ人留学生が講師となり、現地の食文化や生活についても語られました。料理を通じた国際交流の温かい場となりました。
平和を願ったお守り人形作りで復興支援イベント実施(深草キャンパス)(2023年7月19日)
平和と復興を祈るために、伝統的な「お守り人形モタンカ」を手作りするイベントを開催。学生・教職員・地域の方が一体となり、心を込めた支援を形にしました。ウクライナ文化への理解を深める機会にもなりました。
ウクライナのお守り人形を一緒に作ろうイベント実施(大宮キャンパス)(2023年7月5日)
大宮キャンパスで実施された同様の人形づくりイベント。宗教文化や伝統工芸の視点からも学べる内容で、キャンパスを超えた共感と支援の輪が広がりました。
龍谷大学付属平安高等学校でウクライナ留学生を招いて講演会を実施(2022年9月28日発表)
ウクライナ人留学生を講師として招き、高校生向けの特別講演を実施。戦争体験や祖国の現状、文化について語られ、生徒たちは直接的な声に触れる貴重な学びを得ました。若い世代へ国際理解を広げる取り組みです。