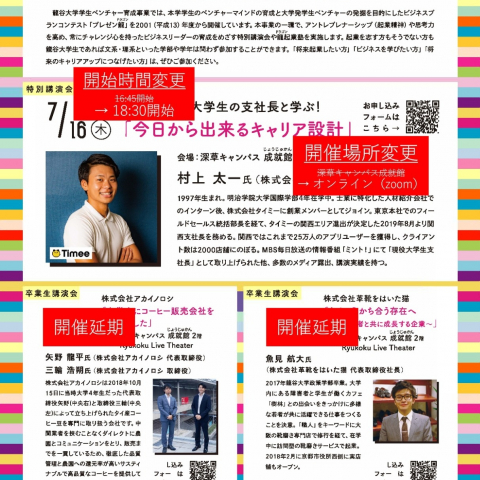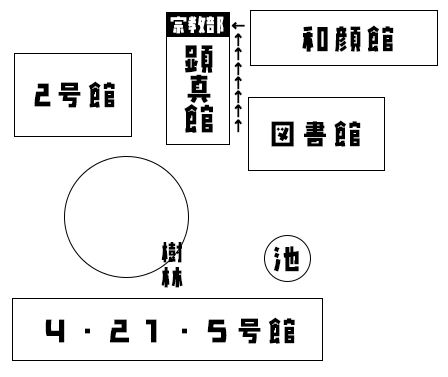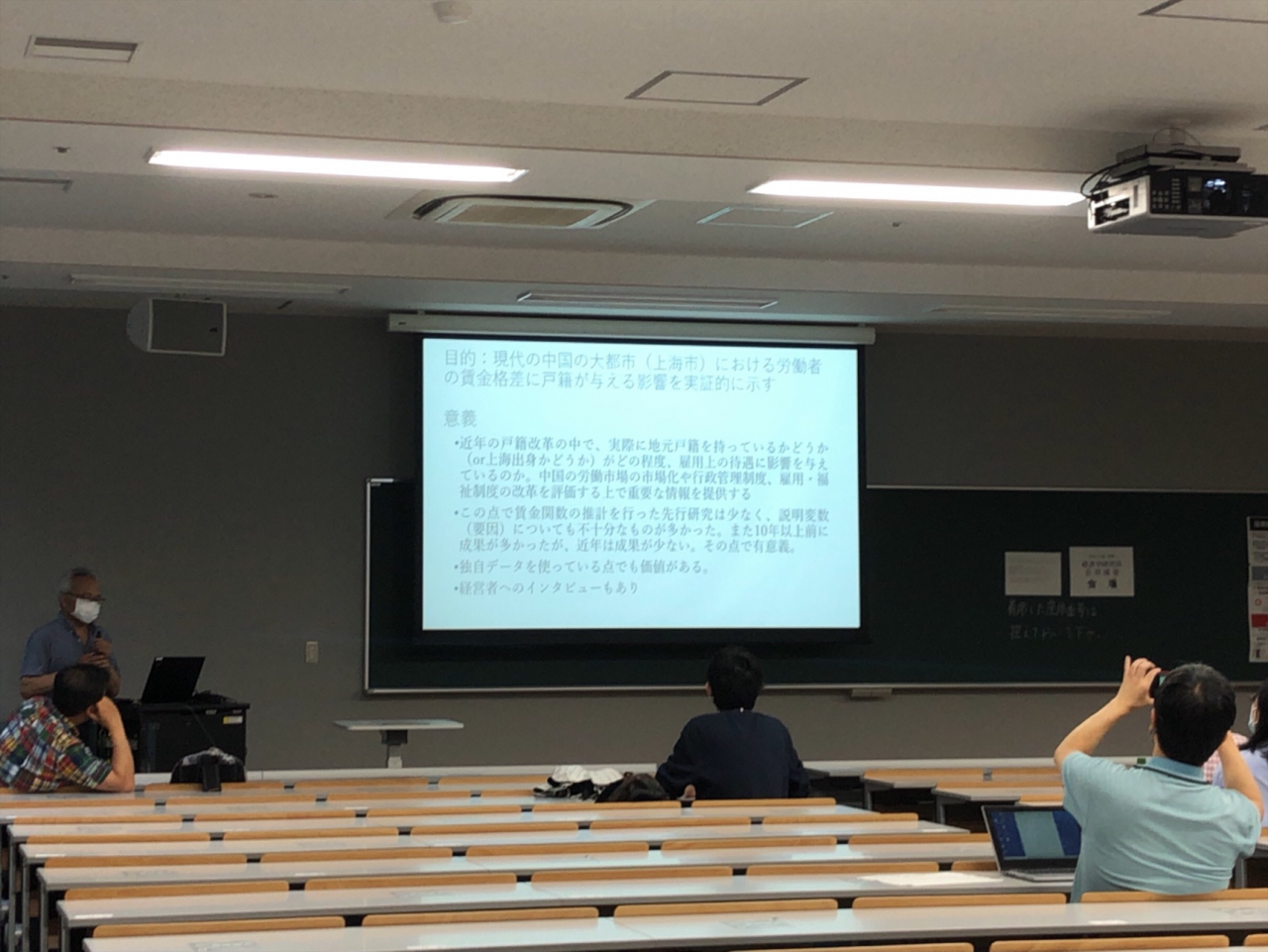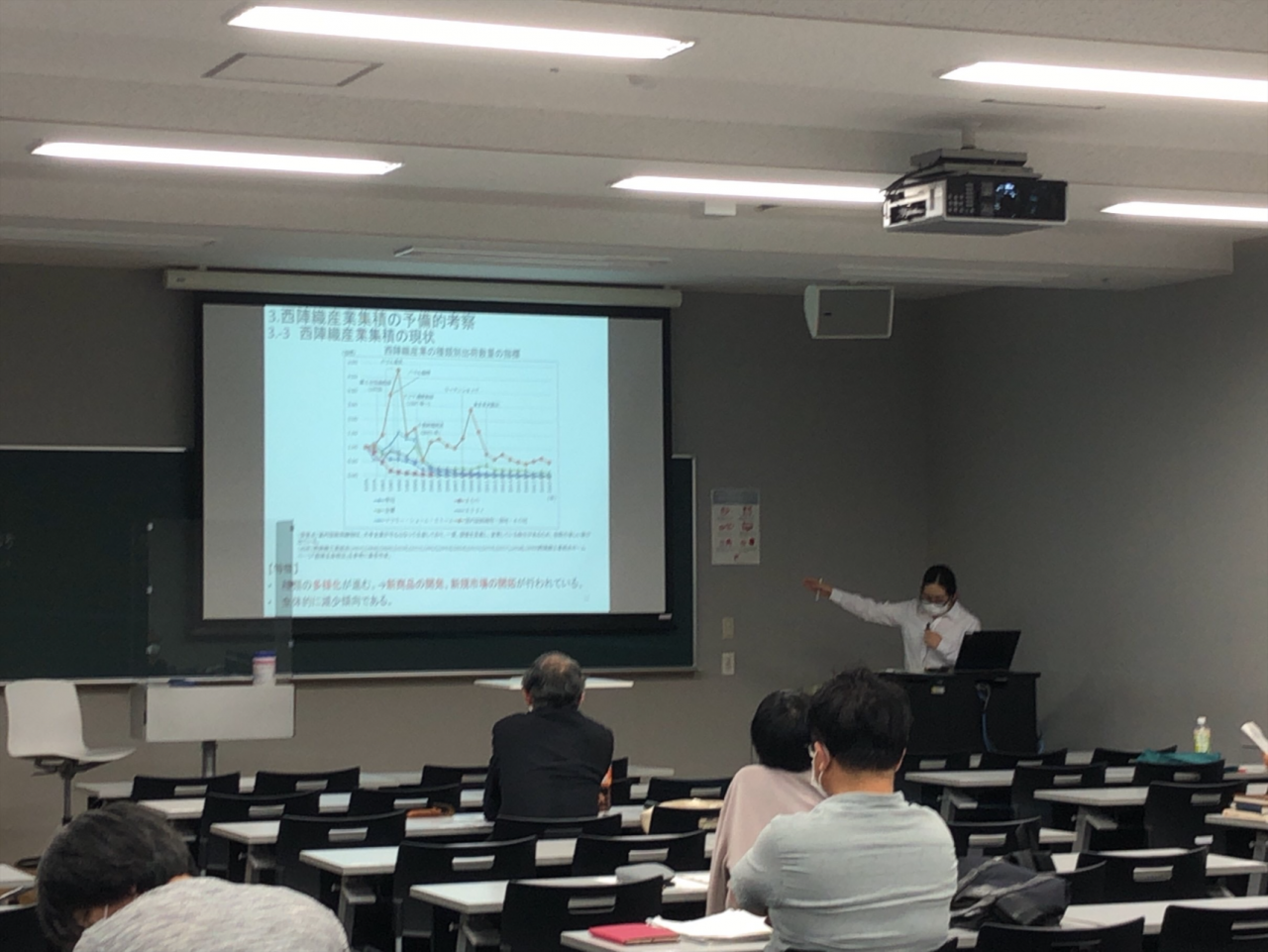REC設立30周年記念事業 三井住友信託銀行提供龍谷講座『今から考える相続対策』~ポストコロナにおける人生100年時代に向けて~を開講 【無料】【REC滋賀】
今年度初めて、REC設立30周年記念事業として、三井住友信託銀行様に龍谷講座をオンライン講座としてご提供いただきます。
一生をかけて築き上げられた財産や、ご先祖様から引き継いでこられた資産も、いずれは「相続」という形でご自身の大切な方へ引き継がれていきます。
大切な財産を守り、次の世代に引き継いでいくために、今から考えておきたい相続や遺言のことについて西川 尚毅氏(三井住友信託銀行京都支店上級主席財務コンサルタント)に詳しく解説いただきます。
REC設立30周年記念事業
三井住友信託銀行提供 龍谷講座
『今から考える相続対策』オンライン講座【受講料無料】(定員70名)
~ポストコロナにおける人生100年時代に向けて~
講師:三井住友信託銀行京都支店 上級主席財務コンサルタント 西川 尚毅 氏
☆7月31日(土) 14時~15時 <ライブ配信>
☆8月 6日(金)~9月3日(金 ) <オンデマンド配信>(予定) 期間中何度でもご視聴いただけます。
(講座のご紹介動画)
(お申込みサイト)