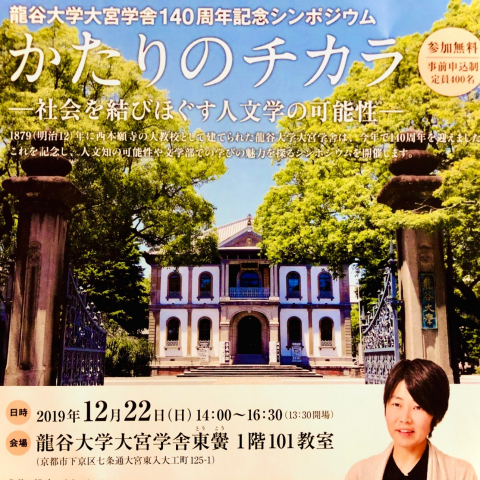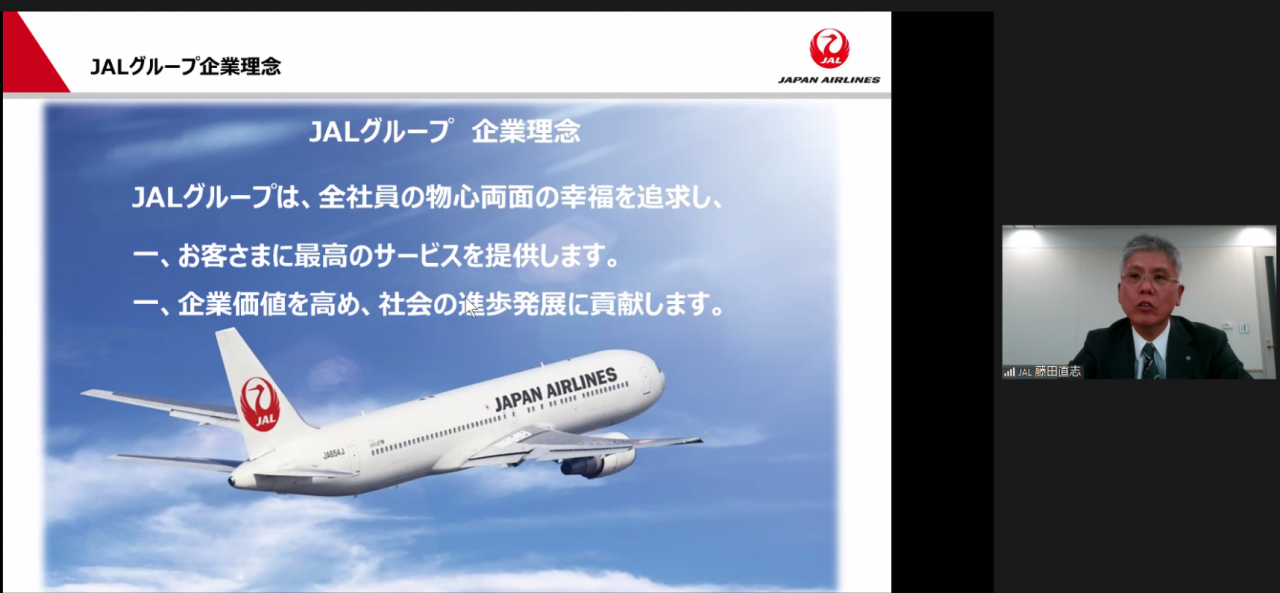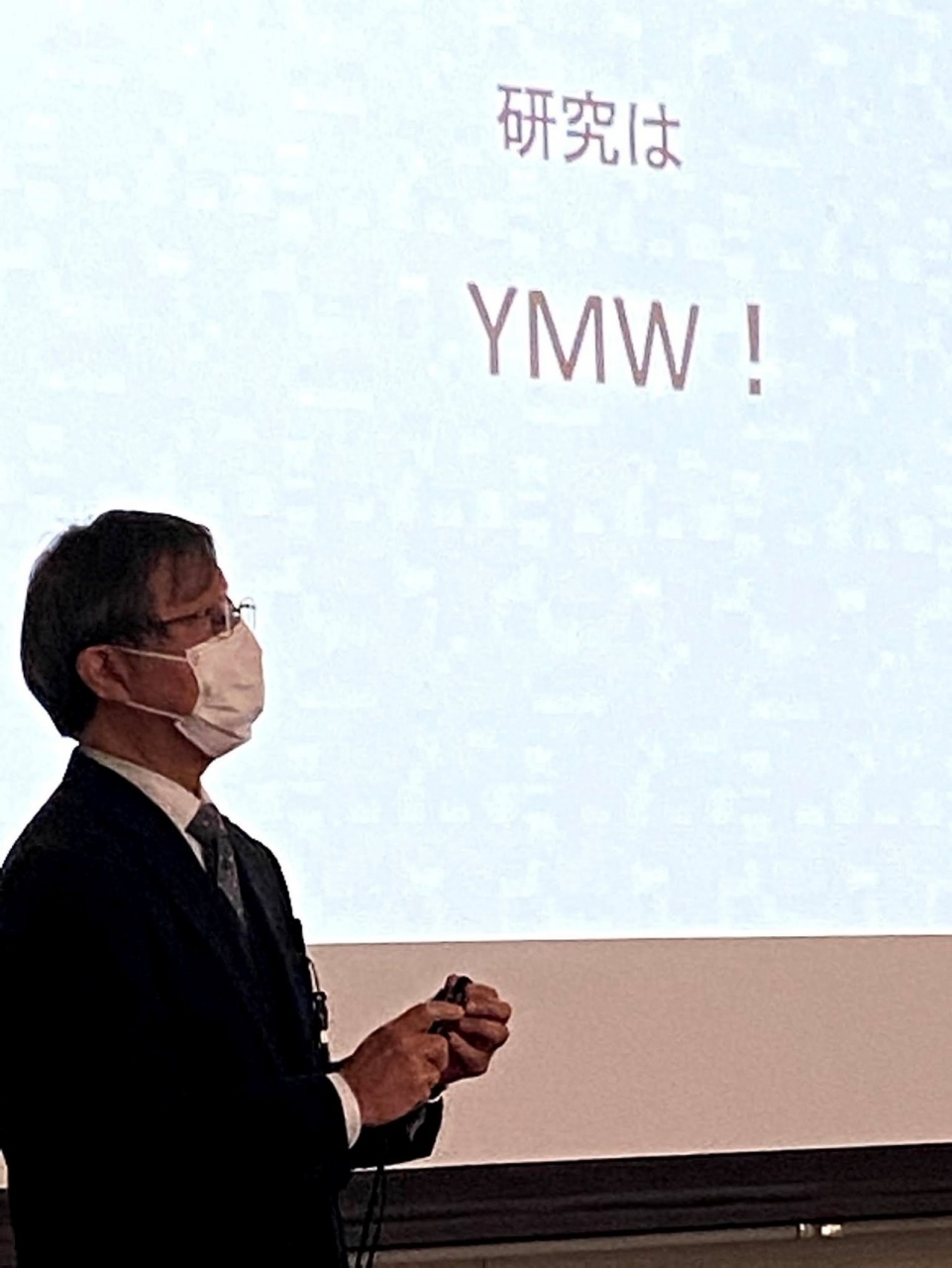実践真宗学研究科進学ガイダンス(1月14日)開催ご案内【文学部】【実践真宗学研究科】
実践真宗学研究科では、春期入学試験の受験を検討しているみなさんを対象とした進学ガイダンスを、開催いたします。
ホームページにて、実践真宗学研究科紹介動画も掲載しておりますので、ご覧ください。
是非、実践真宗学研究科の受験を検討をいただきますようにお願い致します。関心のある方は、文学部教務課(大宮)までお電話いただきますようにお願いいたします。
<実践真宗学研究科進学ガイダンス>
1 オンラインによる進学ガイダンス
日 時: 2021年1月14日(木) 12時30分~13時10分
質問方法: オンラインにてご説明をいたします。お気軽にお越しください。
参加方法: こちらから参加ください Zoomミーティングに参加する
2 実践真宗学研究科合同研究室開放日
日 時: 2021年1月14日(木)~1月15日(金) 12時30分~17時00分
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催できない場合は、お知らせいたします。
<実践真宗学研究科ホームページ>
URL 実践真宗学研究科ホームページ にてご確認ください。
<実践真宗学研究科 紹介動画>
URL 実践真宗学研究科 紹介動画
・設置趣旨と3つの特徴
・大学院生の活躍と修了生の進路先
・Voice 院生の声 ~臨床実習を終えて~
<実践真宗学研究科 入学試験情報>
〇 春期試験(一般入試・社会人入試・指定校入試)
・出願期間:2021年1月6日(水)~1月22日(金)
・試 験 日:2021年2月21日(日)
・合格発表:2021年2月27日(土)
〇学内進学奨励給付奨学金申請期間
申請期間1月6日~1月12日
※文学部教務課(大宮)へお問い合わせください。
<実践真宗学研究科チャンネルについて>
実践真宗学研究科に所属している大学院生がHPやパンフレットの+αの大学院の情報をYouTubeにて発信しています。よろしければご覧ください。
YouTube 実践真宗学研究科チャンネル