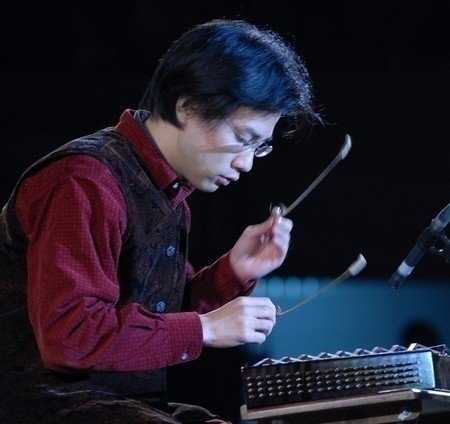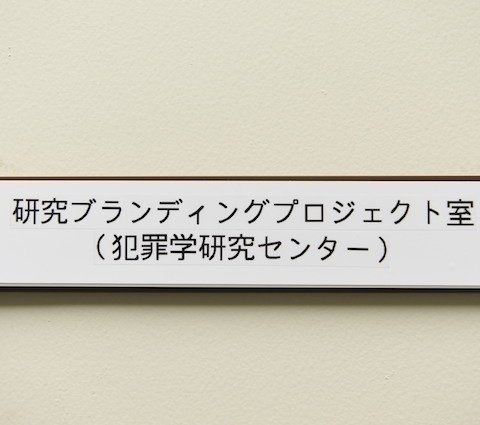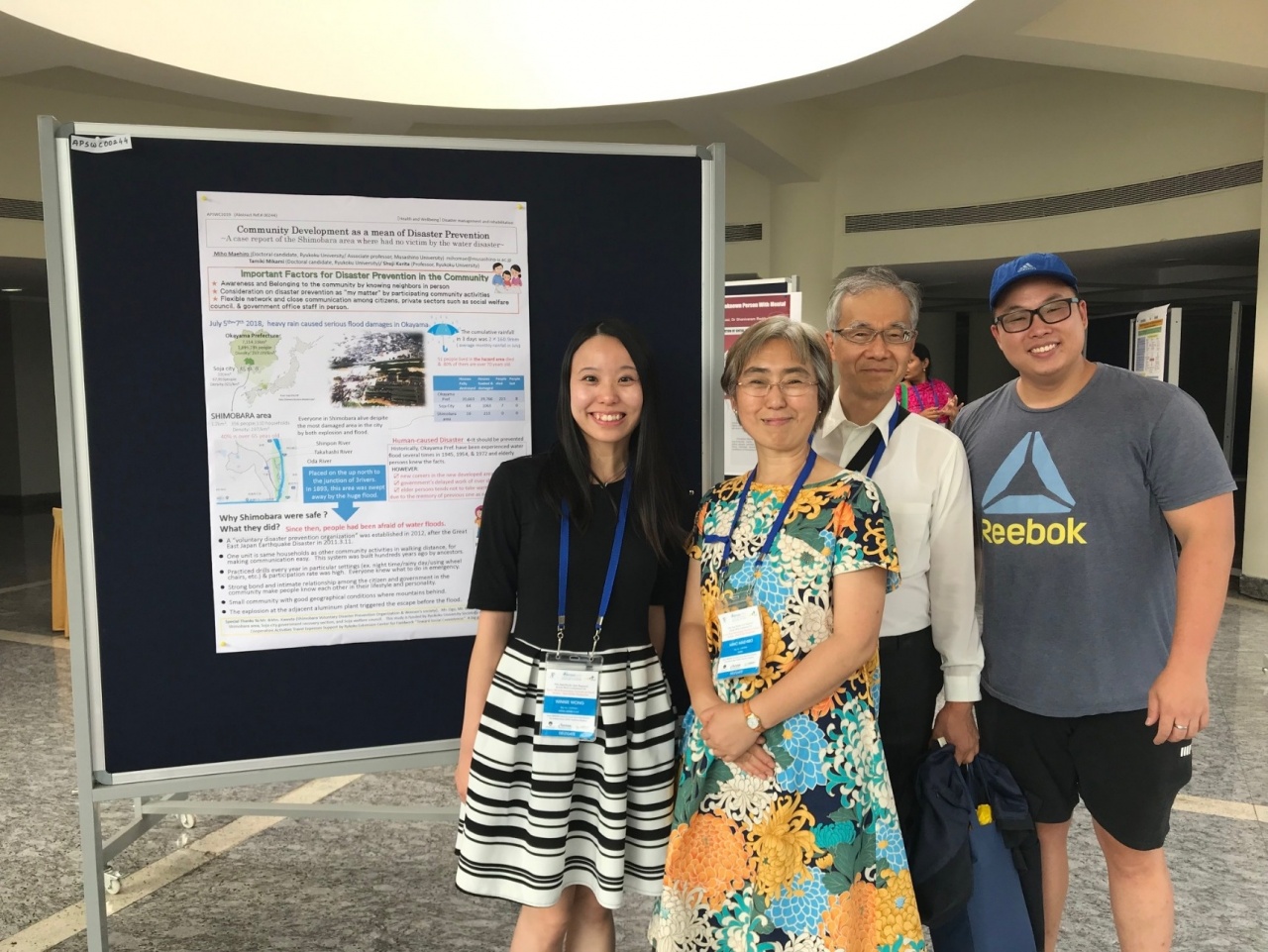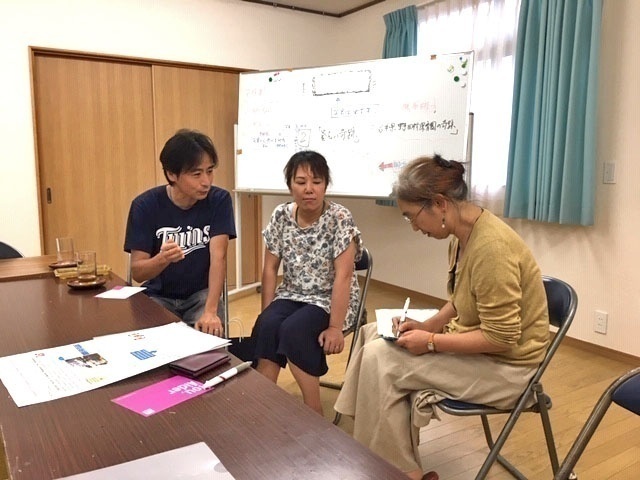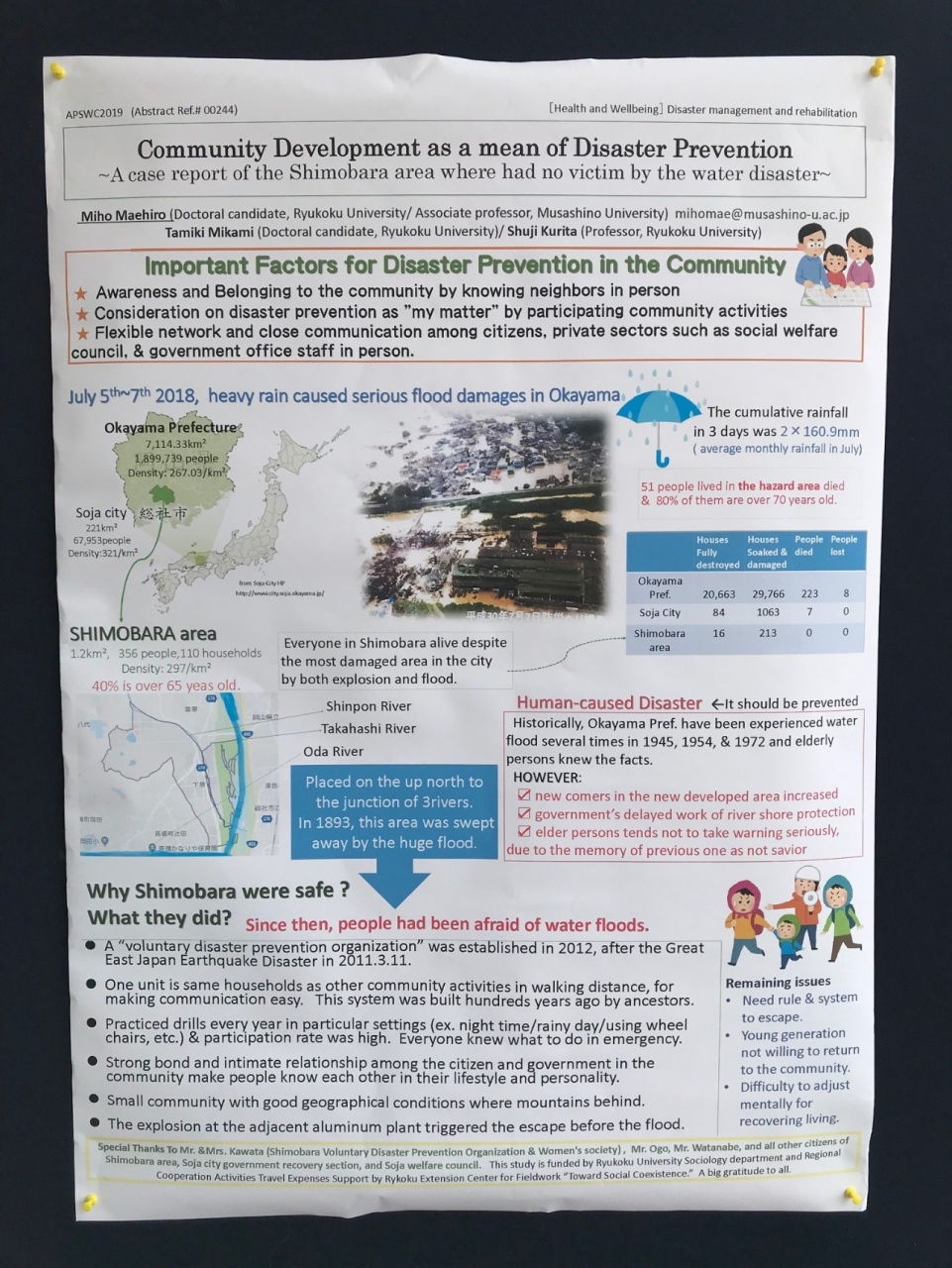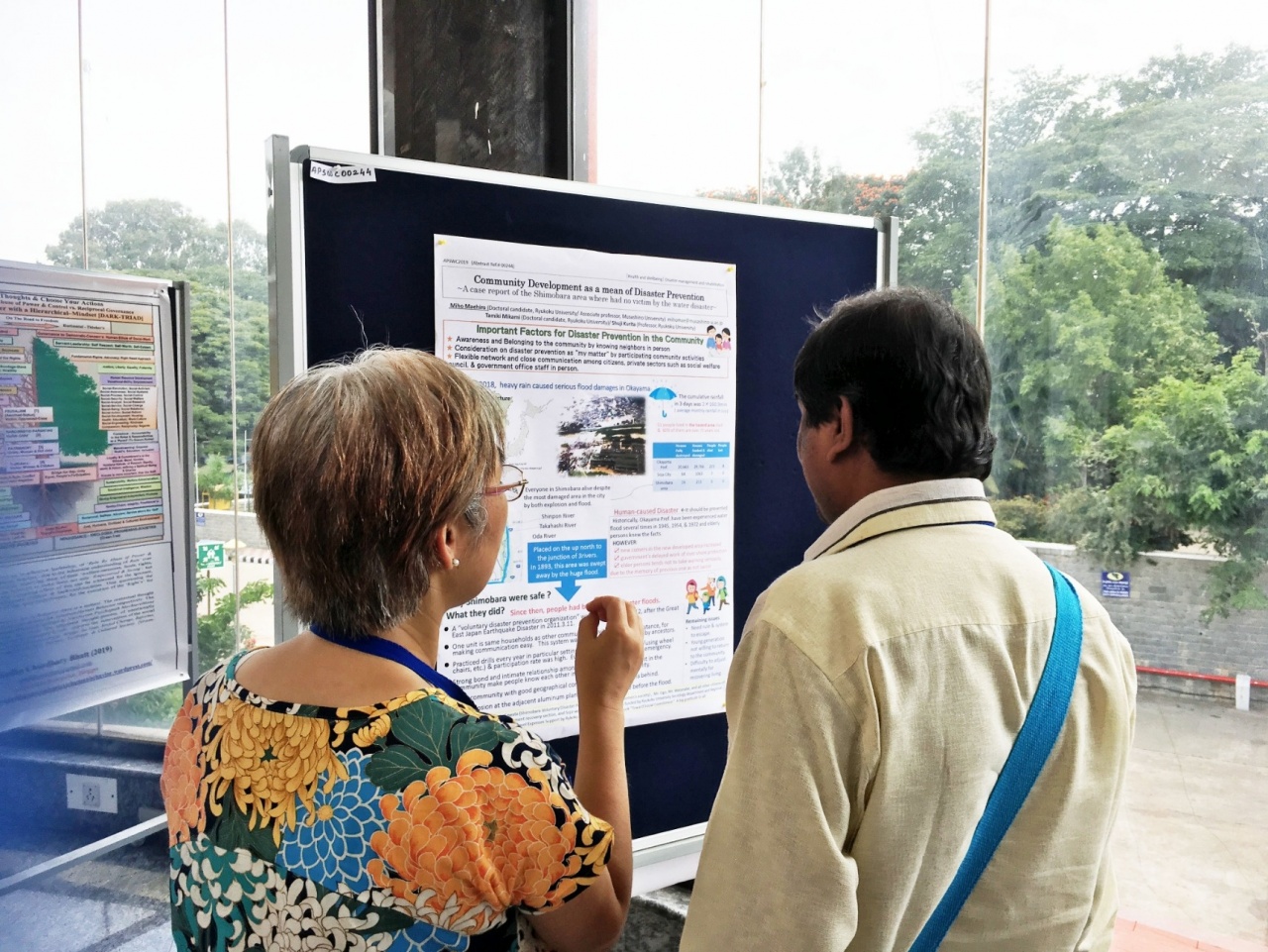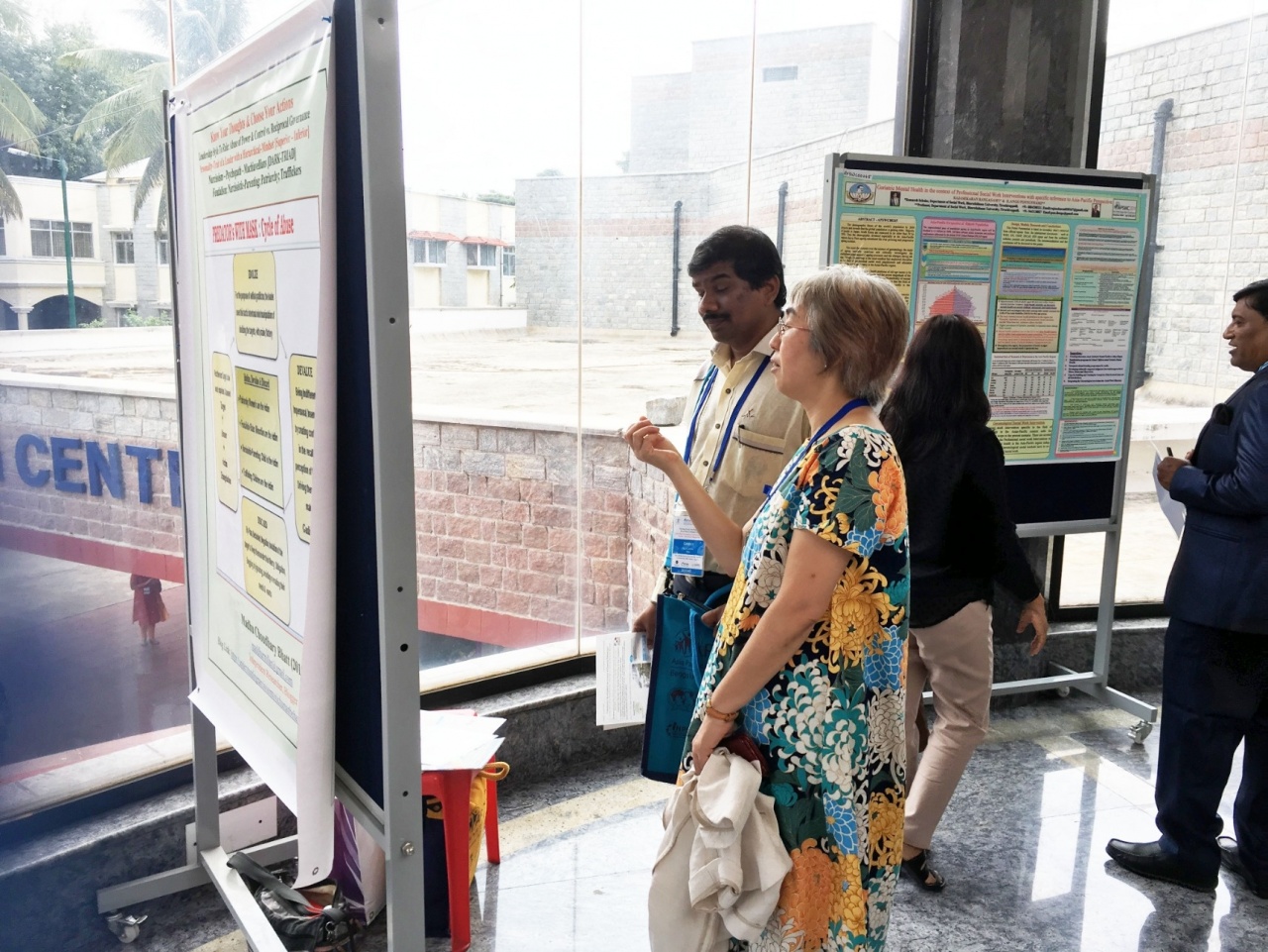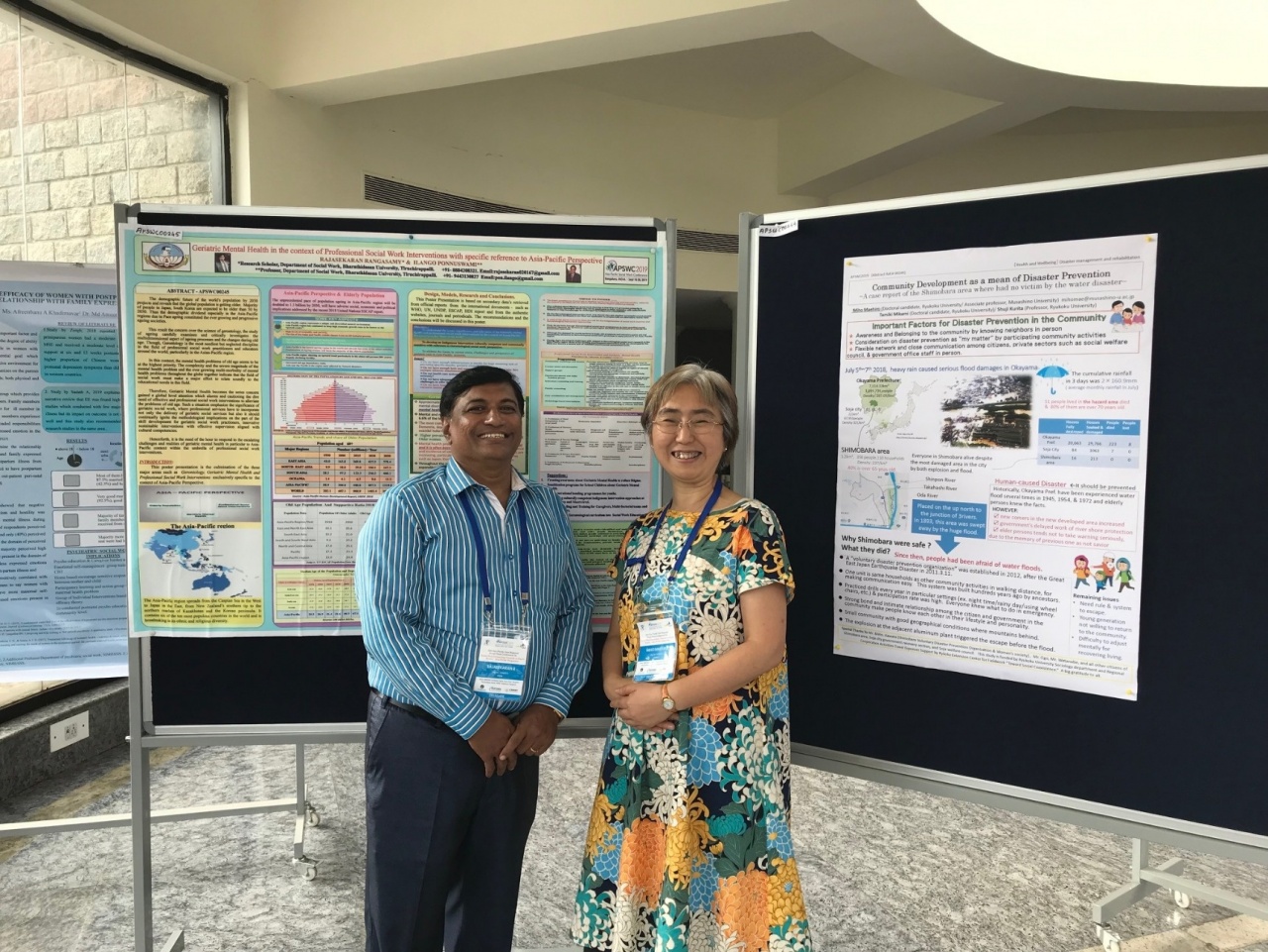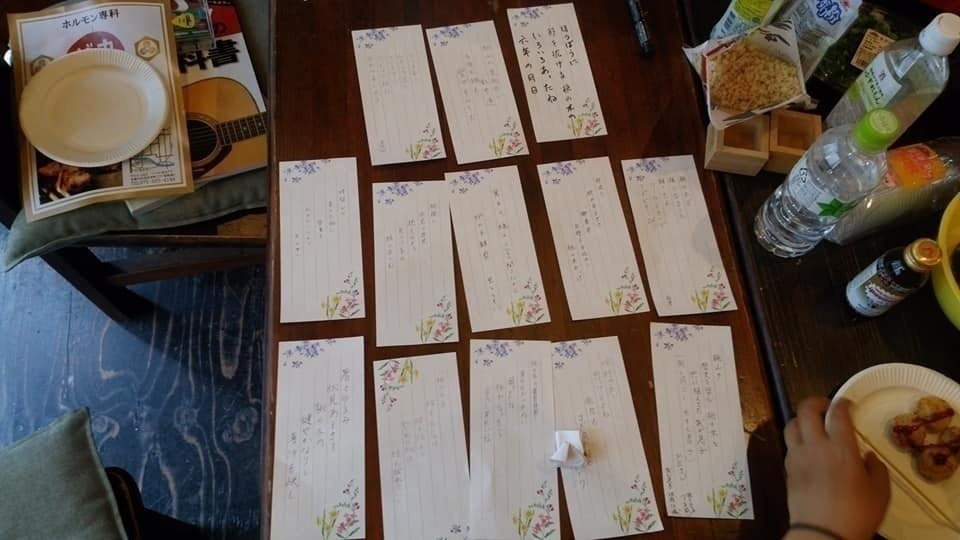龍谷大学法情報研究会 「未公開刑事司法記録研究会」【犯罪学研究センター協力】
【ご案内(10/10 AM9:45更新)】
台風19号の接近に伴い、今回の研究会を中止いたします。
法情報研究会は、犯罪学研究センターの「法教育・法情報ユニット」メンバーが開催しているもので、法情報の研究(法令・判例・文献等の情報データベースの開発・評価)と、法学教育における法情報の活用と教育効果に関する研究を行なっています。毎回、法や社会問題をテーマに多様な分野の専門家を講師に迎え、参加者との活発な議論が行われています。
下記の通り、研究会を開催しますのでご案内します。
龍谷大学法情報研究会
「未公開刑事司法記録研究会」
日時:2019年10月12日(土)13:30~16:00 (入場無料・予約不要)
会場:株式会社TKC 東京本社2階研修室(東京・飯田橋)[>>Link]
住所:東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル2F
[>>Google Map]
テーマ:「刑事確定訴訟閲覧裁判の現状と課題」
報告者:澤康臣(共同通信)、清永聡(日本放送協会解説委員)、大貫挙学(佛教大学)ほか/*敬称略
※報告者には、現在取り組まれている刑事確定記録公開訴訟の実践をそれぞれ20分程度報告していただき、その現状と課題をみんなで考えたいと思います。
主催:龍谷大学法情報研究会
協力:株式会社TKC、龍谷大学犯罪学研究センター
<本研究会の開催にあたっては、龍谷大学社会科学研究所共同研究「刑事未公開記録の保存と公開に関する綜合的研究」からご支援をいただいております>