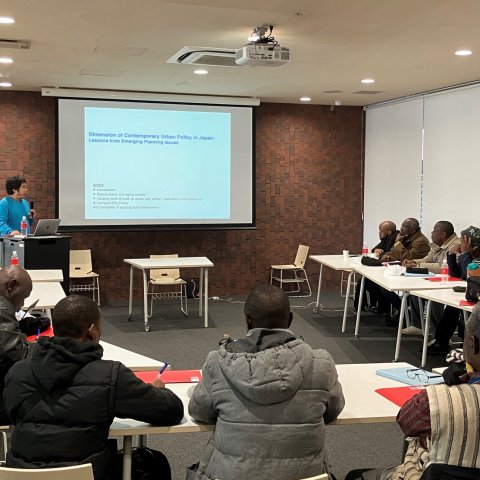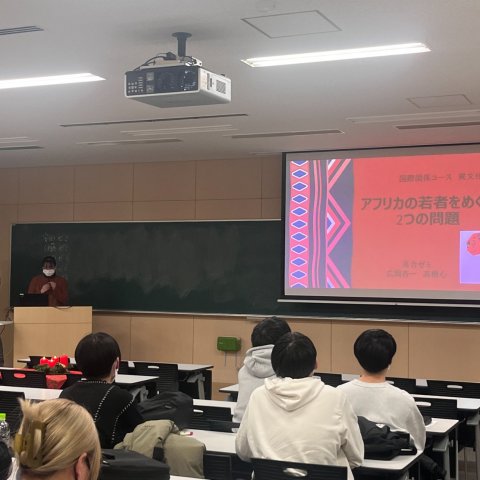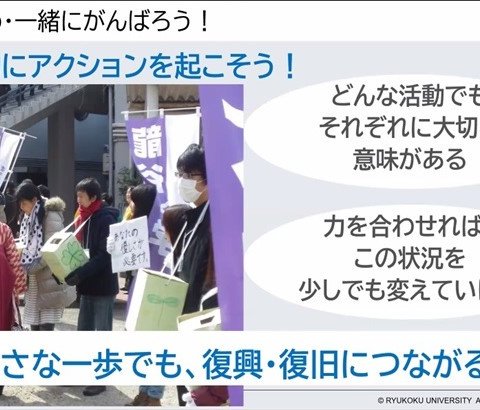2024年度第1回沼田奨学金 研究奨学金授与式を開催【R-Globe】
4月24日(水)、沼田奨学金研究奨学金授与式を執り行いました。沼田奨学金とは、精密測定機器総合メーカー㈱ミツトヨの経営者であった故沼田恵範氏より、寄贈を受けた㈱ミツトヨの株式の果実(配当)によって、1992年度より運用されている奨学金です。
本奨学金は、仏教学術振興に資するための研究・調査に携わる外国人(研究奨学金)や、仏教を専門的に学んでいる成績優秀な留学生(学業奨学金)を支援するために設立されています。
この度の授与式では、San Tun(サン トゥン)氏、兪悧 (ユ リ)氏、金 天鶴 (キム チョンハク)氏の3名が受賞されました。受給研究者からは、研究の内容が紹介されました。入澤学長からは、沼田恵範氏の思いを継ぎ、仏教の学術振興や海外伝道に貢献することとともに、仏教研究での更なる学術交流への期待が祝辞として述べられました。
〈受給者の略歴〉
・San Tun(サン トゥン)氏
Dhammaduta Chekinda University(ダンマドゥータ・チェーキンダ大学) 仏教哲学科教授
Dagon University(ミャンマー国立ダゴン大学) 哲学科教授・同科長
研究テーマ 「仏教における身体と環境の哲学―『転法輪経』と『無我相経』を中心に」
受入教員 三谷 真澄 教授(文学部)
・兪悧(ユ リ)氏
慶尙國立大學校 博士課程修了
研究テーマ 「唯識哲學におけるvijñaptiとākāraの関係研究 -『唯識二十論』と『観所縁緣論』
を中心に-」
受入教員 早島 慧 准教授(国際学部)
・金 天鶴 (キム チョンハク)氏
東国大学校教授
研究テーマ 「『華厳経問答』の総合的研究」
受入教員 野呂 靖 准教授(心理学部)