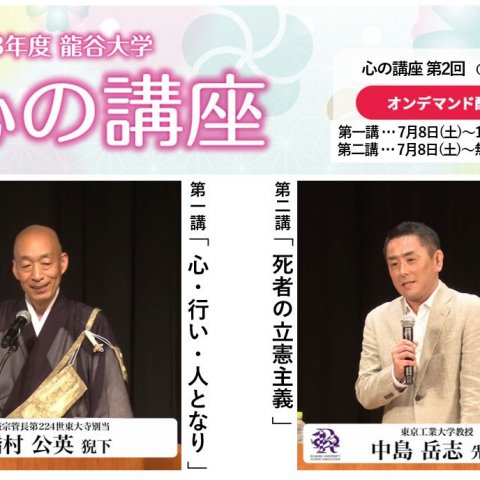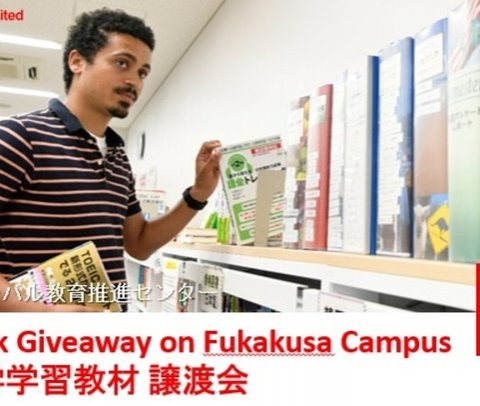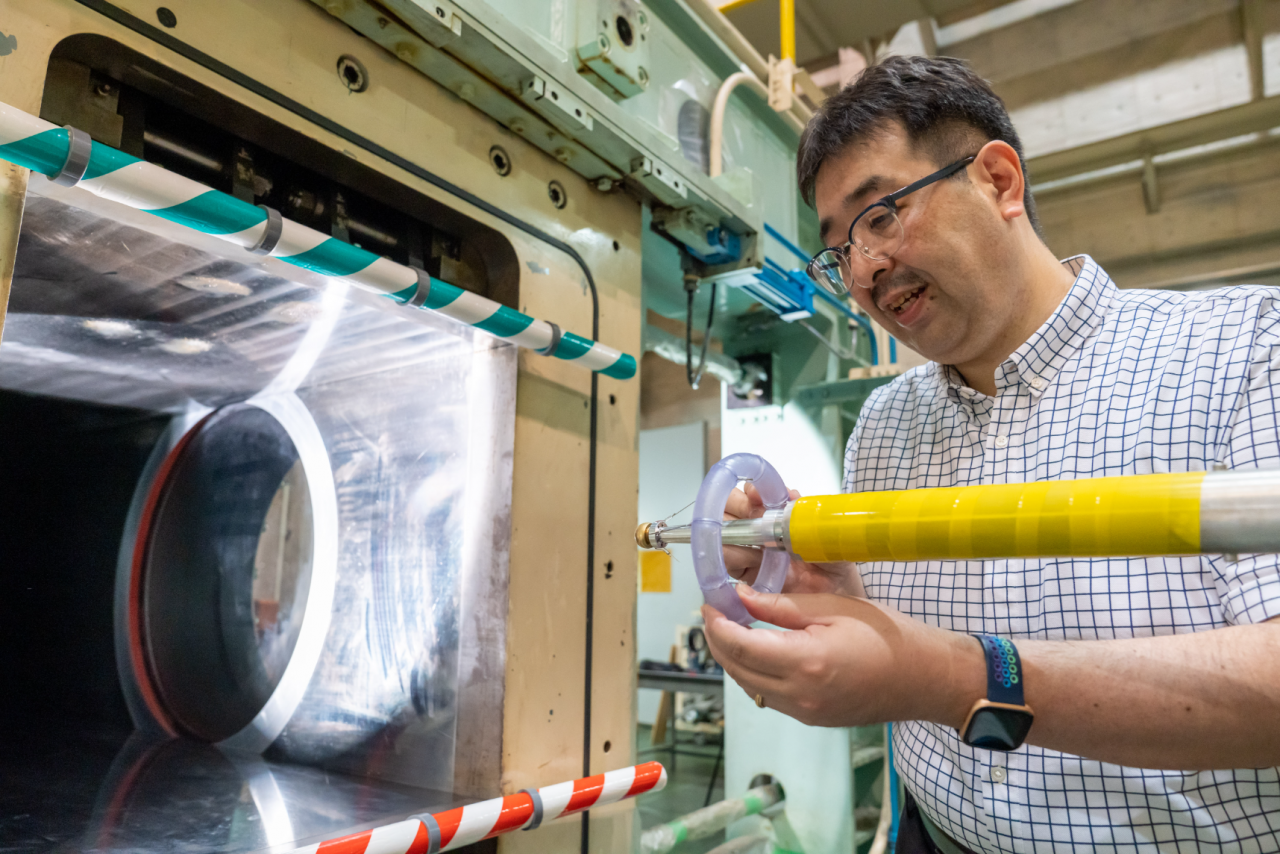第4回オンライン高校生文学模擬裁判選手権
1 本大会のねらい:
①模擬裁判に取り組む高校生の交流を図る。
②人間や社会への眼差しを深める文学模擬裁判を味わう機会を提供する。
2 日時場所
日時:2023年12月17日(日) 9:30-16:30(終了見込)
法廷:札埜研究室のZoom(
4法廷で実施)および各自宅、学校(ZOOM)
3 出場校(7校・1団体)
宮城県宮城野高等学校(宮城)
中央大学杉並高等学校(東京)
神戸女学院高等学部(兵庫)
神戸海星女子学院高等学校(兵庫)
創志学園高等学校(岡山)
済美平成中等教育学校(愛媛)
愛光高等学校(愛媛)
九州高校生有志連合チーム
4 競技方法
参加校は予め配布される文学教材シナリオや関連資料をもとに、参加校が検察側・弁護側どちらかの立場に立って立証・弁護活動を行う。シナリオ創造型の模擬裁判である。
参加校は決められた時間に従い、立証・弁護活動を行い、審査員がそれらの内容を評価して、その総合点で勝敗を決める(検察側、弁護側どちらになるか、あるいは競技方法の詳細については締め切り後に連絡する)。得点の高い順から優勝校・準優勝校を決める。
5 採点基準
読解力、人間や社会への洞察力、論理性、表現力等の視点から採点する。
6 各チーム人員
1試合に必要な生徒数は、検察側・弁護側いずれの立場でも最低3名とする。
(証人役、被告人役は生徒が行う。検察官役、弁護人役の生徒は証人役あるいは被告人役を兼ねることはできない)
7 当日のスケジュール予定
9時30分 Zoom入室開始(各自宅等でスタンバイ)
9時40分 開会式、出場校紹介、選手宣誓
10時00分 対戦校及び立場(検察側・弁護側)の発表、各法廷Zoomへ移動
10時30分 第1試合開始
12時20分 第1試合終了
12時20分 昼休憩
13時20分 第2試合開始
15時10分 第2試合終了
15時40分 講評
16時10分 成績発表、表彰式
16時30分 大会終了、振り返り交流会
※試合状況により、時間変更の可能性あり。
8 問い合わせ
〒600‐8268 京都市下京区七条通大宮東入大工町125‐1
龍谷大学大宮キャンパス西黌129号室
札埜研究室 宛 TEL 075‐343‐3326(研究室直通)
E-mail:
fudafuda@let.ryukoku.ac.jp
主催:龍谷大学札埜研究室・オンライン高校生文学模擬裁判選手権実行委員会
後援:龍谷大学犯罪学研究センター、京都教育大学附属高等学校模擬裁判同窓会、
刑事弁護オアシス、
一般社団法人刑事司法未来、
龍谷大学矯正・保護総合センター、龍谷大学法情報研究会
*この取組はJSPS科研費(課題番号「20K02809」)「国語科の視点を取り入れた新科目『公共』で活用可能な模擬裁判メソッドの研究開発」基盤(C)(一般)の助成を受けています。
[今大会に参加する高校生のための事前学習にご協力いただいた講師陣(50音順)]
石塚 伸一 氏 (刑事司法未来代表、龍谷大学名誉教授、立正大学客員教授)
伊東 隆一 氏 (京都弁護士会・弁護士)
後藤 貞人 氏 (大阪弁護士会・刑事弁護人)
鈴木 聡 氏 (銅版印刷株式会社・代表)
遠山 大輔 氏 (京都弁護士会・弁護士)
野本 和宏 氏 (月形町教育委員会・主幹・学芸員)
山田 悦子 氏 (冤罪被害者・甲山事件)
若佐 一朗 氏 (大阪弁護士会・元検察官、弁護士)
*聴講希望のかたは札埜研究室のメール( fudafuda@let.ryukoku.ac.jp )までお問合せください。