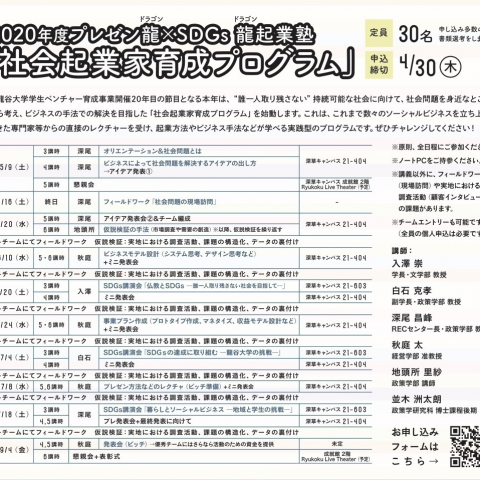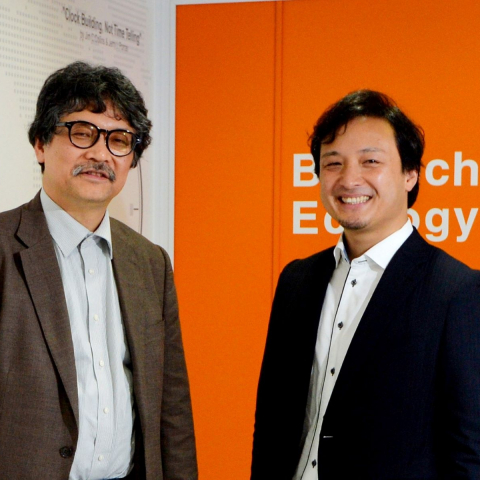【龍谷コングレス2021】龍谷コングレス「龍谷・刑事政策構想」発表 市民のための刑事政策構想〜人に優しい刑事政策をめざして〜/犯罪学研究センター主催
龍谷大学 犯罪学研究センターは、下記イベントを6月21日(月)に主催します。
【>>お申込みページ】
※お申し込み期限:6月21日(月)17:30まで
龍谷コングレス2021
〜人に優しい犯罪学の過去・現在・未来〜
市民のための刑事政策構想〜人に優しい刑事政策をめざして〜
〔企画の趣旨〕
2016年6月に発足し、同年11月に「文部科学省・私立大学研究ブランディング事業」に採択された龍谷大学 犯罪学研究センターは、2021年度をもって一連の事業計画が完了します。そこで、アジア犯罪学会 第12回年次大会(ACS2020)の開催に合わせ、「龍谷・刑事政策構想(第1次案)」を発表します。
この構想は、当センターが有する13もの研究ユニットがこれまでに積み重ねてきた研究成果をとりまとめたものです。
キーワードは、“つまずき” からの “立ち直り” 。
龍谷大学犯罪学研究センターは、新しい学融領域「人に優しい犯罪学」を提言します。
わたしたちは「社会の防衛」という旧来の犯罪学の関心から一歩ふみ出し、科学的知見に基づく犯罪予防と、地域における伴走型の福祉支援の充実を目指します。
日常生活におけるさまざまな悩みや不安、そして加害・被害の問題に対して、犯罪学はどのような解決策を提示できるのか、社会福祉の向上を目標とする市民参加型のまちづくりの可能性について、多種多様な方々にご参加いただき、意見交換の場をもうけたいと考えています。
今後、学会などにおいて多様な研究者や実務の専門家の意見を聴取し、パブリックコメントを求めるなどして、2021年度末に改めて「龍谷・刑事政策構想(第2次案)」を公表します。
本シンポジウムは、研究者・専門家・学生のみならず、どなたでも参加いただけます。ぜひともご参加ください。
〔こんな方におすすめです〕
・犯罪学はどのような知見を積み重ねているのか興味関心のある人
・『再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)』関係で、地方再犯防止推進計画策定をすすめるためにどこに重点をおけば良いのか悩んでいる人
・『再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)』関係で、実際に矯正・保護の現場で活躍する実務家、保護司、地域定着支援センターのスタッフ
・当事者、支援者、当事者グループのスタッフ
・教育、福祉に関する職に従事している方
・アディクションとどのように付き合えば良いのか悩んでいる人
・子どもの問題、子育てに関心を持っている人
・まちづくりに関心がある人
・ご近所づきあいに疲れている人、どこに悩みを打ち明ければ良いのかわからない人
・犯罪報道(少年犯罪・外国人犯罪・大麻・コロナ関係)を見て不安になっている人
・犯罪や非行に対する市民の安心感を向上させるためには何が必要であるか知りたい人
〔プログラム〕
- 開会挨拶
- 報告:「市民のための刑事政策構想〜アンティ・京都コングレス〜」
- 発表:研究部門12ユニットによるテーゼ
司法心理、司法福祉、矯正宗教、治療的司法、犯罪社会学・社会調査、法情報・法教育、実証研究、法科学、保育学、ヘイトクライム、性犯罪、臨床心理など
- ラウンドテーブル・ディスカッション:「人に優しい犯罪学とは何か?」
〔参加費〕無料 /どなたでもご参加いただけます
【>>お申込みページ】
※オンライン参加のためのZoom情報は、お申込み後ご登録のメールアドレス宛に自動配信されます。Zoomの情報を、他に拡散しないようお願いいたします。また、申し込み名とZoomの名前を合わせてください。
主催:龍谷大学 犯罪学研究センター
共催:龍谷大学 ATA-net研究センター | 一般社団法人刑事司法未来
協力:アジア犯罪学会第12回年次大会実行委員会 | 龍谷大学 矯正・保護総合センター 刑事司法未来PJ
【龍谷コングレス2021】龍谷コングレス「龍谷・刑事政策構想」発表 市民のための刑事政策構想〜人に優しい刑事政策をめざして〜/犯罪学研究センター主催 の続きを読む