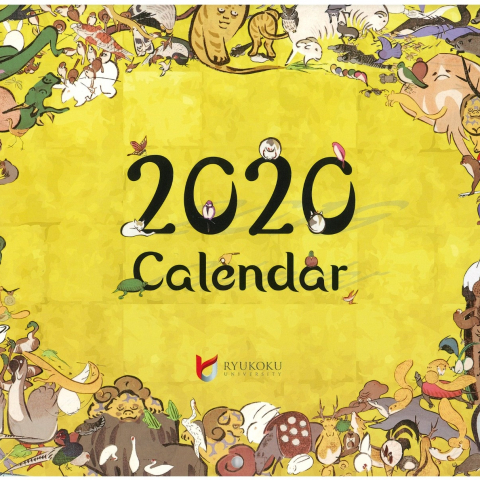文学研究科 大学院進学ガイダンスを開催(臨床)【文学部】【文学研究科】
5月17日(月)に文学研究科の入学試験の受験予定の方を対象に進学ガイダンス(臨床心理学専攻)をオンライン(ZOOM)にて開催いたしました。
國下多美樹 文学研究科長より、開会の挨拶がなされ、文学研究科の魅力について紹介がありました。
引き続き、研究科の概要・入試情報の説明を行った後に、龍谷大学大学院文学研究科修士課程臨床心理学専攻2年生 横山シオンさんから、修士課程での大学院生活について、紹介がありました。
大学院入学後のイメージを掴んでいただけましたか。 今回は、臨床心理学専攻の横山シオンさんに、大学院の生活について、紹介いただきました。文学研究科の案内誌では、他の専攻の学生からのメッセージを掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。
※学内推薦入試の入試要項・出願書類については、ポータルサイトより、入手ください(タイトル:文学研究科・実践真宗学研究科 学内推薦入学試験要項について(2021年4月13日)。