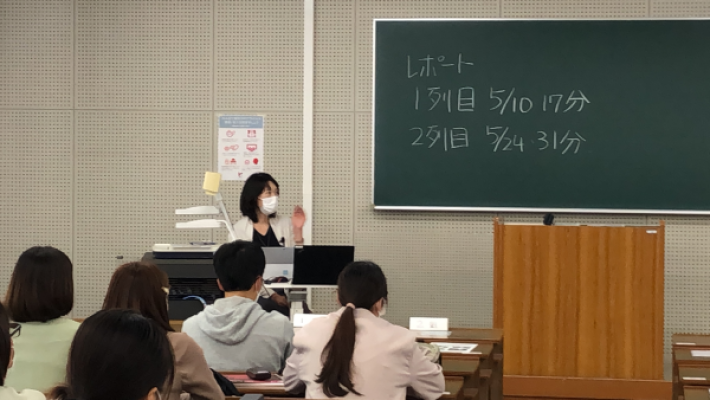ブラウザからレイアウト自由自在
Layout Module
ここにメッセージを入れることができます。

【致各位日本学生及外国留学生】关于海外项目及派遣交换留学等(含自费留学)的对应举措
致各位日本学生及外国留学生 针对海外项目及派遣交换留学等(含自费留学...

Dear Japanese and international students: Information about Ryukok...

センター移転にかかる閉室期間について(深草)【ボランティア・NPO活動センター】
このたび文化系サークル活動等の拠点となる『成就館』の工事が完了し、3...

【法学部在学生のみなさんへ】3月16日履修説明会の中止について
法学部生 各位 2020年3月16日(月)に実施を予定しておりました...

【日本人学生及び外国人留学生のみなさまへ】海外プログラム及び派遣交換留学等(私費留学を含む)の対応について(3月5日発表)
日本人等学生及び外国人留学生のみなさまへ 次の項目に関する海外プログ...

【犯罪学Café Talk】井上 見淳准教授(本学社会学部・犯罪学研究センター「矯正宗教学」ユニット研究員)
犯罪学研究センター(CrimRC)の研究活動に携わる研究者について、気軽...
仏教史学という学科や専攻を設置している大学は日本では他に例がありません。しかし、歴史学科 仏教史学専攻は、龍谷大学ならではの学問領域を専門に学ぶユニークな専攻として長い伝統を有し、幾多の優秀な卒業生を輩出してきました。
仏教史学専攻にご関心がある方は、ぜひ一度、下記アドレスのオリジナル・ホームページ、あるいはPDFファイル「受験生の皆さんへ 龍谷大学で仏教史学を学んでみませんか!」をご覧ください。
URL 龍谷大学歴史学科仏教史学専攻
URL 龍谷大学文学部学科紹介
URL 龍谷大学文学部ホームページ
オンラインにて話し合い研究ユニットの公開研究会が、地域政策学会「イノベーションと話し合い」研究会との共催で開催されました。
研究会では、北海道大学高等教育推進機構准教授の三上直之先生をお招きし、以下のテーマで発表いただきました。
日時:2021年4月22日(木)、18時30分~20時50分
テーマ「完全オンラインによる無作為抽出型の市民会議〜気候市民会議さっぽろ2020の催概要と結果〜」
報告では、近年イギリスやフランスを中心に発達してきた「気候市民会議」を、
札幌市において応用した成果の紹介がされました。気候市民会議は、無作為抽出によって選出された市民が、数週間から数ヶ月かけて気候変動対策について議論するミニパブリックスのことです。
札幌市における気候市民会議は、「札幌市ゼロカーボンシティ宣言」のもと、2050年までに二酸化炭素排出量をゼロにする目標達成のための方策が議題となりました。全4回をオンラインで実施し、取りまとめられた結果は札幌市に提出されました。
会議の結果として、約3分の1の参加者は市の掲げた2050年よりも前段階での温室効果ガス実質排出量ゼロを目指すべきとの考えが示されました。また、脱炭素化に向けた具体策として、住宅メーカーや発電事業者等の製品・サービス供給側の取り組みに期待する意見が多数を占めました。一方で、「自転車の利用」や「脱マイカー」などの項目は、意見の違いや対立がある項目であると示されました。このようなグループは、単に項目に対する支持が低いのではなく、将来的により議論を深化する必要があると指摘されました。
市民会議が求められる背景には、脱炭素社会への転換の必要と、これを実現するために「普通の市民」一人ひとりがどのような社会の姿・暮らし方を選択するべきかについて話し合う方法の模索が挙げられます。気候変動という地球規模、世代を超える問題は、限られた地域の現世代の人々に意識の向く政治家にとっては「票になりにくく」、捨象されがちなテーマです。脱炭素社会への転換には、「民主主義の刷新」を同時に起こす必要に迫られていると指摘されました。
4月21日、英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)社による「THEインパクトランキング2021」の結果が発表されました。龍谷大学は、はじめてこのランキングにエントリーし、総合順位で、世界「401-600位」、日本国内の私立大学では「5位(タイ)」にランクインしました。
THE インパクトランキングは、国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の枠組みを使って、各大学における社会課題解決に資する取り組みを評価する世界的な大学ランキングです。
本学はこれまで、建学の精神である浄土真宗の精神のもと、多様に展開する教育・研究活動を通じて社会的課題の解決に取り組んできました。こうした取り組みは、「誰一人取り残さない」ことを旨とするSDGsの理念と合致するものです。今回のランキング結果から、このような本学の姿勢が世界的に評価されたものと受け止めています。
現在、本学では、創立400周年にあたる2039年に向けた長期計画である「龍谷大学基本構想400」を推進しているところです。そこでは、SDGsと仏教の精神を結びつける「仏教SDGs」という本学独自の視点を踏まえ、学内外の英知を結集し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを加速させていきます。引き続き、本学の取り組みにご注目いただきますようお願いいたします。
国内私立大学順位(1000位まで)
|
総合順位 |
大学名 |
スコア |
| 201-300 | 慶応義塾大学、立命館大学 | 71.0-77.4 |
| 301-400 | 東京理科大学、早稲田大学 | 66.3-70.9 |
| 401-600 | 龍谷大学、帝京大学、東京農業大学、東洋大学 | 56.6-66.2 |
| 601-800 | 中部大学、中央大学、神奈川大学、関西学院大学、上智大学、東海大学、東京都市大学 | 47.6-56.5 |
| 801-1000 | 国際基督教大学、恵泉女学園大学、工学院大学、武蔵野大学、立命館アジア太平洋大学、成蹊大学、芝浦工業大学、創価大学 | 36.5-47.5 |
※総合ランキングの対象となったのは世界1115校
<龍谷大学基本構想400>
https://www.ryukoku.ac.jp/400plan/
【参考】
本学が強みを生かせる分野としてエントリーを行った目標(SDG)は、以下のとおりです。中でも、エントリーした大学の全てに共通して求められる目標(SDG)17における「SDGs教育」において、高い評価を受けています。
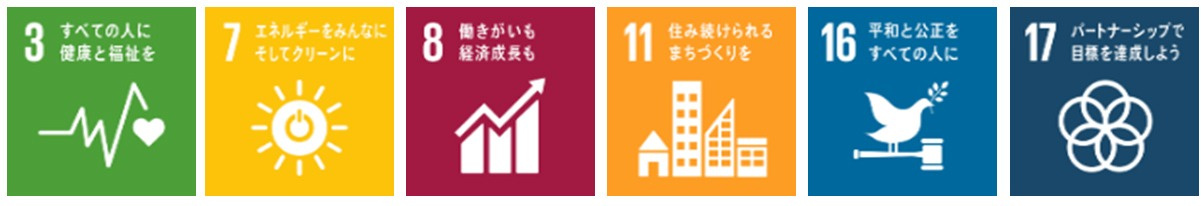
2021年4月26日(月)2講時「基礎演習Ⅱ」において、医療法人悠明会在宅支援いむらクリニック在宅訪問管理栄養士の藤村真依氏を講師としてお招きし、「管理栄養士のキャリア形成ー今後ますます必要とされる在宅訪問管理栄養士ー」と題しご講演いただきました。
藤村先生は、病院の管理栄養士になりたくさんの患者さんと出会う中で、「病院管理栄養士は患者さんの退院をゴールにしてきたが、患者さんにとっては退院した日からがスタートである」ことを気づかされ、在宅訪問管理栄養士の道に進んだ経緯をお話しいただきました。さらにその中で、予防の大事さに気づき、「認定栄養ケアステーションいーと奈良」を立ち上げ、運動・食事・コミュニケーションを3つを柱として健康いきいき教室を企画・運営されていること、コロナ禍で会食できない中ではオンライン会食を実施するなど、地域高齢者の食の楽しさを支える事業をさまざまな他職種と連携して着実に実施しておられる様子をいきいきとお話しいただきました。
学生からは、「環境は与えられるものではなく、作るものという言葉が心に残った」、「何事も自分から行動することが社会人になる上で大切だと思った」等の意見が上がり、自ら積極的に行動することの大切さと同時に、食の楽しさを大事にする管理栄養士の仕事にやりがいを感じてくれた時間となりました。