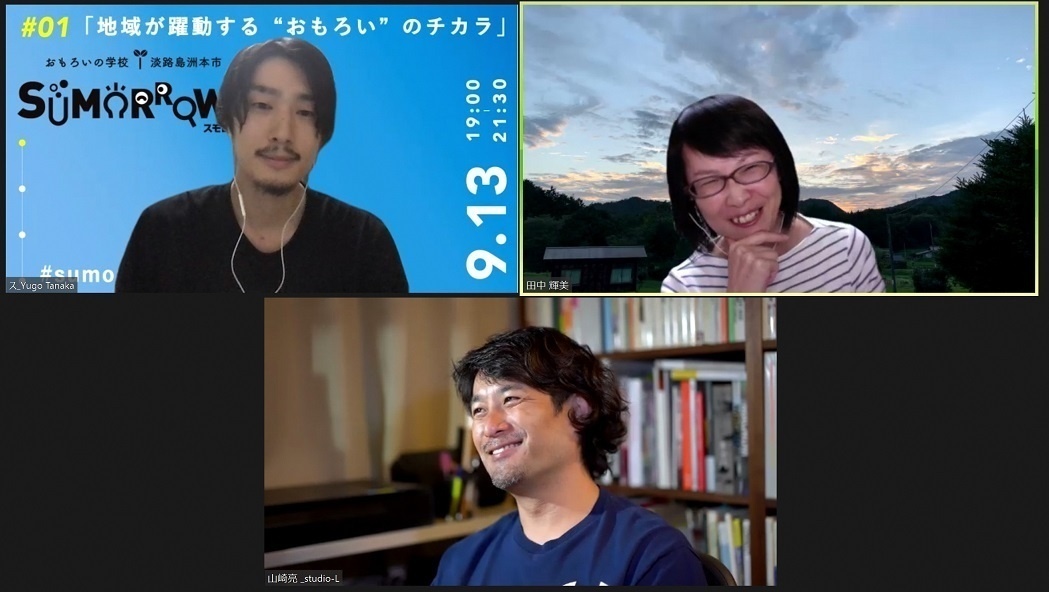【LORC】関係人口の次のステージを描く連続企画「おもろいの学校」第1回目ワークショップが開催されました
龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)が共催しているプロジェクトが始動しています。
主催する洲本市域学連携推進協議会は、全4回にわたるオンラインイベントを開催します。その第一回目のワークショップが開催されました。洲本市を第三者としての立場から見つめるゲストを迎え、100名を超える参加者とともに洲本市について考えました。
【日時】9月13日(日) 19:00-21:30
【会場】オンライン(Zoom)
【内容】
・山崎亮氏(コミュニティデザイナー)、田中輝美氏(ローカルジャーナリスト)による対談
・淡路島洲本市で続く関係人口プロジェクトの紹介
・ゲストと参加者とのクロストーク
【参加費】無料
【連続企画のご案内】~関係人口の次のステージを描く連続企画「おもろいの学校」を開催中です~
これからの地域活動に必要なのは、自分たちが信じる「おもろい」をつらぬく人たち。淡路島洲本市を舞台に「おもろい」をつくる人を応援するオンラインの学校を開校中です!
7年前から、多くの関係人口と地域づくりに取り組んできた洲本市。そんな地域を舞台に、多彩なゲストの皆さんと「関係人口」の次のステージについて語り合います。
キーワードは、ずばり「おもろさ」。
「おもろいの学校」では、活動の魅力をUPするおもろさの秘訣を学びます。辞書に載っている「面白い」ではなく、私たちなりの「おもろい」をつくりだす方法を一緒に考えませんか?
●主 催 :洲本市域学連携推進協議会
●共 催 :龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)