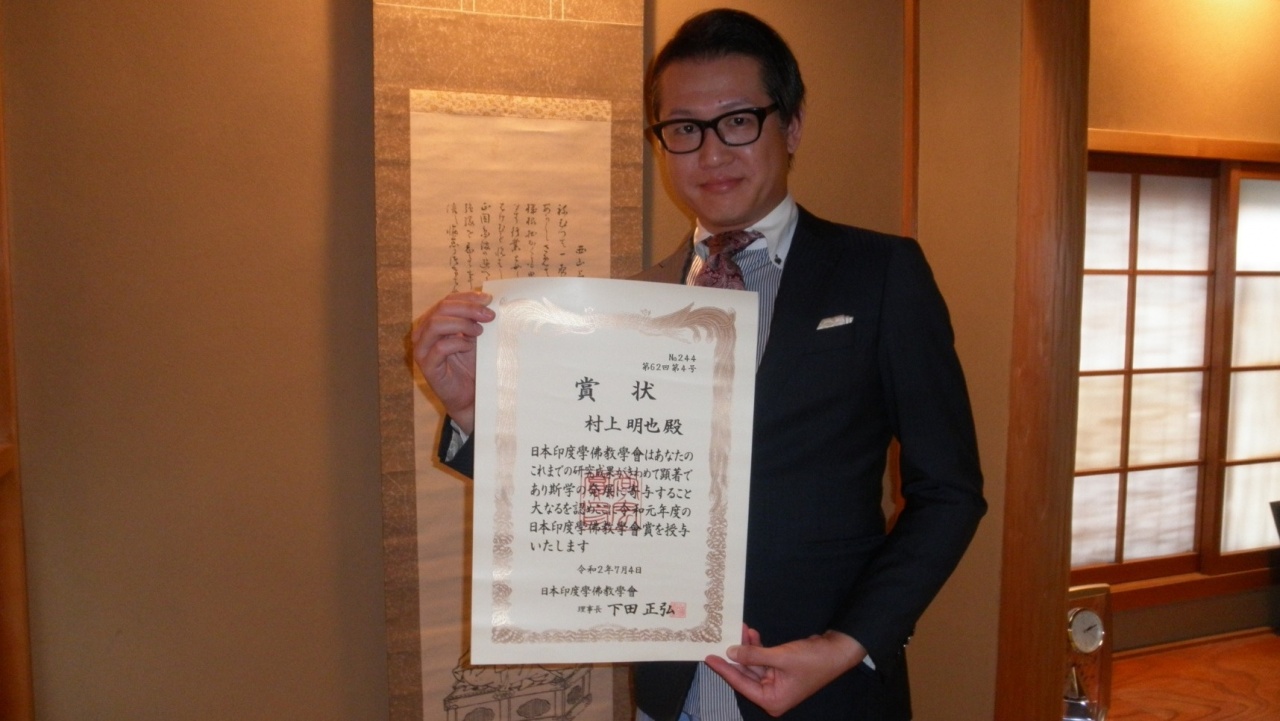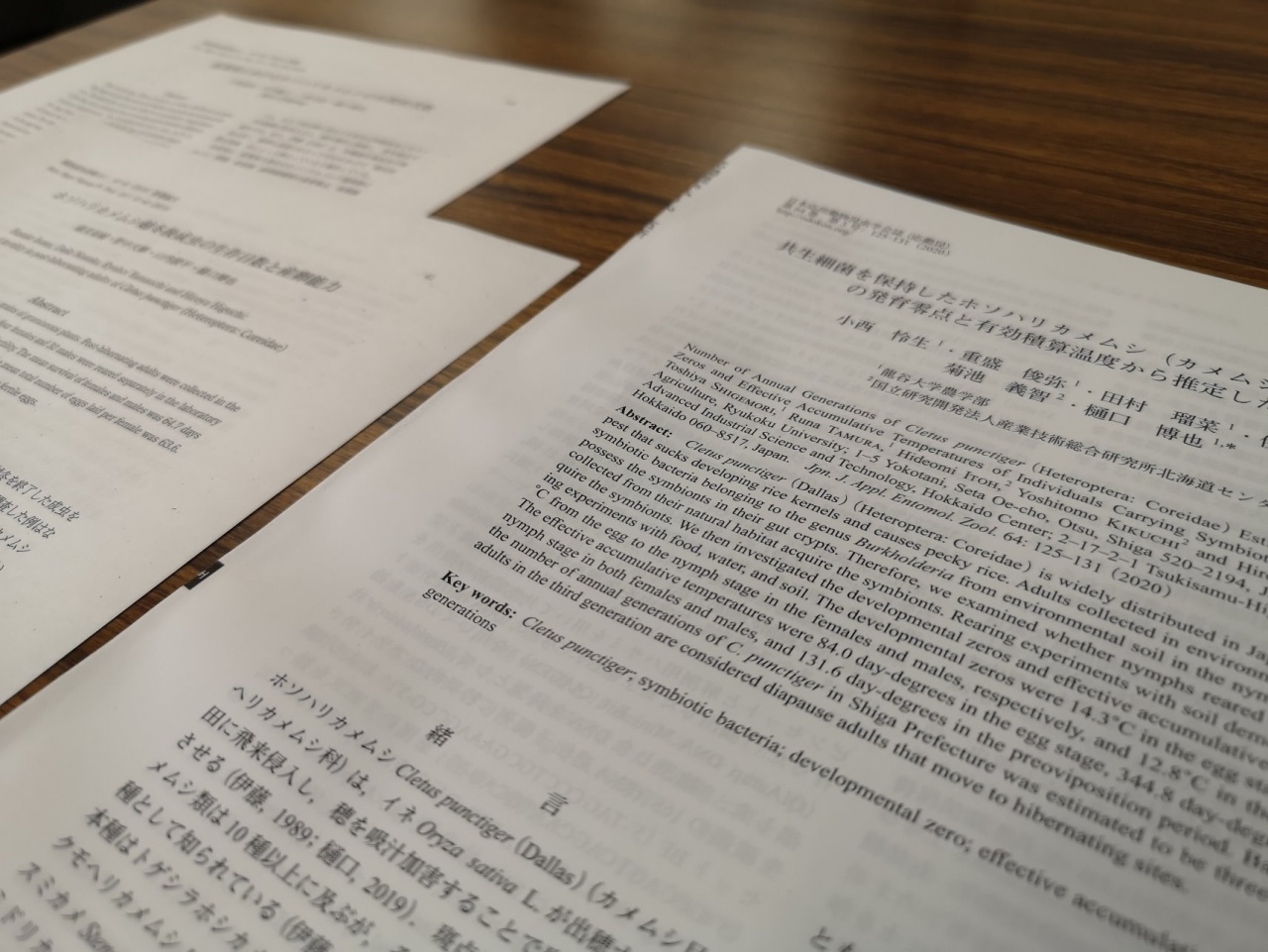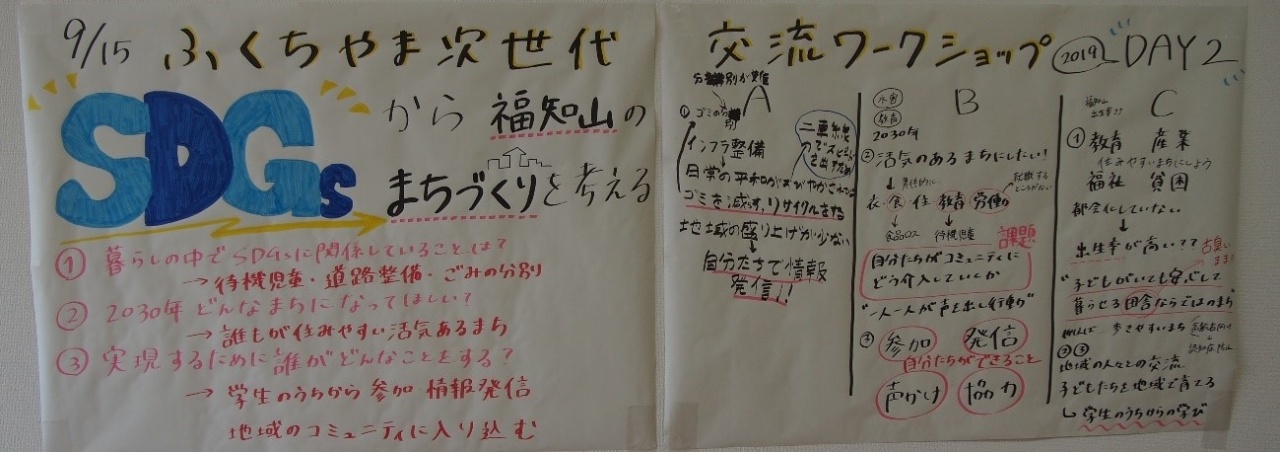「調理学実習Ⅰ」(2組)を実施しました
先日に引き続き、9月1日(火)に食品栄養学科1年生の「調理学実習Ⅰ」を実施しました。今回は、2組の学生が調理学実習室と食品加工学実習室に集まりました。
今回のメニューは、枝豆ごはん、かきたま汁、きゅうりとわかめの酢の物、かぼちゃの煮物、さばの竜田揚げ、利休饅頭です。
学生さんは、慣れない器具や調理方法に苦戦しながらも、慎重にかつ丁寧な手つきで調理を進めていました。出来上がった料理は、その一品にあった器に盛りつけます。盛り付けも料理において肝心なポイントです。
最後は、出来上がった料理を美味しくいただきました。もちろん片付けも入念におこないました。
<学生のコメント>
・品数の多さに驚いた。普段自分ひとりではなかなかこれほど作ることは難しい。
・とにかく美味しい!!
・だしの取り方が丁寧でとても勉強になった。
・さばの骨を包丁を使ってとることが難しかった。